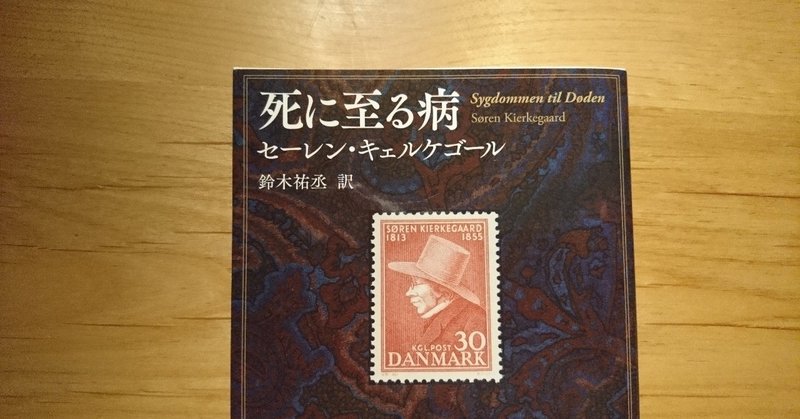
哲学ノート⑫身に覚えのある絶望
「死に至る病とは絶望のことである」。キルケゴール『死に至る病』は、そんなタイトルで第一編を始める。死に至る病でありながら、死にきれないところに絶望がある。前回の記事はそんな内容だった。↓
絶望を細かく見ていくと、その種類はひとつじゃない。キルケゴールはそう言う。その最初のひとつは、本人も気づいていないような不幸のことだ。幸せだと本人は思っている、でも本当の意味では全く違っている。
周囲の人が「そんなの間違っているよ、それはあなたの幸せにならない」とどれほど言い聞かせても、本人は聞く耳を持たない。なぜなら自分の判断は正しいと思っているし、その判断に基づいている以上、自分は幸福な選択をしたと思っているから。そういう「絶望を絶望と知らずにいる絶望(※1)」。
ある人が、真理の光に照らしてみればじつは不幸なのに、幸福であるかのようなうわべで、自分でも幸福であるようなつもりになっているとき、その人がこの誤謬から引き離されることを望むなどというのは、まずありえないのだ。(…)誤謬から引き離そうとする人をもっとも忌々しい敵と見なし、そうした仕打ちを中傷と受け取り、「幸福の息の根を止める」というよく言われる意味で、殺人のようなものと見なすのである。(※2)
例えば、周りから見たらとうてい受け入れられない配偶者に固執する人なんかは、それが自分にとって幸せだと信じている。だから、周囲がどれほど「あんな人やめておきなよ」と言っても響かないし、むしろ自分が否定されているように受け取ってしまう。誤りの内にある幸せ。
この形態の絶望(絶望についての無知)は、世間にもっともよくあるものである。(※3)
他にどんなものがあるか、と言えば、それは後の2つだ。
自分が絶望していることを意識している、したがって自分が何か永遠なものを包有している自己を持っていることを意識している絶望。
そこで、この絶望は、絶望して自己自身であろうとしないか、それとも、絶望して自己自身であろうとするか、そのいずれかである。(※4)
「自己自身であろうとしない」……それは自暴自棄になったり、自己逃避したりする、そういうことだ。もうどうでもよくなってしまって、他人になりたいわけじゃないけどとにかく自分でいたくないような絶望。
「自己自身であろうとする」……絶望しているとわかっていて、なおもそんな自分でいようとする、それは「強情」とか「高慢」とか呼ばれていて、救われることを拒否する。
苦しむ者は、救われるのならこんな仕方やあんな仕方がいいものだ、と考える。そんな願いどおりに救われるなら、彼としてはもちろん喜んで救われたい。けれども、事態がもっと深い次元の真剣なことになり、救われるべきであるということ、とくに、より高い者によって、あるいはもっとも高い者によって救われるべきであるということが問題になる場合には──どんな仕方であれ救いを無条件に受け入れなくてはならないという、この屈辱に直面することになる。
(…)
そんな屈辱に甘んじるほどにはひるんでおらず、だから自己自身のままであることに伴う苦しみの方を、しまいには選んでしまうのである。(※5)
どれも見に覚えのある身近な絶望という感じ。キルケゴールは現実主義者というか、人間に完璧な理想を託したり、多くの夢を見ることがない。興味を持った人は、実際に『死に至る病』を読んでほしいのだけれど、訳者の言葉を注意代わりに最後に置いておく。
キェルケゴールの著作は、『死に至る病』とは、読者を感傷的な気分に浸らされるために書かれたものではない。キェルケゴールは、むしろ読者──あなたのことだ──の生き方を変えるために、あなたの救いのためにこの本を執筆し、世に送りだしたのだ。(※6)
単に絶望してみせただけじゃない、生きる意味に終始苦しみながら生きた哲学者の本。絶望したときには思い出してほしい、『死に至る病』。
※1:セーレン・キルケゴール『死に至る病』鈴木祐丞訳、2019、講談社学術文庫、75頁
※2:同上、75-76頁
※3:同上、79頁
※4:同上、83頁
※5:同上、125頁
※6:同上、247頁
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
