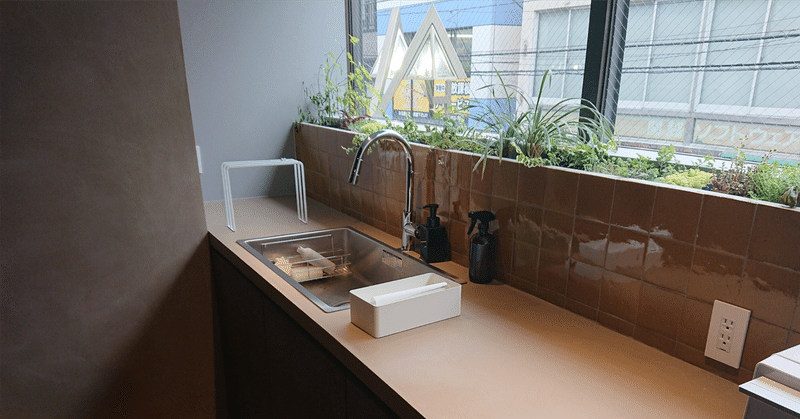
【詩を紹介するマガジン】第15回、大木実
「妻」
何ということなく
妻のかたわらに佇(た)つ
煮物をしている妻をみている
そのうしろ姿に 若かった日の姿が重なる
この妻が僕は好きだ
三十年いっしょに暮らしてきた妻
髪に白いものが見える妻
口にだして言ったらおかしいだろうか
──きみが好きだよ
青年のように
青年の日のように
大木実、1913年生まれ。1996年没。この頃に日本男児として生まれれば、戦争にまきこまれるのが必然だった。大木実も結婚直後に招集され、四年の兵役についた。そのときのことを書いた詩もある。
式もあげず旅行もせず、ひっそりとふたりは暮らした。私は毎あさ坂をくだり勤めへ通ったが、二か月後のある日の夕方、不安な予感があった召集令状を、区役所の兵事係から受けとった。赤紙の鮮やかな色が眼に沁みた。
昭和十六年というその年も、あと十日あまりで終わろうとしていた。
実生活の中で、飾らない言葉で書かれる詩。詩人といえばレトリックを駆使し韻を踏むものだ……なんて技巧には興味がない。素朴な表現が心にすっと入ってくる、てらいのない詩を書く人だ。
「きみが好きだよ」なんて、あまりにシンプルな言葉で、少しプライドの高い人なら使えない言い回しなんじゃないか。みんなまっすぐに言うのは照れるから、あるいは芸がないと思われるから、いろんな遠回しな表現でがんばるのだ。
「月がきれいですね」とか「野守は見ずや君が袖振る」とか「あなたはなぜロミオなの」と言ってみるわけだけど、どれもみんな同じことを言ってる。きみが好きだよ。言ってしまえばそれだけのこと、でもなかなか口に出せないこと。
一緒に暮らしてきた奥さんにそれを言うのは、好きな人に告白するのとはまた違ったハードルがある。「口に出して言ったらおかしいだろうか」とためらうのは、それが自然なことと思われていないからで。
でもやっぱり言いたくなるのだ。青年のように。青年の日のように。
大木実の詩は、どれもが実生活から湧きたつ素の言葉でできている。料理で言うなら、ご飯とお味噌汁みたいなシンプルさ。そして簡素でありながら人の心を動かすのは、凝った料理で人を感動させるよりずっと難しい。
最初にこの詩を読んだとき「大切に読みたい」と思った。「大事に読まれるべき詩だ」と思った。ほかの詩を粗末にしていいということではないけれど、これに関してとりわけそう感じる。
「詩を紹介するマガジン」で記事にしたものは「ウッ刺さる」と感じたものや、「生きる切なさを感じる」と感想を持ったものはあるけど、「大事にしたい」と思うものは珍しかった。
茶碗一杯のご飯を前にして「この日常が愛おしい」と味わうような、そういう趣きがこの詩にはある。たからかに「愛の詩」と呼ぶにはあっさりしていて、あっさりしているけど淡泊ではなくて。
青年真っ盛りの人がうたう愛も、それはそれでいいと思うけれど(ゲーテみたいな)、連れ添った夫婦に新鮮に語られる「好きだよ」はもっと強い。静かだけど、強い。
詩集を読んでいると、その時代の特有の兵役の色が濃くて、ああこういう空気感だったんだなと思う。「吾子一年生」という詩の中には「あかごのとき別れて/四つのとき復員して帰ってきたら/わたしをおじさんと呼んだが」と書かれていた。
そうか、徴兵されて帰ってきた父親なんて、子どもにとっては見ず知らずのおじさんだわな……。実の子どもにおじさんと言われる気持ちは、やるせなかっただろうか。それとも、そんなものだと割り切れたんだろうか。
すべてものごとには「それが終わった後の日常」がある。大木実の詩からは「その後の日常」が漂ってくる。結婚した後、復員した後。あらゆる「事後の日常」が、人生の大部分なんだと思い出す。
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
