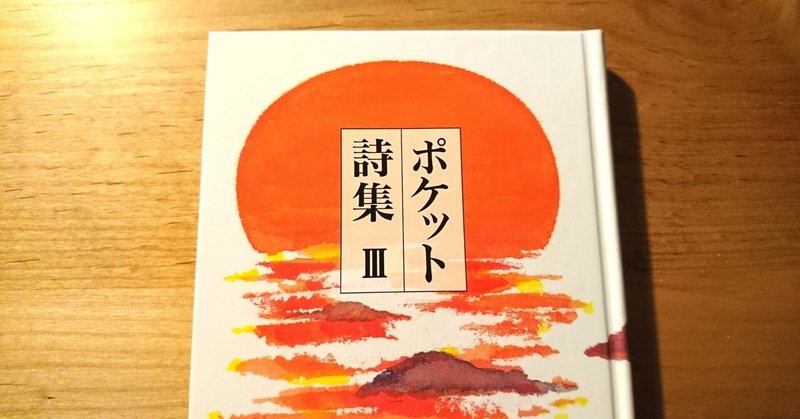
【詩を紹介するマガジン】第10回、江國香織
「江國香織って小説家でしょ」と思う人は多い。自分の中でもこの人は「小説を書く人」の立ち位置だけれど、実は詩もある。そのひとつが「父に」。
「父に」
病院という
白い四角いとうふみたいな場所で
あなたのいのちがすこしずつ削られていくあいだ
私はおとこの腕の中にいました
たとえばあなたの湯呑みはここにあるのに
あなたはどこにもいないのですね
むかし
母がうっかり
茶碗を割ると
あなたはきびしい顔で私に
かなしんではいけない
と 言いましたね
かたちあるものはいつか壊れるのだからと
かなしめば ママを責めることになるからと
あなたの唐突な
──そして永遠の──
不在を
かなしめば それはあなたを責めることになるのでしょうか
あの日
病院のベッドで
もう疲れたよ
と言ったあなたに
ほんとうは
じゃあもう死んでもいいよ
と
言ってあげたかった
言えなかったけど。
そのすこしまえ
煙草をすいたいと言ったあなたにも
ほんとうは
じゃあもうすっちゃいなよ
と
言ってあげたかった
きっともうじき死んじゃうんだから
と。
言えなかったけど。
ごめんね。
さよなら、
私も、じきにいきます。
いまじゃないけど。
最初に読んだときは、ふうんと思った。ずいぶん読みやすくて小説みたいで、あんまり詩って感じがしない。もちろんそんな区別は設けるだけ野暮だけれど、軽いエッセイを読んでいるときのような、頭の働かない感じがした。
詩の価値は、いつも時が経ってからわかる。しばらく(あるいは長い時が)経ってから、詩の一節が頭に流れてきて、ああこの言葉がいい、まさにいまの私のものだって気持ちになる。「父に」も、そういう言葉の連なりだった。
あなたの唐突な──そして永遠の──不在を、悲しめば、それはあなたを責めることになるのでしょうか。
誰もが亡くなった人に対して、そういう気持ちを抱くんじゃないか。死んでいった人は、決して私たちが悲しみに明け暮れることを望んではいなかった。むしろ日常を続けてくれと望んでいた。できたら笑って暮らしてくれと。
そういうときにふと彼らを思って涙をこぼすのは、その望みに対する裏切りに等しいのだろうか。泣いたらダメかな。亡くなった人が誰も、それを喜ばないと知っていて、それでも泣いたらダメかな。
誰か亡くなった人について──自殺した兄や、病死した祖母や、お世話になったおばさんを──思うとき、これは詩を離れて、自分の声で再生される。
あなたの唐突な、そして永遠の不在を──悲しめば、それはあなたを責めることになるのでしょうか。
私もいつか「そっち側」に行く。誰もが行先は同じだ。早いか遅いかの違いがあるだけで。自分にはまだまだ遠い先のことのように思えて、最後の「じきにいきます」のところは、聞いたことのない江國香織の声で聞こえてくる。自分のものにならない。
死んだ人は死んだ人で、私はどうしようもなく生きていて、その違いはあまりにも大きい。もうすぐそっちに行くねと、あいまいだけど確かに約束できるほどのリアリティがない。
でもいつかわかる日が来るかもしれない。私もいずれそっちに行きます、と自然に思う日が来るともわからない。
「かたちあるものはいつか壊れるのだから」。
かたちあるものは、壊れてかたちのないものになる。生身の肉体なきあと、人は記憶の中だけに存在する、かたちのないものになる。輪郭も厚みも持たないものは、もう壊れようがない。そうやって存在する。どこか場所のない場所に存在し続ける。
これは詩というより、詩みたいな小説だ。
「江國香織って小説家でしょ」と言うのは、だからすごく正しい。詩人じゃないという意味でも、生粋の小説家だという意味でも。「小説家の書く詩」という新しいジャンルが自分の中にできた。
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
