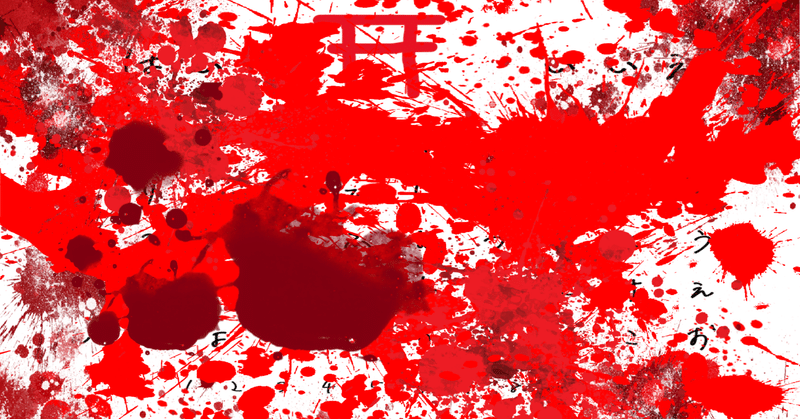
降霊の箱庭 ~第十話~
<前話>
音楽教師・神山冴雪は、空き教室の前に立った。
今やこの米野中学校にいる者なら誰でも知っている、四階の封鎖された空き教室だ。
「…………」
廊下はシンと静まり返っている。
いや、学校全体にそもそも人の気配が全くない。
最近連続する生徒の不審死。「こっくりさん」を巡る噂。極め付けに衆人環視の中で、生徒指導部の長谷川が惨たらしい死を遂げた。他にもガラス片で怪我をした生徒、過呼吸やパニック状態に陥った生徒が多数おり、グラウンドは松原市の救急車全台が来たのではというほどの大騒ぎだった。
学校本部は事態を重く見て、一週間の休校を宣言した。
ショックを受けた生徒の療養のため。そして何より、学校全体にウイルスのように蔓延している、こっくりさんの噂を落ち着かせるため。
午前中に全体職員会議が行われた後、午後も何名かが職員室に残り、作業をしている。
神山はその中からそっと抜け出し、こうして空き教室の前にやって来たのだ。
「…………」
じっ、と教室を見詰める神山。そこにいつも纏っている飄々とした余裕はない。寄せられた眉が彼女の煩悶を表している。
前後入口に張り巡らされた立入禁止の黄色いテープのせいで、教室内には入れない。廊下側に面した窓は曇りガラスで、ちらと中を窺うことすらできない。
どこまでも隔絶されたものを感じながら、神山はふと口を開いた。
「……古栗。そこにいるのかい?」
呼ぶのは、かつての同級生の名。
「懐かしいね。それに悔しい。こんな形で再会なんてしたくなかった。わざわざこっくりさんを利用して出てくるなんて、キミは自虐がひどすぎるよ」
答えは当然返ってこない。
墓石に話し掛けるような寂しさを含んだ、神山の声だけが響く。
「アタシ、音楽の先生になったんだよ。『神山さんは教師に向いてると思う』ってキミが言ったから、頑張って目指したんだ。これでも生徒から慕われてるんだからね? 褒めてくれよ」
冗談めかした言葉。
それから少し黙って……神山は小さく浮かべていた笑みを引っ込めると、改めて空き教室に相対した。
「ねぇ、古栗」
ぐっ、と拳を握り締めて。
「キミがみんなを、殺したのかい?」
しばし、沈黙が流れた。
張り詰めた空気。ただでさえ静かな廊下が、一層静まり返る。
神山はただ真っ直ぐに、空き教室を見詰めて。
ばん!!
と、曇りガラスに血の手形が付いた。
「っ!?」
驚いて身を引く。
直後に、ばん、と次の手形が増える。
上に、下に、右に、左に、見る間に無数の手形が付き、そのたびに曇りガラスが割れんばかりに震えた。
ばんばんばんばんばんばんばんばん!!
ばんばんばんばんばんばんばんばん!!
内側に潜むモノの意図は何か。
出てこようとしているのか、それとも来るなと警告しているのか。
手形に手形が重なり、そのうち重なりすぎてぐちゃぐちゃの血の跡になる。そこからつーっと雫が滑る。よく手形で花や生物を表現する子どものアート作品があるが、目の前で繰り広げられるのはまさに、それを悪趣味にしたような狂気の産物だった。
ばんばんばんばんばんばんばんばん!!
空っぽの廊下に響き渡る、激しく執拗な音。
とうとう曇りガラスは全面真っ赤になった。
それでも構わず叩き付けられる手形に、為す術もなく戦慄して……、
パーン、ポーン、と頭上のスピーカーからチャイムが流れた。
授業の終始ではなく、教師間・生徒間での連絡を告げるチャイムだ。
『神山先生、神山先生。お電話です』
放送の声。一瞬天井の方に意識が向いた神山が、慌てて正面を見直すと、あれだけガラスを紅蓮に染め上げていた手形は一つ残らず消えていた。
嘘のように。幻のように。
おぉん、と廊下にまだ残っている響きだけが、目の前で起きた現象の唯一の証拠だった。
――…………。
胸が苦しい。自分の呼吸が止まっていたことに、ようやく気付く。
その後もしばし神山は、そこから動くことができなかった。
達季はまた、夢を見た。
夢の中の『達季』は、誰かに話し掛けていた。
「〇〇さんは教師に向いてると思う」
そうかなぁと首を傾げる相手は、何故か顔の詳細がぼやけてよく見えない。赤縁眼鏡をかけているのだけは辛うじて分かった。
絵具の匂いがする。同じく霧がかかったように見えづらい周囲には、どうやらイーゼルや石膏の胸像が置かれているようだ。ということは美術室だろうか。
「キミこそ先生に向いてそうだけどね。優しいし、周りのことよく見てるし」
「そんなことないよ。僕はきっと全然向いてない」
言われた『達季』は首を振る。
「美術の知識がちょっとあるだけだよ。根暗だし、他人のこと怖いし……絶対生徒にナメられるって……。うぅ、自分で言ってて悲しくなってきた」
「何がしたいのキミは」
二人して笑い合う。
ここには、穏やかで平和な時間が流れていた。
「……あ~あ、早く大人になりたいなぁ」
〇〇は夕日が差し込む窓辺に行き、ふとそう言った。冗談めかしてこそいるが、そこには真剣な響きが込められている。
「アタシさ、学校って『箱庭』だと思うんだよね」
「『箱庭』?」
〇〇が口にした単語を、『達季』は鸚鵡返しに問う。
「そ。こ~んな狭い空間に、好きな人も嫌いな人も、真面目な人も不真面目な人も、ごちゃまぜに押し込まれてさ。息苦しいでしょ? だから箱庭」
「…………」
「アタシたち生徒は箱庭のアイテムとして配置されて、こうしなさいああしなさいって動かされてる」
「……何というか、寂しい考え方だね」
それにその理論だと、結局大人になってもまた、会社や家族という新たな箱庭に入れられるのではないだろうか。いやそもそも生きている限り、国や大陸や地球といった、さらに大きな箱庭からは出られないというオチになる気がする。
そう所感を述べると、〇〇は大袈裟に天を仰いで溜め息をついた。
「宇宙に脱出するしかないねぇ……」
「でも宇宙は大きな泡構造だから、これまた箱庭だと、」
「うるさい」
「ごめん」
きっとお互い分かっていた。
これはそう、ただの下らない妄想。気持ちだけは大人になりたい、しかし心身共にまだまだ子どもである中学生の、他愛ない会話。
「それでもやっぱりアタシは大人になりたいな。ほら、お金とか欲しいし」
「う~ん、〇〇さんらしいなぁ……」
『達季』は笑う。彼女も笑う。
ああ。
ここは、夢のような夢の空間。
<次話>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

