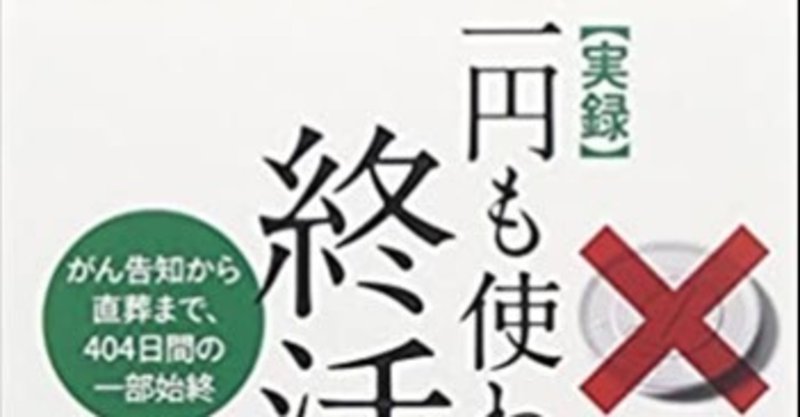
気になるガン闘病・葬儀費用の話「一円も使わない終活 がん告知から直葬」村上夏樹
この本は実際には、社労士と、友人の夫妻による共著だ。友人のご主人は、ガンで亡くなるが、告知されてから闘病し亡くなるまでの時系列のメモ(奥様が書き留めたもの)を元に、社労士の村上さんがまとめたもの。
ところどころ、今は誰が書いている内容なのか、見分けづらく感じる部分が多かった。これは編集の問題なのかもしれない。でも、読み物として楽しむというよりも、いま、闘病費用に悩んでいる人には、特に役立つ内容だと思う。気になるところを、少し抜粋してみた。
ガン闘病と費用の問題
「夫がガン宣告を受けた時、費用についてとても不安だった。しかし、結果は黒字。治療費に対する不安を抱いている人達に私の経験を伝えて、少しでも不安を和らげれれば、社会に役立つことになる。緩和ケアや直葬のことも、私の体験を語ることで、誰かのお役に立てればと思う。」(P4)
主に、治療費や葬儀の費用に焦点を絞っている。治療費+葬儀費=0円というのが、ポイントだ。巻末付録、高額療養費、傷病手当の受給方法。病院の差額ベッド料金、民間のタクシー使用、無料で使える「移送費」の条件など、実際的な費用の話が、今、治療に直面している人には助けになるはず。
費用の問題は現実の問題で、病気への不安と同時に対処していかねばならず、なかなか聞きにくいことなので、こういう本があるのは助かる。準備することで不安は解消できる。
「「病気や葬儀に直面して学んだのは、知識は無駄な支出を抑えてくれるし、収入を増やしてもくれる「重宝な道具」だということ。」「不安は目に見えず、得体が知れないが、知識というメガネをかければ、その姿が見えてくる。何に自分が不安だったのか、それが分かるようになる。」(P181)
特に、その場に至るより前に、少しずつ前に準備をしておくことで、できる限りミニマム(費用)な終活ができると学んだ。ご主人をガンで亡くした奥様の悲しみは、あまり感情的に書かれていない。奥様のメモをもとに書籍化したからだろう。それでも、終活のひとつの形を考えさせる記述があった。
がんで死ぬメリット
がんと告知されてから、亡くなるまでの期間は404日だった。いわば、この期間は、ゆっくりとですが、死に向かって夫婦で準備をしていく期間に充てられた。十分に準備をし、お別れを重ねたら、ある意味で「未練」は残らないのではないかと思わせられた。
本書は、治療費や葬儀の「費用」に焦点が合わされており、感情的な描写はとても少ないのだが「別れ」に関するコメントの中には、ひとつの達観を見る。こう言うとなんだけど、がんで死ぬというのも必ずしも「最悪な死に方」では無いということもわかる。こういう本もあるしね。
「死ぬならがんで死にたい、という医師が多いという。がんによる死は、突然背後からやってくる死ではなく、ゆっくり前から近づいてくる。だから、死の準備や家族、友人との別れをていねいにできる。さらに、緩和技術の進歩によって、今では末期がん特有の壮絶な痛みからも開放され、安らかな死が迎えられる-職業柄、こうした周辺事情に詳しいから、医師はがんによる死を望むのだと思う。・・・夫の判断能力が怪しくなり、自分の意志を明確に伝達できなくなる日がやがてくる。その前に葬儀をどうするか、夫婦で話し合う。」(P63)
人はだれでも死ぬわけだから、その時を、よく準備して逝けるなら、それはひとつの理想なのかもしれない。友人に大動脈解離で突然死したものがいるが、奥さんの衝撃たるや、なかったし。お別れも何もできなかったし。それはとても苦しいことだった。しょうがないんだけど。
それなら、正面から迫ってくる病魔を見据えながら、計画を立てつつそれに対処していくほうが良いのではないかと。でも、ガンで死ぬのは嫌だな~と思ったりもするんだけど。弱っていくイメージがあるからなのかな。
お別れは生きているうちに
終活の話題になると、葬式がメインでどう「見送るか」「お別れ」するかを問われることがある。しかし、むしろ、生きている時のお別れのほうがよほど大事だ。生きているうちに、お別れができれば、葬儀をゴウセイにして、お別れをする必要はまったくないという、ごくごくシンプルな事実に気付かされる。
「ベッドからまだ起き上がれるときに、2人の兄と姉に順番に自宅に来てもらい、「感謝の手紙」を手渡してお別れをした。直葬にすること、延命措置はしないことを、夫の口から説明してもらう。通夜、告別式をしない場合、親戚から「苦言」が出るかもしれないからだ。兄や姉は「それでいいよ」と理解してくれた。夫には兄や姉を玄関まで見送る体力はなく、応接間で椅子に座ったまま「では、これで」といった。生きているうちに有意義なお別れができた、と夫は満足気だった」(P65)
私は叔父が亡くなったときに、同じように、生きているうちにお別れをした。叔父は末期がんだったが、最期は、食べると調子が悪くなるからという理由で、一切食べていなかった。点滴も拒否していた。だから1週間が経過した時には、だんだん眠っている時間が長くなり、もうあと少しで逝くというのがわかった。
だからこそ、病室でしっかりお別れができた。旅立ちでも、卒業でも、いつかはどこかで、誰もがお別れしなければならないわけだから、それが死別でも離別でも同じことだ。きちんと向かい合って、お別れできれば、思い残すことはないことが分かる。
「目ざめれば苦しむと思い、「いやいいです」と断る。私たちの望みは、夫が痛みのない、穏やかな日を過ごして、眠る如く逝くことだった。私は、酸素マスクをつけた夫の顔を見ていた。ベッドのそばで妻が夫の手を握り、互いに見つめ合い、夫が「世話になったね」とつぶやいて息を引き取るのは、映画などフィクションの世界。危篤のときに駆けつけても、病人は目を開けないし、口もきけない。話があるなら、もっと前にしておかねばならない。」(P101)
「安置所で行う納棺の儀を、私たちは見ずに帰宅した。私も子どもたちも、緩和ケアの個室で、生前に十分に会っているから心残りはない。」(P104-105)
最期の選択は「ドライ」に見えるかもしれないけど、しっかり、生きているうちに「お別れ」をしているからこそ言えることなのだと感じた。これも、ひとつの生き方、逝き方なのだと感じ、胸が熱くなる。(著者は、あくまで淡々と書いているが、それが、かえってグッとくる)。
大人のADHDグレーゾーンの片隅でひっそりと生活しています。メンタルを強くするために、睡眠至上主義・糖質制限プロテイン生活で生きています。プチkindle作家です(出品一覧:https://amzn.to/3oOl8tq)
