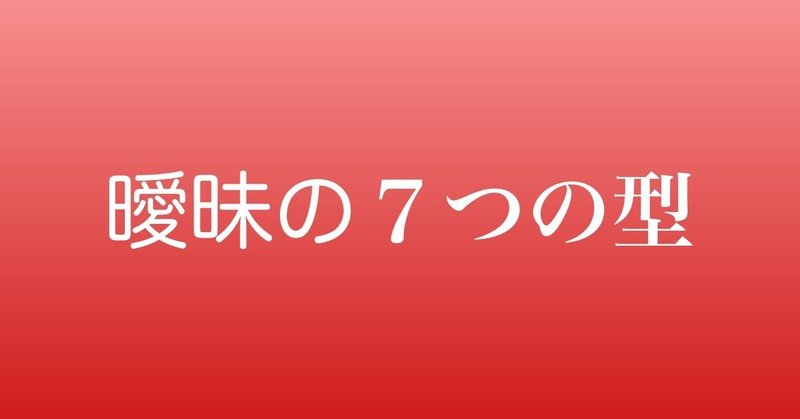
曖昧の7つの型
ウィリアム・エンプソンが1930に発表した「曖昧の7つの型」
ウィリアム・エンプソン(William Empson 1906年9月27日 - 1984年4月15日)は、英国の文学批評家、詩人。
英国ヨークシャー州に生まれる。ケンブリッジ大学で数学を専攻、のち文学批評に転じ、アイヴァー・リチャーズの影響を受ける。1930年『曖昧の七つの型』を発表。1931-1934年東京文理科大学で教え、帰国後、『牧歌の諸変奏』(1935)を発表。1937年北京大学に赴任し、1940年戦争のため帰国。1947-1952年再び北京大学で教える。1953-1971年シェフィールド大学英文学教授。その後名誉教授。ニュー・クリティシズムの重要な批評家で、自らも詩集を出している。
Wikipedia:ウィリアム・エンプソン
曖昧の7つの型
① 1つの単語または1つの文法構造が同時または多様に働く場合
② 2つ以上の意味が1つの意味に含まれている場合
③ 文脈上どちらも当てはまる2つの観念が、それゆえに関係づけられて同時に1つの単語で表現されうる場合
④ 表現されている2つ以上の意味が互いに矛盾しあいながら結びついて、詩人における一層複雑な精神状態を明らかにしている場合
⑤ 詩人が観念を見出しつつ筆をとったり、観念全体を一時に掌握しないでいたりするために、たとえば直喩が用いられても、正確にはなにものにも当てはまらず、比較された2つのものの中途にとどまっているような場合
⑥ ある表現が様々な理由で何ものをも意味せず、そのために読者は読者なりの表現を作り出すことを余儀なくされ、それがまた互いに矛盾を含みがちな場合
⑦ 単語の2つの意味が文脈上どうしても相対立する2つの意味となるために、全体の効果が詩人の精神に根本的分裂のあることを示す場合
1930年発行『曖昧の七つの型』(Seven Types of Ambiguity)
日本語は絶版ですが中古でも買えます。
---
プロジェクトにおける様々な曖昧な部分を体系化するためのヒントになるかも?的な感じで考えています。
アレとソレを組合せてみたらコノ課題を解決できるソリューションができるよね?と言うパズルをやるような思考回路です。サポートして頂いた費用は、プロジェクト関連の書籍購入やセミナー参加の資金にします。
