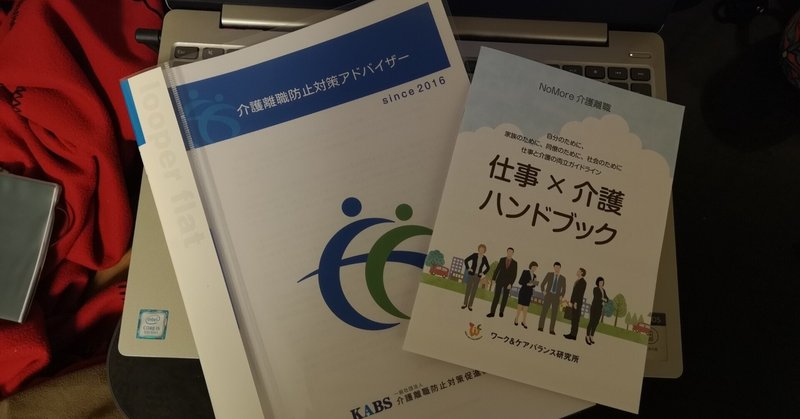
介護離職防止対策アドバイザー(R)
本日「介護離職防止対策アドバイザー」資格取得のための1日講座を受講しました。
本当は、脳腫瘍の夫を介護していた時、自分が学びたくて受講申し込みをしたのですよね。でも、彼の旅立ちの時期が近くなってしまい、受講を延期してもらっていたのです。ようやく受講できました。
これ、人事系の方、組織の管理職の方には超おススメ。介護に漠然とした不安をかかえる方にもおススメです。
https://www.kaigorishoku.or.jp/adviser-mark/
介護支援者側にも人生があり、キャリアを考える上でも重要な要素。
良く考えれば、子どもを4人育てる確率と、介護が4回よぎる確率を比較すると、後者が圧倒的に高く、状況も複雑。
多くの人が経験することなのだから、介護の話って共有されるべきじゃない?と常々思っています。
ものすごい分量の知識を1日に詰め込まれていることと、それを具体的な体験や事例を元に猛スピードで話される講師の和氣さんの勢いに圧倒されますが(笑)、多くの人に受講していただきたいなと思います。
=======
私は脳腫瘍を患った夫を20年近く支援し、夫が旅立つまでの数年は在宅介護もして看取りました。
父と祖母の介護支援経験も多少はあり、キャリアコンサルタントの資格もありますが(汗)、支援の司令塔として実際に関わるのは想像以上に知識不足でした。
介護は誰にでもすぐに出来るようになるほど甘くない。
障害者手帳の申請、会社との面談、雇用保険、介護保険、医療保険、各種年金手続き等良く分からない仕組みに直面。
資料はあるけれど、日本語のくせに意味不明。
病院通いやリハビリ、私の仕事とのスケジュール調整、服薬管理等。
関わる人もケアマネさん、ヘルパーさん、訪問看護師、訪問リハ、訪問医、福祉用具さん、等々。
書ききれないことが降りかかってきました。
ある意味、子育てより複雑で深い。
幸い、夫の場合は少しずつ状態が悪化していたので、私にも心構えの猶予がありました。
子育てもほぼ終わり、私の仕事もフル在宅のフリーランス(逆に代わりはいないし、収入がなくなるのが辛いですが)。
会社員時代のプロジェクトマネジメント経験も大活躍。
手続き先がすべて自転車圏内で、体力があるからこなせたけれど。
これが普通の会社員で、初めて降ってわいた介護だったら。
会社に支援体制がなかったら。
介護休暇・休業で自力で乗り越えるのは相当大変だよなー、と思いました。
そんな時に知ったこの講座。
介護を経験をした上で受講すると、改めて社内に「介護離職防止アドバイザー」がいることの重要性を感じます。
私も、大変なことはありましたが、仕事を諦めず続けてきて良かったと思うのです。
そして、介護に後悔はなく、多くの人生の学びがあった貴重な経験として残りました。
介護する側にも人生がある。
自分が安定していて、初めてちゃんと介護ができる。
夫を支えながら自分に言い聞かせていたのと同じことを講座で言われ、あ、あれで良かったのだ、と思えました。
育児と同じ位、介護についても企業内での支援体制が増えますように。
高次脳機能障害と介護の経験、どっかで私も話したいなー。
あなたを通じて培った貴重な経験が、今後誰かのために活かせると良いね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
