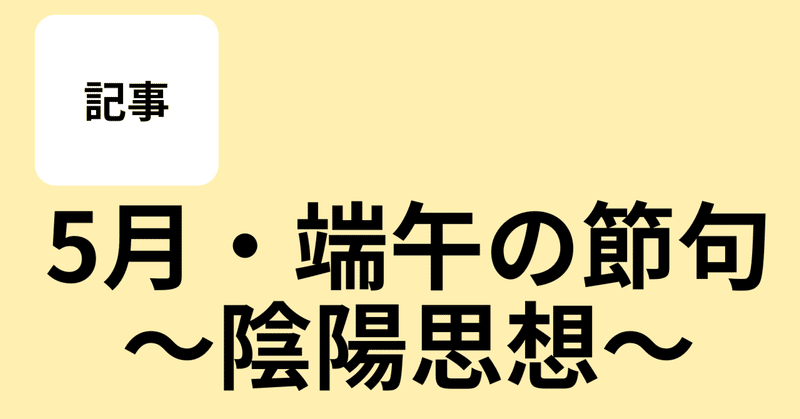
5月の端午の節句は陰陽思想からきた!
端午の節句は元々中国からきた思想の一つ。
中国でも陰陽五行思想から生まれたのが、節句という考え方。
偶数は陰性、奇数は陽性。
奇数同士を足すと陰性になります。「陽から転じて、陰になりやすい」として邪気を祓う行事がこの節句。
元々、節句は「邪気祓い」の行事ではありましたが、時が進むにつれて、いつの間にか「祝い事」に。
生きているだけでも、人の怨念や願いの塊は「邪気」となりますから、定期的に祓うことが大事。
お家の中だって、別に対して汚すことしてないのに埃が溜まったり、汚れが溜まったりしてきますよね?それと一緒^^
端午の節句は、「端午節」と言われ、古代中国紀元前340年〜紀元前278年、戦国時代・楚の時代の詩人・屈原(くつげん)に関係します。
彼は優秀な政治家でもありましたが、当時の王には彼の意見は聞き入れられず、将来を嘆いた屈原は川に身を投げました。
彼の愛国心や、文学の才を惜しむ声は大きく、無くなった日が5/5だということで供養祭が、後の端午節、そして日本では端午の節句になっていくのです。
また、端午の節句に欠かせない「ちまき」は、屈原が川に身を投げたけど、魚に食べられないようにと、池に投げ入れられたのが、今のちまきを食べる風習になりました。
そうそう、関西では「ちまき」ですが、関東では「柏餅」ですね^^
私は関西生まれなので、5/5はちまきでした。
柏餅は柏の葉は、次の葉っぱが育つまで落ちないことから、「先祖代々」に縁起がいいとして食べられるようになったもの。
端午節、端午の節句、そしてこどもの日とは、明確に違いがありましたが、今となっては全体的に同じようになっていますね^^
由来は大事だと私は感じていますが、人が育つように、思想や言語も育つもの。
なので、端午の節句とこどもの日がごっちゃ混ぜのようになっているのも、これもまた現代の良さ。
時代の移り変わりもよし。
この考え方は私は中庸に近いものだと感じていて、すごく好き。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
