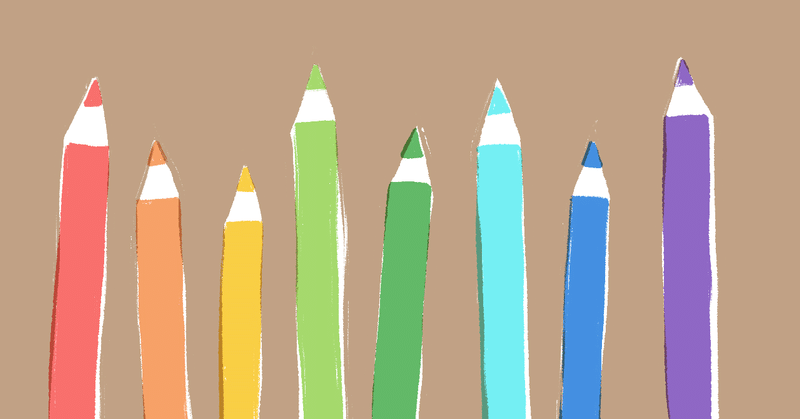
完璧な学校なんてない
息子は今5歳で、来年小学校に入学します。
オルタナティブスクールに通わせようか迷ったのですが、家の近くの公立小学校に通わせることに決めました。
今回は、そんな息子の学校選びについて書きます。
学校選びで迷う日々
息子は好きなことがとてもハッキリしていて、ハマると何時間でも何日でも飽きずにやり続ける子です。
興味をもったことを図鑑で調べたり、コレクションしたり、じっくり時間をかけてコツコツやるタイプ。
オタク気質もあるような...。
そんな息子なので、時間割がキッチリ決まっていて、みんなで同じことをするのが基本の公立小学校は、合わないのでは?と私は心配でした。
45分の授業、その後5分休憩、また45分授業、という慌ただしいスケジュールの中で時間通りに行動すること。
自分だけ違うことをすることはできず、たとえ嫌だとしてもみんな一緒に国語や算数をしなければいけないということ。
こういう環境の中で、果たして息子はイキイキと過ごせるだろうか、と。
私は、上に書いたような性格を息子の良さとして伸ばしてあげたいと思っているので、みんなについていけないとか、切り替えができなくて注意されるとかで、変に劣等感をもってほしくない。
短所は裏を返せば必ず長所になるのだから、自分の特徴を強みと思って、ありのままで伸びていってほしい。
だから、公立小より自由な環境で過ごすことのできるオルタナティブスクールへの入学を考えていました。
体験会にも何度も行ったし、複数のスクールの説明会にも出ました。
でも、いざ通わせようとなると難しい問題がたくさんありました。
オルタナティブスクールに通わせる場合の問題
問題は大きく三つ。
一つ目は「私の住む県内にオルタナティブスクールがない」ということ。
フリースクールは何校かあるのですが、オルタナティブスクールは一校もないんです。
だから通わせるなら引越しが必要になります。
環境を全て変えてまで、通わせることがいいことなのか?と悩みました。
二つ目は、「お金がかかる」ということ。
オルタナティブスクールは基本的に国からの補助金がないので、保護者は月数万円という学費を払わなければなりません。
それ以外にも入学金や給食費など、色々かかってきます。
引っ越すなら引越し費用や家賃もかかります。
それを払えるだけの経済力があるのか?ということも問題でした。
そして三つ目は、「オルタナティブスクールが本当に息子にとって良いかどうかは分からない」ということ。
オルタナティブスクールは比較的少人数のところが多く、どうしても人間関係が濃くなりがちだったりします。
ちなみに私が検討していたスクールは、全体の子どもの人数が20人程度。
その中で話し合いを数時間かけてしたり、ぶつかって喧嘩になったり、お互い譲り合ったりしているそうです。
私は個人的に、クラス替えがあるくらいの人数がいた方が刺激もあって楽しいのではと思っているので、その環境が良いかは分からないなと思いました。
一方、近くの公立小は、新一年生が約100名。
たくさんの子供たちがいるから、息子と合う子もきっと見つかるだろうし、保育園時代の仲良しさんも一緒です。
100名ならクラス替えもあるし、規模感としてはちょうどいいと私は思います。
完璧な学校なんてない
色々考えて最終的に思ったのは、完璧な学校なんてものはないのだということ。
公立小学校もオルタナティブスクールも、それぞれに良さがあり欠点があります。
使えるお金も、人手にも限りはあるし、他の子供たちもいるので我が子ばっかり見てくれるわけじゃない。
だから、「この学校に行きさえすれば絶対大丈夫!」なんて学校はないのだと。
大切なのは、どの学校に通わせるかではない。
親が「我が子にどう育ってほしいか」という軸をしっかり持ち、それを実現するために親として全力でサポートすることが大切なんだ。
「どんな環境であっても、私が息子の良さを見つけて認めて伸ばしていくぞ」という気持ちがあれば、何か問題が起こっても、その時の息子の様子を見ながら柔軟に対応していけます。
今は、不登校が過去最多という問題もあり、公教育でも、公教育の外でも、本当に多種多様な選択肢が色々出てきています。
だから、公立小に行ったからといって絶対そこに通わなければいけないわけではなく、色んな組み合わせが可能だろうと思います。
もし息子が学校に馴染めず行きたくないと言えば、フリースクールに通わせるという手もあるし、ホームスクールという選択肢もあります。
ということで、色々悩んだり、周りの人にも相談したりした結果、オルタナティブスクールではなく公立小学校に通わせよう、と決めました。
ただオルタナティブスクールに興味があることは変わらないので、これからもオルタナティブスクールの情報や、それについて私が考えたことを発信できればと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
