
全国のめぐるびとが一堂に会す、「日本の食卓会議2023」開催!
「めぐるめくプロジェクト」は、「農と食がめぐり続ける、やさしい世界をつくる。」をビジョンに掲げ、2022年9月に活動をスタートしました。日本全国をめぐり、農業・水産業・畜産業などの“タベモノヅクリ”を担うプレーヤーと出会いながら、私たちにできるチャレンジのサポートの在り方を考え続けています。
そして今回、活動開始から1年を経て、日本全国の食と農に関わるプレーヤー="めぐるびと"たちが一堂に会する「日本の食卓会議」を開催しました。私たちの代表的な取り組みである「食卓会議」は、食を起点とした地域へのフィールドツアーや交流会を通じて地域と地域の学び合いを生み出す プログラムです。これまでで20以上の地域の「エリアハブ」が、各地域で内外のプレーヤー同士を結び、地域と地域、さらには地域と企業の共創を生み出してきました。
(これまでの食卓会議のようすは、noteのレポートをぜひご覧ください。)
食卓会議とは…地域へのフィールドツアーや交流会を通じて、地域間の学び合いを生み出すプログラムです。地域内だけではなく、地域外からの多様なプレイヤーの関わりが、地域内に新たな食と農のチャレンジを生み出す循環につながることを目指しています。
全国各地から参加者が集まった「日本の食卓会議2023」は、愛知県豊橋市でおこなわれました。遠いところでは、なんと佐渡島から8時間かけて参加してくれた方も!このレポートでは、「めぐるめくプロジェクト」と日本の食の魅力を詰め込んだ、盛りだくさんな1日をお伝えします。

東三河の地で、「明るい食」の話をしよう。
「私たちは、“明るい話”がしたいんです」
100名を超える参加者が着席する会場で、「めぐるめくプロジェクト」の発起人である三菱地所の広瀬が最初に聴衆に投げかけたのは、そんな一言でした。今、日本の農業・水産業・畜産業などの農と食をとりまく業界には課題がたくさんあります。広瀬自身、「めぐるめくプロジェクト」を通して日本全国を訪れるなかで、その現状や課題感を肌で感じてきたと言います。
「ただ、感じたのは課題だけではありません。各地域でポジティブなチャレンジが広がっていることも実感してきました。ネガティブなワードで不安を煽るのではなく、農と食の明るい部分にスポットライトを当てていきたいと思っています」

「日本の食卓会議2023」、開催場所となったのは愛知県豊橋駅至近にある「ホテルアークリッシュ豊橋」です。「東三河」と呼ばれる愛知県の東側の海から中山間地域までのエリアで、豊橋市は玄関口として栄える町。静岡県浜松市と同じくらいの規模感で、人口75万人の町です。そして、農業や漁業を始め、「農と食」にまつわるさまざまなプレーヤーが集まる豊かな場所でもあります。
広瀬に続き、開催の挨拶では、株式会社サーラコーポレーションの代表取締役社長兼グループ代表・CEOの神野吾郎さんから、東三河エリアの紹介がありました。

「豊橋は日本の真ん中に位置する豊かな町です。今、この豊かさを維持していくために日本全体で、突破口を見つけることが求められています。東三河もさまざまな形でチャレンジしているところです」
2008年にサーラコーポレーションが豊橋駅前の百貨店跡地を引き受けて開発したのが、会場となった『ホテルアークリッシュ』を含む複合商業施設「COCOLAFRONT(ココラフロント)」です。豊かさへの架け橋として、「ここから始めよう」という意味合いを込めた命名であると、神野さんは教えてくれました。
続いて登壇したのは、中部ガス不動産株式会社代表取締役であり、『ホテルアークリッシュ』の社長も務める赤間真吾さんです。東三河で計画している「東三河フードバレー構想」について説明がありました。

「私たちが目指しているのは『フードクリエイターの聖地』です」
赤間さんの話した「東三河フードバレー構想」は、幅広く食に関わる人を「フードクリエイター」と呼び、彼らの活動拠点となっていく構想です。
農業・漁業・畜産業などの生産者だけでなく、調理する人々、物流に携わる人々、家庭で料理を楽しむ人まで、幅広い「フードクリエイター」としているとのこと。ただ単に食材や料理を提供するだけでなく、環境やウェルビーイングへの配慮、食の持続可能性の追求などに取り組んでいく「未来のフードクリエイター」を発掘・支援していくことをミッションとしています。
東三河内では、すでに具体的な動きがあると説明する赤間さん。例えば、地元の生産者と飲食店のマッチング「Farm to Table」、子ども料理教室など地産地消イベントの開催、東三河フードクリエイターアワードも実施を予定しています。今後は他地域との連携もおこなっていきたいと考えていた際に、めぐるめくプロジェクトと出会ったといいます。
「東三河だけでやりたいわけでも、自己満足のために活動するわけでもありません。もっと他の地域との交流やマッチングを通して発展させていきたい。今日、実際にさまざまな地域から集まった方々を前にお話できることができて幸せです」

開会の挨拶、最後に登壇したのは三菱地所株式会社プロジェクト開発部長の吉村です。不動産会社である三菱地所が、「めぐるめくプロジェクト」をどのように位置づけて推進しているのか。改めて参加者に向けて、未来の構想をお話ししました。
「我々は不動産会社ですから、直接なにか“タベモノづくり”をすることはできません。ですが、不動産会社として場や機会をつくることで貢献できるのではないか、と考えています」
2025年11月、三菱地所が建設を進めている「内神田一丁目計画」のなかで、「食と農の産業支援施設」をつくる予定になっています。目指すのは、さまざまな食のプレーヤーが交わりながら、新しい未来をつくっていくような場です。
「『あそこに行けば、食に関して取り組む誰かがいる』と、各地域からみんながふらっと立ち寄れる、部室のような場所をつくっていきたいと思っています。本日は1年の集大成であり、通過点でもあります。農と食を通じた地域と都市の豊かな関係づくりは、自分たちだけではできません。今日お集まりのみなさんと、協力してつくり上げたいと思います」
基調講演:農と食がめぐると、やさしい世界が訪れる。

基調講演のスピーカーとして壇上に上がったのは、株式会社TeaRoom代表取締役の岩本涼さんです。9歳から茶道にのめり込み裏千家茶道家としての顔も持ち、起業家でもあります。「対立のない優しい世界を目指して」という企業理念のもと、お茶を中心としたさまざまな取り組みをおこなっています。
今回は、「農と食がめぐると、やさしい世界が訪れる。」というテーマで講演をお願いしました。岩本さんが講演のなかで繰り返し触れたのは、企業理念にもある“対立”や“優しさ”というキーワードです。
「私が茶道家や起業家として活動するなかで気づいた、さまざまな“対立”がありました。お茶の生産者と茶道文化など『産業と文化』の隔たり、お茶業界とその他の業界が分断されている『業界と業界』の対立、そして生産から販売までの工程が交わらない『工程と工程』の分断です。これらの対立を解決し、新しい産業をつくっていくことを、我々のミッションとしています」
それぞれの“対立”について解説しながら、岩本さんが語ったのは「対立をなくし、つながりをつくることが、いかにイノベーションを起こして業界を豊かにするか」ということ。具体的な事例も交えつつ、ひとつの業界や手法に囚われずに新たな価値を生み出していくお話に、日本中で活動する参加者の方々も引き込まれていました。
「対立をなくして転用していくのは、自分だけではできないと認識を持つことが非常に大切です。それぞれが自分たちの知見や顧客をシェアしあって、一緒に成長していく姿。それがこれからの時代的なんじゃないかなと思っています」
岩本さんは「めぐるめくプロジェクト」も、お互いの価値をシェアして新しい豊かさを産んでいく土壌になりうると話します。そして最後に、「やさしい世界」に変えていくためのヒントを、お茶に例えて参加者に呼びかけたのが、とても印象的な講演でした。
「お茶の成分は、水溶液中の0.3%です。社会の0.3%が変わるだけで、世界もお茶のように色が変わっていく。今日参加している方々の活動が拡張されて社会に届いていく希望を持って、一緒に行動していけたらと思います」
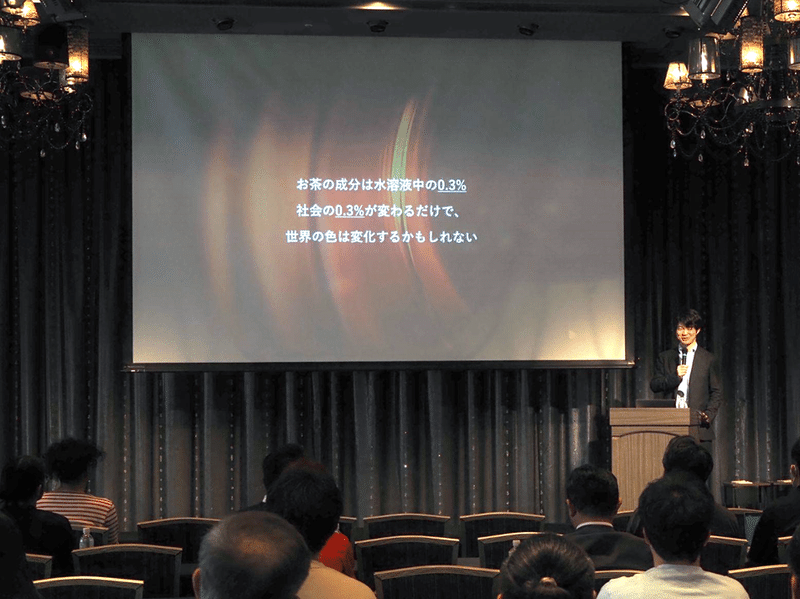
パネルトーク①出会いの場はタベモノヅクリの価値を高めるか?
続いて行われたのは、2つのテーマでのパネルトークです。それぞれのテーマに即した活動をされてきた方々にお話を伺いました。今回のレポートでは、特に印象的だった対話を一部引用してお伝えします。パネルトークの雰囲気を感じ取っていただければ嬉しいです。
最初のテーマは「出会いの場はタベモノヅクリの価値を高めるか」です。作り手と使い手と売り手の出会い、民間と行政の出会い。さまざまな出会いを生んできたおふたりをゲストにお迎えし、場づくりの方法から参加者同士のいい関係の築き方まで、幅広く伺いました。

<登壇者紹介>
鈴木正晴/株式会社コンタン代表取締役
「ニッポンのモノヅクリにお金を廻す」を旗印に、日本全国のスグレモノを発掘・国内外へ発信。雑貨・食料品のセレクトショップ「日本百貨店」創業や、缶詰専門店「カンダフル」などのセレクトショップのプロデュースを通じ、一貫してニッポンのモノヅクリと都心マーケットを繋ぐ活動を行っている。
松尾真奈/霞ヶ関ばたけ代表
大学在学中、京都府・京丹後市にある野間地域にて「田舎で働き隊」として活動。そこで出会った人や風景に魅了され、2013年農林水産省に入省。現在は千葉県農林水産部に出向し輸出施策等を担当しつつ、2018年より、食と農林水産業の学びと対話のコミュニティ「霞ヶ関ばたけ」の代表を務める。これまでに開催した勉強会は190回以上。
モデレーター:岡山史興/70seeds株式会社
岡山:イベントの場は、人や情報など何かしらの出会いを求めて参加する方が多いと思います。「霞ヶ関ばたけ」では、どんなことを意識して場づくりをしていますか?
松尾さん:私たちにとって場づくりは「種まき」のような感覚で、その場の出会いが後にいろいろなところで芽が出るイメージです。対話を通して参加者同士のつながりが生まれる仕掛けをおこなっています。
岡山:例えば、どんな仕掛けを?
松尾さん:単純に「話を聞いて終わり」というインプットの会ではなくて、参加者同士や自分自身がどう感じたのか、どう活かしていけるのかを振り返る、対話の時間を設けています。
岡山:対話の時間、いいですね。
松尾さん:はい。考え方が違う人たちが集まると、もちろん議論になることもあります。ただ、そのぶつかり合いこそ、世の中の課題が見える瞬間だったりもして。 相手が大事にしている価値観について話し合う場があることで、議論の解像度が上がるのを感じます。
鈴木さん:僕らは小売店として出会いの場をつくっているので、ガチンコ勝負です。最初は「買い人と作り手がつながる場所になればいいな」くらいの気持ちだったんですが、お店を始めてからお金を出してもらうことの厳しさを実感しました。
岡山:たしかに「販売」という場づくりは、また違った難しさがありそうですね。
鈴木さん:ただ僕らも、松尾さんがおっしゃっていた「ぶつかり合い」と一緒で、お客さんの声をちゃんと作り手に伝えようと思ったんです。それを伝えなきゃ、僕らがやっている出会いの場の意味が半減しちゃうなって。そのうち、つなぐだけじゃなくて僕ら売り手や周りの人たちも巻き込んでいくスタイルになりました。
岡山:先ほど岩本さんが基調講演で話していたとおり、知見や価値観をシェアし合う関係ですね。
鈴木さん:そう、持っているものや感じていることを全て隠さずに発信していく。そういう出会いの場が、僕らができる場づくりなんじゃないかと感じています。
パネルトーク②次の世代につづく食と地域をつくる“デザイン”とは?
続いてのテーマは「次の世代につづく食と地域をつくる“デザイン”とは」。パッケージデザインを始めとして、食や地域と深い関わりのある「デザイン」について伺いました。デザイン的な視点を持って、地域や食を見るとはどういうことなのでしょうか。

<登壇者紹介>
佐藤哲也/ヘルベチカデザイン株式会社代表
2011年、郡山市にHelvetica Design株式会社を設立。福島の基幹産業でもある農業を中心に温泉街の再生プロジェクトや地域観光のリブランディングなどを担当。また都市再生推進法人として郡山市の都市再生整備計画にも参画している。地域や産業、観光などの魅力をデザイン活動を通じ発信している。
種田憲人/株式会社タスキ代表取締役
豊橋市に移住し、自治体や地元企業、大学と連携をしたコンサル事業等を展開。脱炭素を目指す社会情勢と研究開発が進んだ技術の社会実装を目的に、2021年に豊橋技術科学大学にて株式会社パワーウェーブを共同創業し経営全体を担うほか、専業農家を中心とした豊橋百儂人の事務局長として、地域に根ざした生産者のあり方を提案する活動を提案。
髙木章雄/emCAMPUS FOOD料理長
料理人として浜松のホテルやシドニーの総領事館、東京の有名ホテルなど、さまざまな場所で料理の腕を磨く。日本一の野菜の生産地である東三河に興味を持ち、emCAMPUSで地産地消やSDGsの取り組みに関わる。
モデレーター:大森愛/70seeds株式会社
大森:ここにいるみなさん、それぞれご自分の活動を「次世代まで続けたい」と思っていると思います。そして、それを“続けられる”ように設計していくのが、まさにデザインなんじゃないかと。佐藤さんは「ロングライフデザイン」という言葉を使い続けていますが、どういった意味合いで使われていますか?
佐藤さん:僕らはただ「古いものは良い、だから残そう」という感覚ではなくて、それを使い続ける生活をどうやって手にできるか、ということを考えています。例えば、岩手の鉄瓶はかっこいいけれど、ちゃんとメンテナンスする手間暇をかけられないと錆びてしまいます。物だけでなく、僕らの生活そのものがロングライフになっていない。それを変えていきたいという活動です。
大森:ありがとうございます。続いて、種田さんは地域づくり、つまり生活をつくっていくお仕事かなと思いますが、どのようなモチベーションで活動されているのでしょうか?
種田さん:僕たちはゼロからつくるのではなく、既存のものをどう生かすのかを考えています。東三河という地域や、今の時代だからこそおもしろいと思えることを発見しつつ、表現していくところにおもしろみを感じていますね。
大森:ありがとうございます。そのなかで、特に東三河の食について活動しているのが髙木さんだと思います。次の世代に活動を続けていくために、チャレンジしていることがあれば教えてください。
髙木さん:そうですね、私のところには「どうやって調理したらいいかな」という規格外の野菜がよくやってきます。そのとき、すぐに否定的にならず、活用して生み出すことを意識しています。なかでも、若い人たちのアイディアをどんどん取り入れていくことを大切にしていますね。
大森:まさに、次世代に続けていくための取り組みですよね。
髙木さん:次世代という意味では、生産者さんの後継者問題も気にしています。生産者さんと直接話すと、組織化などで豊橋の農業を絶やさないようにしているとも聞いて。それぞれの立場で、できることをしていきたいと考えています。
大森:属人的に活動される一方で、仕組みにしていくことで次世代にも渡していける側面もあるんでしょうかね。佐藤さんはどう思われますか?
佐藤さん:そうですね。個人的には、仕組みを“作る”というより、仕組みに“なっていく”のが緩やかでいいかなと思っています。まずは大人たちの活動を見せることで、若い人たちにも「こうやっていいんだ」と思ってもらう。それが「いい町」を自然につくっていくことになるのかなと思います。我々がどういう生活を送るのかが根底にあり、その上にデザインがどうあるべきかを考えていく必要があるんだと思います。
大森:ありがとうございます。「じゃあ実際どうやるのか」というのが一番難しいと思いますが、ご参加のみなさんにぜひそれを考え続けてもらえたらと思います。このパネルトークを聞いて感じたことを話せる相手が、今日の会場にはたくさんいます。「めぐるめくプロジェクト」の場が、惜しみないシェアの場になったら嬉しく思います。
エリアハブとの対話に参加!オープンテーブル
昼食を挟み、午後の最初のプログラムは4ヶ所に分かれてのオープンテーブルです。全国の各地域から集まった「エリアハブ」や「クリエイター」が、テーマごとにトークセッション形式の対話をおこないます。参加者にも聞くだけでなく対話に混じってもらい、交流を促す目的で少人数でのオープンテーブルが設けられました。
セッションは2部構成で、参加者は各回4テーマの中から興味のある1テーマを選び、参加します。参加者同士でも「お互いの話が聞きたい」という声が上がるほどのホストとテーマ。各登壇者の詳しいプロフィールは、こちらをご覧ください。

【セッション1】
■ 地域発展につながる共創価値のつくり方
一平ホールディングス・村岡浩司さん × 中部ガス不動産・兵藤太郎さん
■共創や価値循環の最初のキッカケは誰がつくるのか
金楠水産・樟陽介さん × めぐるまち国分寺・南部良太さん
■プロダクトは、地域活性化のヒーローになれるか
稲とアガベ・岡住修兵さん × t0ki brewery・藤原敬弘さん
■貨幣価値だけでは測れない、令和の価値基準とは
FARMAN・井上能孝さん × ナオライ 三宅紘一郎さん × そにのわのkatte・アノタイ・オウプカム(オング)さん、森岡奈月さん
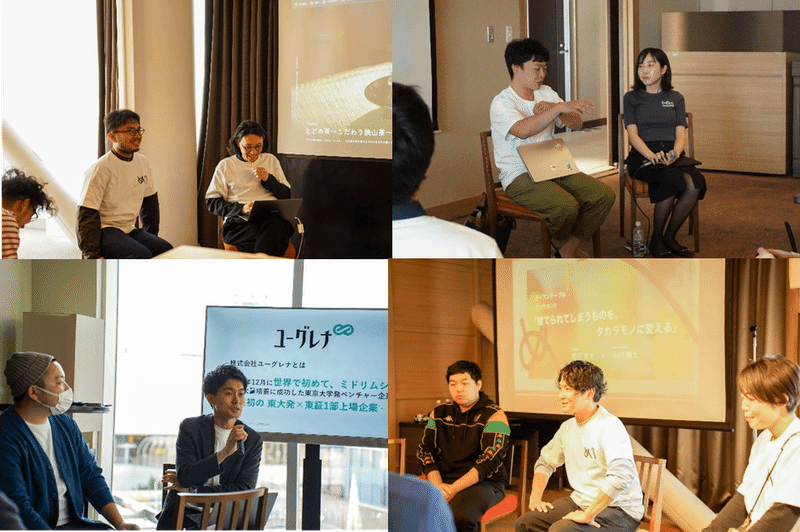
【セッション2】
■おやきプラットフォームが、日本の地域を救う
Huuuu・藤原正賢さん × TETOTETO・井上豪希さん
■地酒のように、地魚が地域を育む日が訪れる
伊東(敷嶋)・伊東優さん × リージョナルフィッシュ・石井愛可さん
■互いの企業価値を高める共創を、いま始める
haccoba・佐藤太亮さん × ユーグレナ・井上陽介さん
■捨てられてしまうものを、タカラモノに変える
fabula・町田紘太さん × loss is more・小川翔大さん
各セッションの中でどんな会話が繰り広げられたのか、一例としてご紹介すると、「捨てられてしまうものを、タカラモノに変える」にて廃棄物を圧縮した新素材をつくるfabulaの町田さんと、捨てられてしまうカーネーションをジンの材料として生まれ変わらせたloss is moreの小川さんのトークでは、それぞれが“捨てられてしまうもの”に目をつけたきっかけや、実際にどのようにアイディアを形にしていったかなど、お互いの考え方に共感しながら聞く姿がありました。また、「実はこういう廃棄物で困っていて……なにか使い道はありそうですか?」といった参加者の飛び入り相談も。少人数で実施するオープンテーブルだからこその会話が生まれていました。トークが終わってからも参加者との交流が続き、設定されていた40分では「時間が足りない!」という声も上がるほどの盛り上がりでした。
未来をともにつくる、チャレンジャーピッチ
オープンテーブルを終えると、参加者は再度、元の会場へ。最後のプログラムとして、5つの地域から集まったチャレンジャーのプレゼンがありました。それぞれの地域ならではの活動をご紹介します。

吉開仁紀さん/道の駅とよはし(愛知)
「道の駅の可能性ってのは、“ただの休憩施設”や、ただ野菜を売る場所では、もったいない。それんだけのもんじゃないんです。地域に眠っている資源を、いかに地域のみなさんや観光客の方々に届けるか。それを考えながら、日々さまざまな活動をしています」
前日の「穂の国めぐるツアー」でも訪れた「道の駅とよはし」。東三河エリアの野菜やご当地品の販売のみならず、地域の生産者と一緒に商品開発をおこなうなどの取り組みを行っています。

立野嘉之さん/北陸ポートサービス株式会社(富山)
「天空の城ラピュタに『“土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう”。どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんの可哀想なロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ』というセリフがあります。その通りだと思いますが、今はまだ残念ながら武器やロボットの方が儲かる社会です。この現実に向き合いながら、じゃあどうやって良い社会をつくって作っていくかを考えています」
北陸ポートサービス株式会社は、富山県射水市で「地域資源循環」をミッションに、木質廃材の堆肥化や、未利用間伐材を燃料にした木質バイオマス発電をおこなっています。農業や家庭菜園で堆肥を使い、よりよい循環を起こすための活動をしています。

中野直子さん/合同会社Absolute(愛知)
「『コカ・コーラとペプシ、どっちにしようかな』という相対的な状況ではなくて、『絶対にコカ・コーラしか飲みたくない!』という絶対的状況。それを作りたいと『絶対的』という意味の“Absolute”を社名にしました。みなさんのやりたいこととバイヤー視点と掛け合わせて絶対的価値を生み出したいときは、ぜひ私にお声がけください」
愛知県豊橋市のマーケティング会社、Absolute(アブソルート)では、しっかりとしたリサーチのもと、商品やサービスの価値を生み出し、広めています。「穂の国めぐるツアー」で訪れた「イノチオファーム」のミニトマトのブランディングも行っています。

山田恵也さん/株式会社CYCLE(福岡)
「2023年6月におこなわれた福岡食卓会議で生まれた企画が、生ごみ100%で野菜を育てる超循環型URBAN農園「CYCLE FARM」です。まずは福岡で実証実験をして、今後は全国各地で同じモデルを広めていきたいと考えています」
フードロス事業に取り組んでいる山田さんが、食卓会議をきっかけに始めた「CYCLE FARM」。土を使わず、生ごみだけで野菜を育てます。作った野菜はすべて無料で子どもたちに届ける仕組みを設計。未来に向けて、収穫体験や料理教室などの食育も企画しています。

鈴木将さん/SUZU GROUP(新潟)
「僕の目標は、2030年に新潟を美食都市にすること。高級な料理が食べられるという意味ではなくて、地域のことを知って食を楽しむ場です。ちゃんとビジネスとして成功する形を僕は長岡でチャレンジしたいし、モデルケースとして全国に広まれば、地方でのビジネスのあり方も変わっていくんじゃないかと思っています 」
新潟県長岡市で、店舗事業、観光事業、食品の開発や加工、プロデュース、教育事業、畑の体験プログラム、ケータリングなど幅広い事業をおこなうSUZU GROUP。長岡市と新潟市で地域の食材を使った飲食店を10店舗経営し、観光資源としても活用しています。また、地域の生産者の声をもとに、オリジナル商品の開発などもおこないます。
地域間のコラボレーションで生まれた、新たな価値
最後に、この1年間で「めぐるめくプロジェクト」をきっかけに生まれたふたつのお酒の紹介がありました。野沢温泉食卓会議をきっかけに生まれた「haccoba×野沢温泉蒸留所」のクラフトサケ『Vert』と、宮崎県の日向夏を材料に稲とアガベが開発した、「めぐるめくプロジェクト」オリジナルの限定生酒です。
2023年8月におこなわれた「野沢温泉食卓会議」で野沢温泉蒸留所を訪れ、その場で「ジンを蒸留した時に、ボタニカルのカスが出る」と聞いたhaccobaの佐藤さん。「カスをお米と一緒に発酵させたらおもしろいのでは」と現地で盛り上がり、そのままクラフトサケを作ることが決まったと話します。
「僕自身、野沢温泉が好きで何度も行ったことがあります。でも、観光客として野沢温泉蒸留所に行っても、ここまでスムーズに話は進まなかったんじゃないかな、と。『めぐるめくプロジェクト』という信頼のあるコミュニティを通して、キーマンに出会えたからこそ、コラボレーションの話が早かったように思います」

また、「めぐるめくプロジェクト」を通じて宮崎県の特産品・日向夏で限定酒を作った、稲とアガベの岡住さんも、地域間でのコラボレーションの魅力について語りました。
「クラフトサケの魅力は、3つあります。地方創生との相性がいいこと、原料さえあればコラボレーションしやすいので出会いがお酒になること、そして未知の味が生まれる可能性があること。おいしいお酒に出会ったら、人はその地に行きたくなります。メディアとして、お酒とのコラボレーションを活用してみてください」
クロージング「めぐるめくの価値ってなんだろう」

長いようであっという間だった1日の締めくくりに、事務局の広廣瀬と岡山が改めて登壇。クロージング・トークとして、「めぐるめくプロジェクト」の価値について話しました。
広瀬:今日こうやって集まってみて、“一堂に会すこと”の価値をどうお考えですか?
岡山:ものすごい偶発性があったなって思うんですよ。今は簡単にSNSでつながれる時代ですけど、やっぱり実際に会って伝わるものって全然違う。お互いの事業にかける必死さっていうか、そういう雰囲気まで伝わったんじゃないかと思います。
広瀬:それぞれの活動内容だけでなく、そこにかける熱量みたいなものが感じられましたよね。
岡山:ここに集まっている人たちは、事業が成功している“上がった人”じゃないのがいいなと思ったんですよね。どういうことかと言うと「もう稼いで悠々自適に過ごして道楽でやっています」みたいな人じゃなくて、みんなひいひい言いながら必死に事業をやっている。だからこそ、お互いにすごく刺激を受けたんじゃないかと思いました。
広瀬:わかります。お互いにリスペクトし合える仲間が広がっていく感覚がありますよね。とはいえ、そういう結びつきやコミュニティって他にもたくさんあると思うんです。そのなかで、じゃあ「めぐるめくプロジェクト」の価値って、一体どこにあるのだろう、と。
岡山:僕が感じているのは“形になる”と思えること。今日のトークのなかでも、みんな『あ、この人と一緒に何かしてみたいな』と考えたと思うんです。僕も、オリジナルのクラフトサケを作りたい!と思いましたし。みんな具体的に動いている人たちだからこそ、なんとなくの「いつか何かやりましょう」で終わらない。この人たちだったら形になると信じて動けるのは、素敵なことだなと思っています。
広瀬:そうですね。さらに個人のつながりがまた共有されていくと、100倍になって自分に返ってくると思います。我々としては、そういうつながりを見える化して、シェアして、さらに広げていく場になっていくことを目指したいですね。

「今日、この場で、 新たな化学反応が起き、そのエネルギーがまたそれぞれの地域にへと、めぐるめく。」
最後に、この日、広瀬が参加者から受け取った言葉を会場に共有してのクロージングとなりました。ご参加・ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!「日本の食卓会議2023」をきっかけに、新たなつながりが生まれたのであれば嬉しく思います。
ここからまた、「めぐるめくプロジェクト」は活動を続けていきます。今後も「食卓会議」を始めとした、全国各地での活動が予定されています。プロジェクトに関わってみたい、コミュニティに参加したいという方はぜひご連絡いただければ嬉しいです。
日本の農と食の未来を、明るく語り合っていきましょう!
Special Thanks
兵藤さん・神野さん・久曽神さんをはじめとする中部ガス不動産の皆さま、“ホテルアークリッシュ豊橋”と“emCAMPUS FOOD”のスタッフの皆さま、ご協力ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
