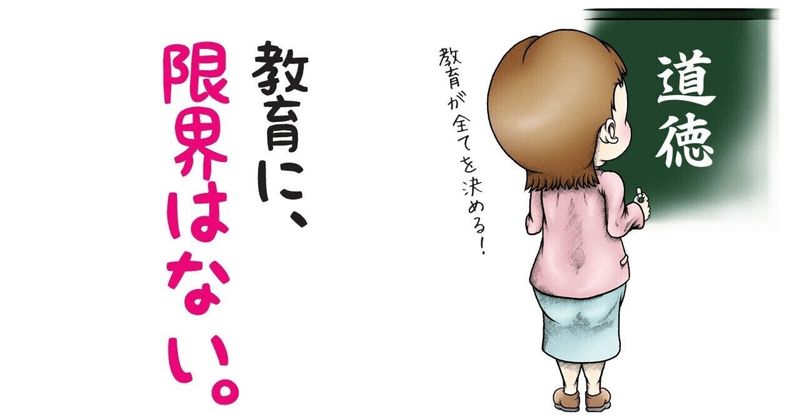
Photo by
featurecompass
教学聖旨(1879)
1870年代末期になると、教育をめぐるイデオロギー(理念や思想)にも変化が現れ始めます。明治維新以来の西欧化路線に対する反動として、保守的な宮廷官僚を中心として、教育政策の転換を図ろうという動きが起こります。
その中心人物が天皇側近の儒学者である「元田永孚(もとだ ながざね)」です。この辺りの「修身」をめぐる話は、以前にも道徳教育の話でしていたので、まだ読まれていない方は以下をどうぞ。
1879年(明治12年)、元田永孚を中心にして、伊藤博文などの反対を押し切り、明治天皇から文部卿に対して下されたのが「教学聖旨」です。これは、天皇が公教育に介入した最初の出来事であり、学制の序文であった「被仰出書(おおせいだされしょ)」の方針ともまったく異なるものでした。
教学聖旨の特徴は次の2点です。
①道徳は孔子の学(儒教)を主とする。
②徳育重視から、修身を筆頭教科にする。
1870年代後半は、藩閥政府の強権的な政権運営に反発する者や、政府内部での権力闘争に敗れて下野した政治家たちによる「自由民権運動」も展開していきます。当時の学校教員の中には、その運動に積極的に関わる者も多く、学校はしばしばその集会のための場所としても利用されていました。政府の中の保守的な官僚の中には、こうした動きを牽制しておきたいという思惑もあったのでしょう。
「教学聖旨」の翌年に改正された「改正教育令」では、教学聖旨の方針を踏襲し、「修身」が筆頭教科に位置付けられました。こうして、日本の教育は国家主義的なものへと傾倒していくことになるのです。
参考文献
『日本の教育経験』 JICA 2003
『教育の理念・歴史』 田中智志・橋本美保監修編著 一藝社 2013
『教育学の基礎と展開』 相澤伸幸著 ナカニシヤ出版 2007
