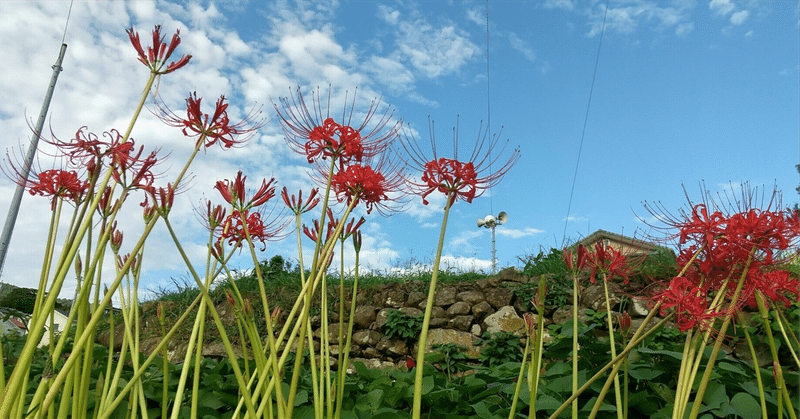
道徳教育の概観(修身〜教科化前まで)
(『道徳教育の可能性』 中戸義雄・岡部美香編著 ナカニシヤ出版 2005)より
岡部美香によれば、学校教育における道徳教育の始まりは「学制(1872年 明治5年)」における教科「修身」である。当時の「修身」は「修身口授ギョウギノサトシ」と呼ばれ、文字通り教師による一方的な口授を行う授業であったが、必ずしも熱心に実施されたわけではないという。さらにその後、福沢諭吉をはじめ日本の近代化へ向けて、実学を重んじる風潮が強まることになる。
しかし、明治12年に儒教学者であり「教育勅語」の起草にも参加した元田永孚もとだながざねの「教学聖旨」という文章が伝達される。これは、自由民権運動の高まりへの儒教勢力の対抗という背景もあった。明治政府は儒教道徳の徳目である「忠孝」を強調する。「忠」は「主君への服従」で、「孝」は「親への服従」ではあるが、明治政府は天皇を家長とする一大家族として国家を捉える家族国家観を浸透定着させ、明治13年には、修身を小学校諸教科の筆頭たる首位教科に位置付けた。それは、WWⅡに修身が廃止されるまでは基本的に変わることはなかった。
明治23年には、「教育勅語」が発出された。これは日本の教育の基本理念を天皇制と結びつけ、天皇制の永続的発展に奉仕することを国民(臣民)の徳性と見なし、そうした徳性を涵養するように教育を全面的に方向づけるものであった。この文書は、天皇制教育の確立を決定づける一つの重大な契機であった。それはまた同時に、自由民権運動に垣間見られた教育観、すなわち教育を人間に固有の権利ととらえ、主体的で自由な近代的人間の形成を図ろうという教育観が失われていくことを意味していた。
その後、大正自由教育期には生活綴方教育などの修身教育への批判もなされたが、1925年(大正14年)の治安維持法が成立すると、そうした立場を支持した教師の多くは治安維持法違反で処分されていった。1935年(昭和10年)には衆議院で「国体明徴」が決議される。「国体」とは、大日本帝国が「万世一系の天皇天祖の神勅」を永遠に奉じる神の国であることを意味しており、「国体明徴」とは「国体」を「事実」として明確に認めることをさしている。これは、天皇に奉仕し忠孝の美徳を発揮するよう全国民に要請するものであった。1937年(昭和12年)には盧溝橋事件が勃発し、日本は中国との全面戦争へと突入する。これを境に、日本では急速に軍国主義化が強化され、小学校は「国民学校」に名称を変更し、修身は「国民科」の一科目になった。国民学校では、国家への奉仕を第一義とする皇国主義教育の実践場とする構想が打ち出された。1943年(昭和18年)ごろからは日本への空襲も激化し学校教育は事実上停止し、日本は終戦を迎える。
戦後はGHQの指令によって、国民化の科目とともに修身も廃止された。その後、道徳教育を担うようになったのは社会化であった。しかしながら、他方で1950年(昭和25年)の天野文省による修身科復活問題をはじめとした動きもあった。これは、「子どもによる非行件数が戦後ピーク(1951年)を記録」するなどの「社会不安」、戦後復興を促進するための「日本の民主化・非軍事化」からの逆行を示す「教育の逆コース」などの動きと呼応するものであった。その後、日本は1960年代から一気に高度経済成長期へと突入していくのである。
こうした状況の中、1958年(昭和33年)の第三次学習指導要領において、「道徳の時間」が特設されることになった。戦後の「道徳の時間」は「各教科、特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら、これを補充し、深化し、統合し」、道徳的実践力の向上を図ることを目的とするものであった。これは、民主的な精神に基づいて目標を定めるという点において、戦前の修身の授業とは明確に区別されるものであった。
