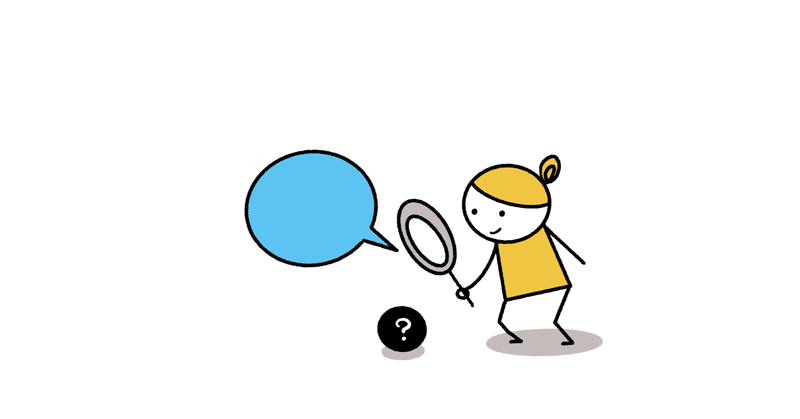
フリースクールを立ち上げてわかったこと
3月にフリースクール事業を立ち上げたわけですが、現段階で感じていること、わかったことについて書いてみます。進んでいくと今のことを忘れてしまいそうなので、自身の記録として。
◯手続き関係の手応えのなさ
フリースクールはその名の通り『フリー』なスクール、つまり何をやってもどんな形でもOKな学校です。私の理解が十分でないかもしれませんが、こうでなければいけないというルールはなく、多分何をやってもいいはずです。そんなフリースクールなので、クリアしなければいけない手続きがありません。やりたい人が「やります!」と言ってしまえばスタートできます。
いろんな福祉事業をやっているので、こんなに簡単に始められてしまうことに「えっ、これでいいの?」と思ってしまいますが、ほんとにそんな感じです。どこからもお金をもらっていないので縛られるものは何もありません。それもフリーならではのこと。でも手続き等が何もないので手応えはありません。それもフリーならではのこと?、なんでしょうね。
◯でも動き出すと確実に手応えがある
スタート前までは、2名の子どもをボランティアとして受け入れていました。それが「フリースクールを始めます」と宣言した途端に問い合わせが届き始めました。新たに3名の利用が始まっています。それとは別で2名から利用を検討していると言われています。手続きの手応えのなさとは違い、このような場が求められていることはすごく伝わってきます。手応えはありまくりです。
◯勢いでスタートしたから当然問題は出てくる
十分に検討を重ねた後にスタートしたのではなく、とにかくスタートさせることを優先したため、今様々な課題に直面しています。9時〜17時を基本としているが、それを超えた利用はできないのかという問い合わせ。活動中に事故が起きた際にはどのように対応するのか(保険の問題)。問い合わせや調整などに職員が対応する時間が増えすぎないようにしなければいけない。地域の受け入れ先を増やしていく担当者がいない。保護者の悩みをしっかりと聞く体制が不足している。保護者同士がつながる場所を作ることができていない。
考えないといけないこと、整備しないといけないことがいろいろと出てきているんですが、動き出したからこそ見えてきたことだと考えると、まず動く、その後考えるという順番でよかったと思っています。
◯やってもいいし、やらなくてもいい、だからこその難しさ
最初に書いたように、特にルールがないのがフリースクールです。この設備がないといけない、人員体制や資格はこうでないといけない、これを行わないといけないといったことがありません。すごく動いてもいいし、あまり動かなくてもいい。そんな状態なので、よりよいものにしていこうと思い続けるモチベーションを保つためには工夫が必要だということです。利用があったり問い合わせがあったりするだけでモチベーションは勝手に上がるのですが、よりよい環境づくり、利用しやすいように改善すること、協力者を増やすための取り組みなどを続けるためには、何か工夫は必要だと思っています。
◯公的な支援を受けるのはなかなかハードルが高い
最後にひとつ。これは動いてみてよーくわかったことですが、公的な支援を受けるのはなかなかハードルが高いということ。支援というのは金銭的なものではなく、教育委員会に活動を支援してもらうことです。具体的にいうと、フリースクールの活動を学校の出席に認めてもらうことです。出席日数が多い少ないが何かに大きく影響するわけではないそうなので、だとすれば出席にすること自体は特に問題はないように思うのですが、まあそんな簡単な話ではないんでしょうね。
もしも学校への復帰を目的としたフリースクールでなければいけないとかが条件だったらさすがにびっくりしますが、決してそんなことではありません。学習活動が行われることとかの条件のようなので、体制を整えて教材も用意しプログラムも作るといった簡単な…うーん、簡単ではないですね。でもここはじっくり考え、教育委員会ともたくさん話をしていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
