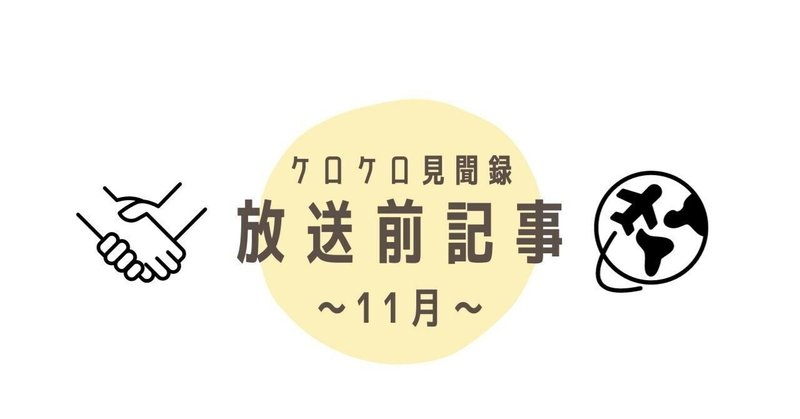
ポーロと予習~私のグローバル化~
みなさん、こんにちは。medien-lienライターのこーすけです。最近は寒暖差が激しく、山がちな九大キャンパスで暮らしていると体調がおかしくなっています。本当になんでこんなとこr…いえ、季節の移り変わりを感じられる大変素晴らしいキャンパスです。
さて、2023年のケロケロ見聞録も残すところあと2回。今回のテーマは「目指せ、地球規模の『私』~パラグアイから考えるグローバル化~」。今年ももうすぐ終わる中、世界では様々な動揺が生じています。グローバル化って、何だろう?と改めて問い直すには、十分なタイミングではないでしょうか。ぜひ、パラグアイの空気を感じながら、記事をお楽しみください!
この記事は、九州大学の現役学生が制作するラジオ番組「ケロケロ見聞録」(ラブエフエム国際放送、毎月第一日曜22:00~)がもっとおもしろくなる情報を提供するものです。この記事に興味をもった皆さん、ぜひ各種サービスでケロケロ見聞録をお楽しみください!
1. 明治維新から考える「グローバル」
「グローバルな人材を目指して~」
高校時代、生徒指導の先生の口癖はこんな具合でした。しかし、聞いている側のうち、その意味をちゃんと理解している人はどれくらいいたのでしょうか?
グローバルという言葉は、「地球規模」という意味を表します。語源はラテン語の「globe」、球体を意味する言葉でした。語源から考えれば、天動説が否定されたことによって、日の目を見たともいえる言葉かもしれません。
第二次世界大戦以後、極端な地域主義が多くの犠牲者を生んだ反省から、この言葉は平和を目指すための合言葉のように使われてきました。どちらかといえば、批判的な場面でより多く、です。「グローバル化が遅れている」「グローバル人材育成が急務」・・・生徒指導の先生がなぜああなってしまったかがよくわかります。
では日本が「グローバル化」を推し進めようとし始めたのはいつ頃なのでしょうか。歴史の教科書をよく読んでいた方ならお分かりになるでしょうか。そう、明治維新です。それまで外界との人流・物流を遮断していた日本は、「風説書」と呼ばれる報告書を一部の国から受け取ることでのみ、国際情勢を把握していました。もちろんこの報告書は幕府が持っていたので、民衆の「グローバル」知識は0に等しいものだったでしょう。
幕府が倒れ、新たな政府は欧米に追い付くことを目指しました。まさしく、グローバル化といえるでしょう。そんな時代を象徴するような資料があります。

出典:https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/bon-ukiyoe/008/677
これは浮世絵の名画家、歌川広重の『流行英語尽し』という作品。注目すべきは、当時の「カタカナ読み」です。例えば、Lumpは「ランムプ」、painterは「ペフンナー」、travellerは「トラベレル」。今のイメージとはどこか異なります。実は当初、こうした読み仮名は聞こえた発音を元に作成したというんです。こちらの方が英語話者に理解された、という噂もあるそうで、個人的にはこれでいいのでは?とも思います。
グローバル化は私たちそれぞれが地球規模の視点を持つ、という解釈が一般的です。だからと言って、『もっと早く開国していたら』などと過去を過剰に批判することには意味がないのではないでしょうか。日本は遅れているのではなく、確かに独自の進化を遂げています。あなたももし、自分がグローバル化できていない!と焦っているのだとしたら大丈夫です。是非、ケロケロ見聞録・11月放送をお聴きください。ちょっとだけ心が軽くなる、明るい「グローバル化」のお話をお届けします!
2. Youは何しにパラグアイへ?
11月放送、実は予習なしでも結構楽しめるのですが、予習事項を書かないとタイトル詐欺になってしまいます。ということで、今回のゲスト、つぐみが大きく関わった国、パラグアイをご紹介します。
パラグアイは先住民族の言葉で、「豊かな水量」という意味の川、パラグアイ川に由来します。ということで、豊かなパラグアイ情報をいくつかご紹介。きっとパラグアイが近く感じるはずです。
ワイワイがお好き
パラグアイに根付く文化、アサード。日本で言うバーベキューのようなものだそうです。家族によっては毎週末アサードを楽しむことから、一家に一台お肉を焼く窯があるのだとか。素晴らしい文化ですね…(肉好き)

日本の血が流れる国
パラグアイには、南米の中でも大きな日系社会があります。戦前、ブラジルへの移民が反日運動により滞ってしまったことから、パラグアイに目的地が移ったことがきっかけでした。
現在、パラグアイには7000人の日系人が暮らしています。数としてはそこまで多くありませんが、彼らが作る農作物、特に大豆はパラグアイの輸出総額のうち、4割を占めるほどの「稼ぎ頭」なのです。
ちょっとだけ、パラグアイが気になってきませんか?え、どこにあるのかって?つぐみさんは結局何が関係しているんだって?
それはまあ、ぜひ本編をお聴きください…!
https://open.spotify.com/episode/5lxR4JJJDiFpvqMEQYv92e?si=f2bc3092e2244125
参考および出典:横浜国立大学 パラグアイの文化
3. 11月放送の聴きドコロ!
改めて、11月5日放送のケロケロ見聞録の注目ポイント、聴きドコロをご紹介!
1. つぐみのパラグアイ紀行
今回の出演者はつぐみ、めい、初登場のりさこ。つぐみとパラグアイの関係、そしてパラグアイはつぐみに何をもたらしたのか…!なかなか聞けない、異国体験譚がそこにある!
2. 「私をグローバル化」ってなに?
コロナ禍が収束に向かい、増える訪日外国人の数。天神が異言語にあふれる中、私も何かしなくてはいけないの!?
グローバル化という言葉を、大学生3人があらためて、ゆるく考えてみます。
放送は、11月5日、22:00から!お楽しみに!
radikoなら、放送から一週間はお聴きいただけます。
▼こちらからどうぞ!▼
https://radiko.jp/share/?sid=LOVEFM&t=20231105220000
4. SNS展開
4、SNS展開
私たち、medien-lienもSNSを使ってラジオの情報を配信中! Twitter、Facebook、Instagramから、ぜひご覧ください🐸 ラジオを聴き逃してしまった! という方は、radikoやこちらのポッドキャストから番組をお楽しみ頂けます✨

番組内容や番組の後日談を、西日本新聞のニュースアプリ「me」でも紹介しております。ぜひ西日本新聞のニュースアプリ「me」をダウンロードしてこちらの記事もご覧ください。
アプリのダウンロードはコチラから!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
