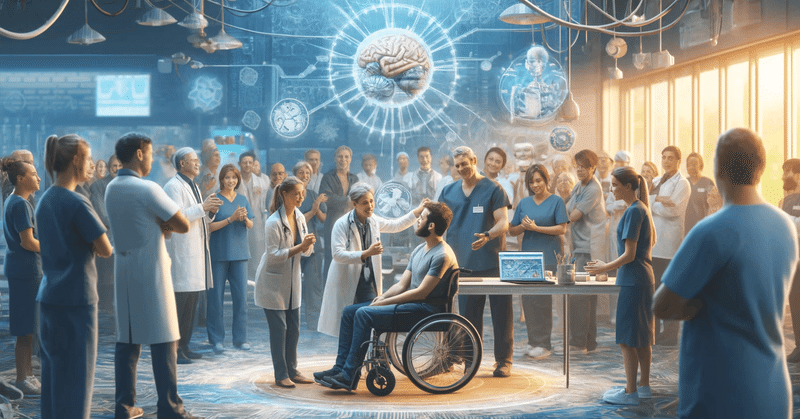
医工産学連携の基礎:(7) 共感② ユーザからの共感とプロセスエコノミー的アプローチ
前記事ではデザイン思考等でも取り上げられている、製品・事業開発におけるユーザへの共感の重要性について解説しました。
この記事では事業開発におけるもう一つの重要な共感、ユーザからの共感について解説します。
ユーザからの共感がなければ買ってもらえない
ユーザへの共感に基づき、アンメット・メディカル・ニーズを掴み的確なインサイトを獲得し、それに対する適切な解決策となる技術を持つ製品を開発できたとして、もちろんそれだけで製品が売れるわけではありません。営業や広報や規制対応など、マーケティングにかかわる数多くの課題に対して適切に対応せねば、事業上の成功を収めることは困難です。
そもそも、技術的な成熟度が上がっている現代では、アウトプットとしての製品能力は、極めて革新的かつ模倣が困難な特殊な事例以外においては、競合との差別化が難しい時代になっています。どの会社の製品を買っても特に基本性能・品質に大差は無い。ある会社が新製品を出しても似たような製品が特許に抵触すること無くすぐに競合として誕生する。しかもどれも同じ様に安い。そんな時代になってきました。
アウトプットエコノミーとプロセスエコノミー
そこで他社との差別化を図りユーザを獲得するために必要となってくるのが「共感」です。特にアウトプット、性能そのものでなく、そこに至るまでのプロセス・ストーリーによってサービスの魅力を向上し、ユーザの共感を獲得し、購買行動に結びつける。この考え方をけんすうさん・尾原和啓さんは「プロセスエコノミー」と表現しています。従来型の製品サービス能力重視の「アウトプットエコノミー」では戦えない時代に必要な考え方と思います。
医工産学連携におけるプロセスエコノミーの重要性
医工産学連携による医療製品・サービスの事業開発においても、このプロセスエコノミーの考え方が重要になってきます。
メドテック・ヘルステックの分野においても、分子構造が性能を決定し別構造での模倣を実現することが困難な材料・製薬の分野と異なり、医療機器や医療サービスにおいて唯一無二の製品技術で市場を長期間独占することは非常に難しいです。
「いいものをつくれば売れる」「お武家の商法」では通用しないのは古くから理解されている事項ですが、アウトプットの魅力を最大限に引き出す「アウトプットエコノミー」としての事業戦略だけでなく、そこにいたるまでのストーリー、製品のWhatではなくWhyやHowを元にし「ユーザからの共感」を中心としたサービスの魅力向上を図る戦略である「プロセスエコノミー」の考え方を導入することが、特に新規の事業開発では重要と考えます。
事業開発の根本にある開発者のビジョンや社会的使命感、最終的な製品に至るまでの開発者の葛藤や努力、研究上の困難や達成、さらには製品・技術開発とは直接関係のないところでの開発者の体験・達成など、そういったストーリーがユーザの共感を呼び、製品の求心力を向上させます。ブランディングもその一つと思います。
また一方で注意すべき点として、プロセスエコノミーの特徴は、プロセスによるマーケティングのため最終製品・サービスが完成する前から戦いを始められるor始めなければならないという点があります。
ユーザからの共感がなければ最後まで走りきれない
魔の川・死の谷・ダーウィンの海
研究・開発から事業成功までの苦難の道程を表しているとしてよく知られる表現として、死の谷(デスバレー、Valley of Death)を中心とした「魔の川・死の谷・ダーウィンの海」という表現があります。
基礎研究から応用研究へ発展できずに死ぬ技術。応用研究から製品化に至らず死ぬ技術。製品化から事業化に進まず死ぬ製品。事業化しても市場で淘汰されるサービス。文献によってどれが魔の川・死の谷・ダーウィンの海に対応するか多少異なりますが、技術を事業成功にまで到達させるまでの道程で大きな困難となる壁が
基礎研究→応用研究
応用研究→製品化
製品化→事業化
事業化→市場獲得
に存在するとされます。
これらの障壁を如何に乗り越え事業を成功に導くかという経営戦略が技術経営(MOT)等において重要な課題となります。
臨床研究・治験/薬事承認・保険収載
さらに医工産学連携による医療製品・サービスにおいては、一般的な工業製品とは異なる規制上の大きな壁があります。それが
応用研究→臨床研究
製品化→治験/薬事承認
事業化→保険収載
のプロセスです。
薬機法、臨床研究法、次世代医療基盤法などを中心とした様々な法規制に対応して製品を完成・生産し、さらにマーケットにおいて対価を得る・競争力を持つためには薬事戦略と保険収載戦略※が必要となりますが、これがかなり大変なプロセスとなります。
すなわち魔の川・死の谷・ダーウィンの海がそれぞれ2倍なのが医療機器開発です。
※医療機器の場合、薬事品のすべてが保険収載されて点数が付くことを必要とはしてません。包括の中で償還する戦略も保険収載戦略です。
走り切るにはステークホルダーからの共感が必須
このように大きな壁が多く立ちはだかるテック系の新規事業開発を完遂し成功することは長く困難な道程です。特に医療製品開発は壁の数も多く乗り越えるのに要する時間も長く、事業開発が長丁場になりがちです。
この困難な道程を乗り越えるために、開発メンバーのやり切る強い気持ち・マインドセットはまず第一に必要です。しかしそのマインドセットを維持するうえで、周囲からの応援は非常に重要になってきます。すなわち、周辺の仲間、支援者、ステークホルダーからの「共感」が必須です。
応援がなければ気持ちが続きません。また実体としての応援、資本・資金や設備環境などの支援も非常に重要です。またこれは事業開発の途上で必要となる応援ですので、最終製品への共感でなく、そこへ至るまでのプロセス、ビジョン、ストーリーなどへの共感が必要となります。
ユーザへの共感は製品開発に必須、ユーザからの共感は事業開発に必須
以上を踏まえると
ユーザへの共感は、アンメット・メディカル・ニーズを正しく掴み、的確なインサイトを獲得し、それを満たす技術・製品を開発するために必須(デザイン思考的アプローチ)
ユーザからの共感は、医療製品開発における魔の川・死の谷・ダーウィンの海を乗り越えて事業を成功に導くために必須(プロセスエコノミー的アプローチ)
ということになります。
では、このデザイン思考・プロセスエコノミーの考え方を踏まえた医療製品開発はどの様に進めるか。
医工産学連携体制で、医・工、産・学それぞれがそれぞれの役割を果たし、技術開発から製品上市に至るためにはどの様な戦略があるか、次の記事からはこの点について私の経験を踏まえて解説したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
