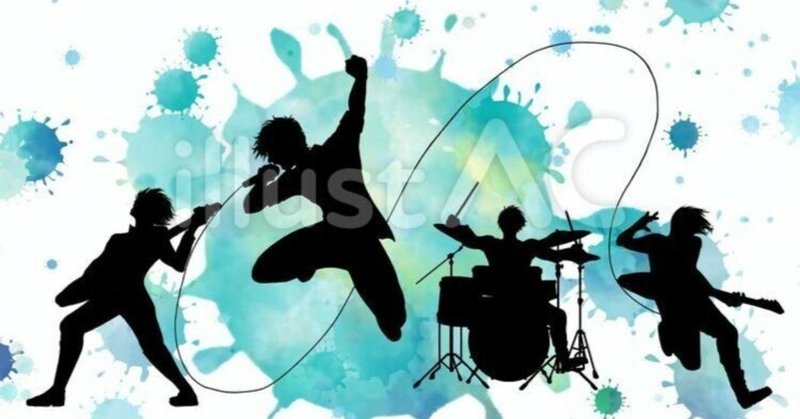
体験小説「チロル会音楽部 ~ ロック青春記」第2話*チロル会音楽部、活動開始!
チロル会の活動も順調に続けられ、日増しに会員間の結束も強くなっていった。
それと反比例するように、来る日も来る日も、ハーモニカを吹く器楽部での単調な時間に、不満は募る一方。
― それじゃあ、自分達で好きなようにやってみようではないか! ―
というわけで、
ある日ある時、ギター、ウクレレ、大正琴、オルガン、ハーモニカ、リコーダーなどの楽器を持って末原君の家に集まり、独奏やアンサンブルなどを楽しんだ。
いよいよ《チロル会音楽部》の活動開始である。
実は、その誕生の瞬間を僕は知らない。
話が出たとき、チロル会に参加せず、直行で帰宅してしまっていたのだ。
その演奏に最初に接したのは、後日、録音テープを聴いたときだった。
録音された曲が何だったか、おぼろにしか覚えていないが、映画音楽「駅馬車」、そして、器楽部では打楽器を担当していた小牧君のボーカルで、ザ・タイガースの「花の首飾り」を演奏していたことだけは覚えている。
末原君が、オープンリール・テープを音楽準備室に持ってきて、部活が始まる前、先生に内緒で、備品のテープレコーダーで聴いて、楽しんでいた。
ところが、その日に限って、いつもはそんな時間には姿を見せない指導の先生が入ってきた。
― ヤバい! ―
勝手に備品を使っているのを目撃された。しかも、録音されているのは、器楽部に内緒で演奏している自分たちの演奏。曲にしても学校教育の場に相応しいとは言えない。
相手は、決して穏やかな性格の持ち主ではない。いわゆる熱血教師タイプ。常日頃、特に男子生徒に対する指導には容赦がなく、言葉も辛辣極まりない。
ところが、予想に反して、彼の反応は悪いものではなかった。
その様子から判断すると、たぶん彼は胸の内で、こう呟いていたに違いない。
― 熱意あるオレの指導が、こんなに音楽好きな子供を育てたのか・・・ ―
彼は、教え子の演奏に聴き入った。そして、器楽部の練習を開始する前に、好意的なコメントを添えて、それを部員たちに聴かせた。
ウクレレや、大正琴など、当時、中学生が演奏するのは珍しく、部員の一人、徳森君が弾いた電動オルガンも、バッハのコラールみたいな格調高いもので、皆がその楽器に対して描いていたチープなイメージを覆すものだった。
「へえ、これオルガンなの?」
聴いていた器楽部員から、そんなささやきが聞かれた。
1曲ごとに、「会長」山下君のナレーションが入っているのも面白かった。声に張りがあり、抑揚も豊かで茶目っ気があった。
中でも、徳森君の演奏を、
「普通のオルガンですよ。カッコいい!」
と紹介していたのが、印象的だった。
僕はそれを聴きながら、自分がそこに加わっていないことにジェラシーを感じていた。
チロル会の活動に、もっと積極的に参加していれば良かったと悔やみ、2回目の練習からは、当然、僕もそこに参加するようになった。
その後、次第にメンバーも入れ替わり、3年になるころには、急速にロック・バンドとしての方向性が固まるが、このころは、まだそんな気配は微塵もなく、そのまんま老人ホームの慰問に使えるような、素朴でのどかな音を出していた。
僕らが駅馬車などを演奏し始めた1968年という年、イギリスのロック・シーンに目を移すと、大きな変革の波が押し寄せていた。ボーカルのみがヒーローだった時代は去り、才能溢れるギタリストたちが、高度な演奏技術と革新的な表現力を前面に押し、新たな時代のヒーローとして台頭してきていた。
主な記録を拾い出してみよう。
* ジミ・ヘンドリックス&ジ・エクスペリエンス、アルバム『アー・ユー・エクスペリエンス』で初のゴールド・ディスクを獲得。
* ジェフ・ベック・グループ、ニューヨーク、フィルモア・イーストでアメリカ・デビュー。
* クリーム、『クリームの素晴らしき世界』をリリース。
* レッド・ツェッペリン、アトランティック・レコードと契約。
一方、日本では、タイガース、テンプターズらのグループサウンズが全盛。ある意味魅力ある若者たちで、その個性的な歌声も懐かしくはあるが、この年のナンバー1ヒット曲は、千昌夫の『星影のワルツ』。一般的な日本国民にとって、ロックはまだまだ日陰の存在だった。
68年の来日アーティスト。
ウォーカー・ブラザーズ、モンキーズ、ベンチャーズ、スプートニクス、エリック・バートン&ジ・アニマルズ等々。
英米でジミ・ヘンドリックスや、クリーム、ジェフ・ベックらが活躍していた、まさに同じ頃のことなのだが・・・。
インターネットの発達で、世界中の情報がリアルタイムで伝わってくる現在と違って、当時は、国内と国外の音楽シーンの隔たりが大きかった。
チロル会音楽部に参加したころの僕は、まだ海外のポップス事情には疎く、その点に於いては、一般的な日本国民と何等変わりはなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
