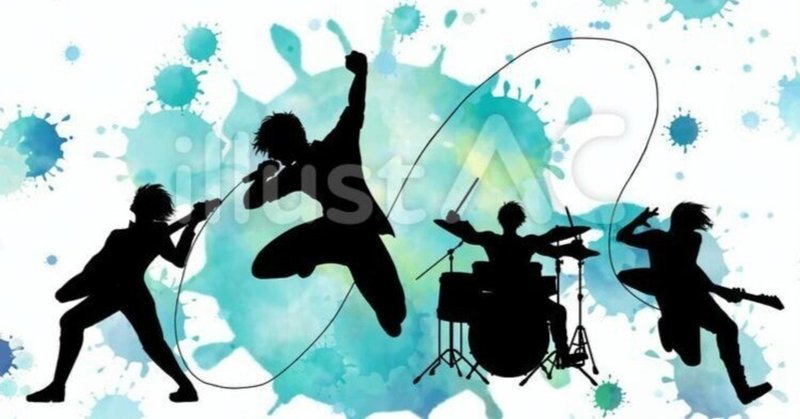
体験小説「チロル会音楽部 ~ ロック青春記」第10話*3年生になった
1970年春。
僕らは3年生になった。末原君と鮫島君が同じクラス。何組だったかはっきり覚えていないが、3階建て校舎の最上階の最も東側に近い位置に教室があった。
一方の僕は、2階の最西端に近い10組。1学年あたりの生徒数が1000人近かった城西中。ワンフロアにおよそ10クラスがずらりと並び、端から端までがえらく遠く感じられた。
3年生ともなると、全体に俄然受験色が強くなる。
僕が所属していた10組の担任は、社会科担当の、骨太でやや肉付きの良い男の先生だった。40代前半。良く通る太い声の持ち主で、性格もその声のイメージ通り、腹の据わった安心感のある先生だった。
毎朝、乾布摩擦をし、真剣より重い木刀を振っているという絵に描いたような薩摩隼人で、高校受験に向けて空気を引き締めるために、
「一の太刀を信じて二の太刀は無し。肉を切らせて骨を断つ」
という薩摩示現流の極意を繰り返し口にしていたのが強く印象に残っている。
難関ラ・サールを受験する者から就職志望まで、様々な生徒がいたが、中には休み時間もずっと本を開いている生徒もいた。
そういった受験体制の1年間は、僕のような受験一筋ではない生徒にとって、かなり息苦しく感じられていた。
10組では、好きな音楽の話も存分にはできなかった。当時心酔していたレッド・ツェッペリンのファンがいなかったし、クラプトンやジェフ・ベックの話も通じなかった。
5月にビートルズのラスト・アルバム『レット・イット・ビー』が発表され、クラスの話題もそちらに集中。ピアノによるイントロを練習する生徒がいたほどの人気ぶりで、弾き方を請われるままに、備品のオルガンで教えたこともあったが、内心ではそんな状況をイマイチつまらなく感じていた。その頃は、エッジの効いたスーパーヘビーな音楽こそが先鋭的で魅力的だと思い込んでいて、その後、1人でツェッペリン啓蒙活動を行なうも、状況にほぼ変化は見られず、クラスから一人浮きがちになっていた。
末原君と鮫島君がいたクラスには、他にも音楽の趣味が合う子が何人かいて、昼休みや放課後など、よくそこまで遠征して雑談に興じたものだ。
修学旅行から帰って来た翌日、担任の先生から全日程を総括した感想が伝えられたが、その中で、
「他のクラスの生徒とばかり交流していた者もあったが、もう少し自分のクラスメイトとも打ち解けるようにしてもらいたいものだがねぇ」
と、いかにも残念そうに語る姿が、今でも忘れられない。
その言葉に該当する生徒など、どう考えても1名しかいなかった。担任の先生の目からも、その1名の行動は、よほどズレて見えたようだ。
末原くん等とよく話題にしたテレビ番組があった。若者向けの情報番組『ヤング720』(TBS系1966年~1971年)。
テレビでロック映像が流れるなんて極端に少なかった時代、番組のワンコーナーでたまに紹介される海外のミュージシャンの姿や、国内のバンドのスタジオ・ライヴなどを楽しみにしていた。
前年の69年、アメリカで開催された『ウッドストック音楽祭』の映像も、この番組でその一部が紹介され、想像を掻き立てられた。
鹿児島でこの伝説の音楽祭の記録映画が公開されたのは、中央より少し遅れてのことだったが、ビートルズの『レット・イット・ビー』と同時上映だったのがありがたかった。学校の許可映画になっていなかったので、坊主頭も恥ずかしげに、こそこそと入館し、そして、ジミ・ヘンドリックスや、テン・イヤーズ・アフターのアルヴィン・リーの演奏を、それこそご神託のように受け止めたものだ。
国内のバンドでは、フラワー・トラベリン・バンドに憧れた。ボーカリストのジョーは、当時の日本では、ブリティッシュ・ハード系のハイ・トーン・ボイスを披露出来る唯一の存在だった。彼らのナンバーで、特にカッコいいと話題にしたのが『21世紀の狂った男』。不規則で、複雑なリズムによる決めフレーズが特に良かった。
この曲、てっきりオリジナルだと思っていたのだが、その後、キング・クリムゾンのデビュー・アルバムの国内盤が、本国イギリスに遅れて発売され、初めて耳にしたときに、その曲が冒頭でいきなり聴こえてきたときには驚いた。
70年と言えば、まだ海外のロック・バンドが来日することもほとんどなく、国内のロック・バンドは、まだ海外のバンドをお手本にしている感覚があり、カバーというより、そのまんまフル・コピーして演奏することも普通に行なわれていた。日本のロックが、まだまだ黎明期にあり、シーン全体が、良くも悪くもアマチュアイズムの延長線上にあった。
ロックの情報源として楽しみにしていた『ヤング720』は、朝7時20分からの放送だったため、登校前に、遅刻ぎりぎりの時間まで見てから玄関を飛び出すという毎日だった。
話題にしたのは、もちろんロックだけではなかったわけで、校内でのいろんな噂話にもあれこれと花が咲いた。
そんな中で、鮫島君に関する、ちょっと面白い話を耳にしたことがあった。
「サメがラジオ番組にリクエストすると、必ず採用されるぞ」
「それって偶然じゃないの?」
「俺だって最初はそう思ったんだよ。だけど、他の誰もハガキを出しても曲が掛からないのに、サメのリクエストだけが何度も採用されて、景品のシングル盤が送られてくるんだぞ」
「へえぇ!」
「だから試しにサメにたのんでオレの名前で出してもらったんだよ。そしたら、ラジオでちゃんと俺の名前が読まれたんだよ」
「へえぇぇ、驚きだね」
「びっくりしたよ」
「放送局にサメの親戚でもいるの?」
「九州ネットだから、福岡でやってるんだぞ。そんな訳ないだろう。それに、
俺の名前で出したハガキだって選ばれてるんだぞ」
「あ、そうか・・・。じゃ、何でサメのハガキだけ何度も選ばれるんだろう?」
「分からないけど、俺だけじゃなくて〇〇もサメに書いてもらったらレコードが送って来たからな。君も書いてもらってごらん。たぶん、レコードがもらえるよ」
その当時は、なぜ彼の書いたリクエスト葉書が採用されるのかということまでは考えなかったが、今思えば、鮫島君の書いた葉書が、選者の目に止まり易かったのではないかと思う。目立つ葉書は採用されやすいと聞いたことがある。
彼は1年のときから美術部に席を置いていて、美術の先生にも目をかけられていた。イラストを描くのが好きで、音楽雑誌などから切り抜いたミュージシャンの写真と組み合わせたりして、遊びながらもわりとセンスの良い作品に仕上げていたのをよく見たし、3年になって初めてもらった年賀状にしても、何やら楽しげなイラストが、色彩も鮮やかに、サラサラと描きこまれていた。リクエストの葉書を見たことは当然ないが、たぶんそれらと同じように、魅力的なイラストが書き込まれ、面白い一言が添えられていたのだろ。
というのが僕の推測だが、もしそれがハズレだとすれば、鮫島君が念力でも込めたに違いない。
いつも自分のクラスを抜け出し、末原君たちのクラスに居心地の良さを感じていたが、同級生との関係に特に問題があったわけではない。ただ、受験一色の空気が息苦しい上に、音楽のことを本気で語れない物足りなさを感じていたというだけのこと。
それに比べると、家庭の中では、はっきりと居心地の悪さを感じていた。高校教師だった父の目からは、気持ちが受験に向かわず不良が好むような音楽をピアノでガンガン弾きまくる長男が何を考えているのか解らず、いつも不機嫌そうだった。
僕の方でもそんな父を疎ましく感じ、親子関係はいつもギクシャクしていた。
末原君や鮫島君にしても、受験体制の中での強い葛藤を感じていた。
特に、自分の部屋を練習場にしていた末原君など、そのこと自体が目立ち、担任の先生にもその情報は入っていたようで、進路指導のための個別面談が、大きなストレスになっていた。
当時は、バンドなど不良がやるものだというレッテル貼りがなされていて、エレキギターを弾きバンド活動を続けることを、ほとんど愚弄に近い言葉で否定されていた。
人一倍のプライドを持って取り組んでいた彼にとって、それは到底耐え難いことだった。
ある日の放課後、いつものように、ふらりと彼らのいる教室に入って行くと、2、3のクラスメイト相手に、末原君が苛立った顔で何かを話している最中だった。途中で入って来た僕には、話の詳細までは解らなかったが、どうやらクラス担任から嫌なことを言われたようだった。周りにいた数名が、彼の話に耳を傾け、しきりに肯いている。
それでもどうにも気持ちが収まらない末原君。怒りに燃えた眼差しで宙を見据えたまま、突然立ち上がり、廊下に向かって歩き出した。
女性との一人が、尋常ならぬ気配を察知し、声をあげて止めにかかったが、阻止できなかった。
着ていた上着を脱ぎ、その端を両手でつかんで振り回し、窓ガラスに思い切りぶち当てた。
破壊音とともに、ガラスが砕け散った。
異変を察知した生活指導の先生の足音が、階下からバタバタと足早に近づいてきた。
** ** **
長じてからの彼からは、なかなか想像し難いエピソードであるが、そこに横たわっていた亀裂がいかに大きかったかを物語っている。
その頃の日本は、まだロックで稼げるような状況ではなかった。しかも、中央から遠く離れた鹿児島で、学校教育という場にどっぷりと浸かった大人たちにとっては、ロックで食べてゆくと言うこと自体、想像もつかない絵空事でしかなく、そんな彼らの目に、末原君の存在は、受験のことなどお構いなしでエレキバンドなどという戯けた遊びにうつつを抜かしている困った生徒ぐらいにしか映っていなかった。
そんな中でバンド活動を続けられたのは、まだ自立した人生を体験していない幼さゆえのこととも言えたが、何よりも純粋な情熱あってこそだった。
「貧乏しても、好きなことを続けていられればいいよね」
自分たちの意志を確かめ合うように、そんな言葉が誰からともなく、繰り返し発せられたものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
