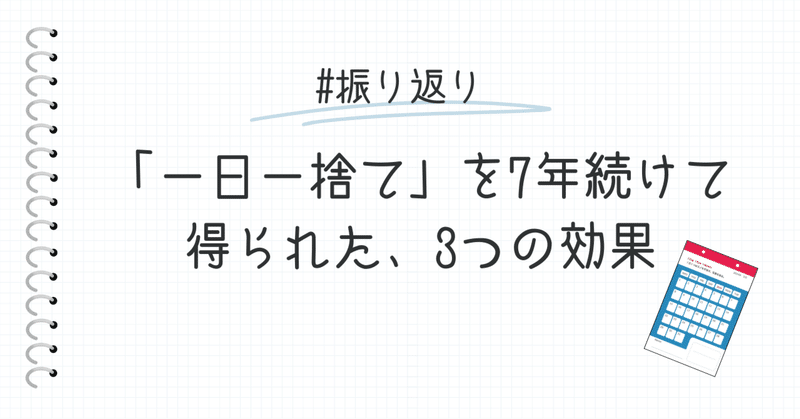
「一日一捨て」を7年続けて得られた、3つの効果
はじめに
2017年5月1日、私は「一日一捨て」という小さな挑戦を始めました。
きっかけは、忙しい日々の中で、どうすれば「ラクに、いつも片づいた状態をキープし続けられるのか?」という問いの答えを見つけるため。
そして、その答えこそ、「捨てる習慣」だ!と思い、その検証実験を始めたわけです。
このシンプルな習慣は、日常に静かな革命をもたらし、多くの方々と共に成長を続けています。
「一日一捨て」とは?
「一日一捨て」とは、毎日、不要になった物を一つは選んで手放すこと。
具体的には、捨てるものを決める→カードに記録する→カードと共に捨てる物の写真を撮る→コメントをつけて、LINE公式アカウント友だちに送る。
それだけのシンプルな行動です。

現在、139名の方がこの「一日一捨て」の旅を共にしてくれています。
友だち登録中の方にとっては、私との1:1のやり取りなので、自分の取り組みをこっそり送信することができます。
それに対して、私がスタンプ返信で応援、という流れです。
この仕組みと、皆さんからのフィードバックのおかげで、無事に7年間、皆勤で続けることができました!本当に感謝です。
「一日一捨て」を続けて得られた3つの効果
実際に7年間「一日一捨て」を続けてきたことで、得られたことはたくさんありますが、大きなものを3つ、ご紹介したいと思います。
1. スッキリとした生活空間をキープ
毎日少しずつ物を減らすことで、部屋はいつも、どこを開けてもスッキリ。
掃除がしやすくなり、探し物に費やす時間もほとんどありません。
子供の成長に伴って増えがちな衣類や学用品、思い出の品も、必要な分だけ、ほぼ一定量に保ち続けることができました。
2. 決断スピードがアップ
物を手放す習慣が、日々の決断を敏速にしてくれるようになりました。
不要なものはすぐに処理し、物を新しく購入する際も、衝動買いはほぼなくなり、必要性を素早く考えられるようになりました。
また、タスクや時間の使い方に対しても不要なものを減らす習慣が身につきました。
例えば、「子供の弁当作り」は、中1の頃から娘に任せています。子供の自立も促せるし、朝の自分時間をたっぷり取ることができています。
3. 思考が柔軟になり、自己理解が深まる
物を手放す時に躊躇するのは、物ではなく、「自分の考え」に執着があるから。
それに気づき、執着してきた「自分の考え」を手放したり、新しい捉え方を取り入れる練習をすることで、思考がかなり柔軟になりました。
さらに毎日のコメントを通した小さな内省が、自己理解を深め、感情のコントロールも自然と上手になっていきました。
まとめ
「一日一捨て」という習慣は、「ラクに、いつも片づいた状態をキープし続けられる」のはもちろんのこと、私たちの生活を豊かにし、心を軽くします。
5月は、7周年記念キャンペーンを実施中なので、この機会にぜひご参加ください。一緒に、毎日をもっと心地よく過ごしましょう!
登録はこちらから!
▼「一日一捨て」LINE公式アカウントをお友達追加
ご参加、お待ちしています!
いただいたサポートは、新たな気づきのヒントをお届けするための糧にさせていただきます。
