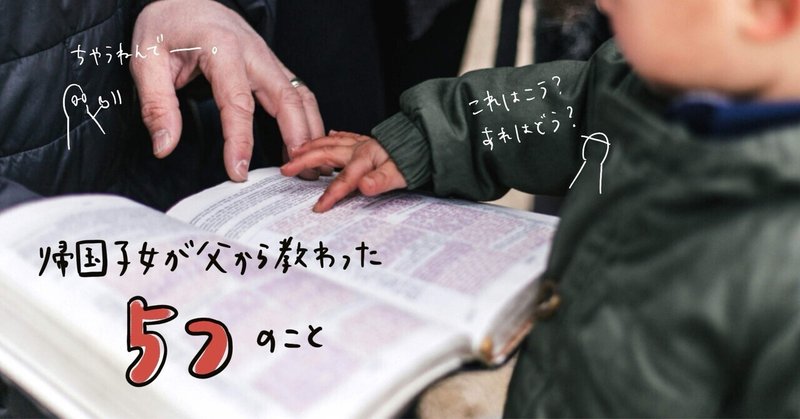
帰国子女が父から教わった5つのこと
はじめに
親は子どもの背中を見て育つとはよく言ったもので、うちの兄妹は仕事に対して真面目なところがある。悪く言うのであれば、いささかワーカーホリックなところがあり、ひとえに父の背中を見てきた影響だと言える。
正直なところ、私が父から教わったと自覚できることは、それほど多くはない。というのも父と私が一緒に過ごした時間はかなり少ないからだ。
万年海外出張だった父。日本に戻れば戻ったで、会議だの接待だので家をほぼ空けている生活であったし、土日が休みとなれば死んだように寝ているので話すこともない。夏休みなどの長期休暇に温泉旅行などのイベントがあっても、父は決まって寝坊し、旅行先のお出かけの予定が潰れてしまう。いつも母はそんな父を怒っていたし、私自身もそれが不満で仕方なかった。
今となっては、当時のワーキングバランスなどが社会的に皆無だったことも理解できるし、そんな時代に特に父の業界は働き詰めの生活を強いられていたと理解することもできるものだが、同時はもちろん家族からの理解を得ることは出来ない。父がいない家の子どもだと思っていたくらいには、父は家になかった、それは事実である。
それでは私が父との思い出を語れることはないのでは?というとそういう訳でもない。私は過去に父の駐在について行ったことが3回あるわけだが、この駐在生活という時間が家族の形態を一変させていた。というのも、日本ではあり得なかった家族団欒の週末が実現するようになるからである。
自身が海外で働いて知ったことでもあるけれど、海外営業組はどうやら海外にいると海外出張も近隣諸国になり、日本企業特有の不毛な拘束時間も激減、さらにはバケーションを取る人権を獲得することに成功する。こうなれば必然的に父は親としての時間を過ごす割合が増え、家族と顔を合わせるようになる。日本にいるときは、私の宿題など興味関心すらなかった父が、宿題を見る、授業参観に出席するなど、学校の諸々行事にも関わってくるようになる。そのため、学校の話題を報告する機会も増えるし、休みは決まって外食や買い物へ出かけ、長期のバケーションには家族旅行もできるようになるというミラクルが起きるわけだ。
こんな調子で、私と父の思い出は主に駐在生活の10年間ほどで培われたものである。もしかすると他の家庭よりもその長さと密度は極端に短く薄いものかもしれないが、今回はそんな海外駐在員の父と私の話を今回はお話ししていきたい。あくまでも私の場合に限定されるものの、今親の世代の方は、自分の子供が親の何を見て、何を学び、そして大人になってそれをどのように活かしていくのか一つの例として知っていただけたら嬉しい。帰国子女の皆さんは、自身の帰国子女生活と照らし合わせて棚卸し程度に使ってもらえたなら嬉しいなと思う。

1. 世界では日本人として生きる義務を負う
どこまでいっても我々は日本人として生きることを強いられる
ダイバーシティーだ、グローバリズムだと叫ばれている昨今、嫌悪感を抱く人も決して少なくない表題を最初に入れ込んでしまったかもしれないが、こういった平等やボーダレスを謳う耳障りの良い言葉がすんなり受け入れられる世の中が本当に実現すればどれだけいいだろうか。
日本以外のコミュニティーで生きたことがある人は上記の壁に十中八九苦しむのではないだろうか。というのも、日本でいる以上に「自分の国籍や性別と性質」に向き合う経験が増えるからだ。どんなに嫌でも、私たちは外で「日本人」として認識されるし対応を受ける。必然的にマイノリティーとして生きることを強いられる場面に遭遇することは多い。
そんな経験をビジネスの場で死ぬほど経験した父は、私たち子供にはいつも日本人であるという自覚から逃げないことを求めてきた。先にも言った通り、思春期は特に海外生活をしていると海外かぶれになりがちなこともあって、日本人として生きるのを強制されることは苦痛だった。特にアメリカに住んでいた頃は、何もかもが先進的に見えた。学校教育においても、自分でカリキュラムを組める自由度が魅力的だった。だからこそ、日本の集団意識や個性を殺して生きる文化が古臭く感じて馬鹿にしがちだったように思う。
「君はどこまでいっても結局は日本人なんだ」父の言葉は若い頃よりも今の方が理解できる。というのも、仕事で世界の人と会話すれば理解せざるを得ない。あえて日本人だからとネガティブな差別をされることはないけれど、どの組織に入っても特にグローバルな職場では自分の「日本人」というナショナリティーから逃げることはできない。なぜなら私たち人間は、相手と自分を区別して共感したり判断する傾向があるからだ。
「逃げる」という表現も実は変な話で、海外で出会った他の国からの帰国子女たちは自分の国から逃げるようなそぶりを見せたことがない。どんなに自国が貧困に苦しんでいても、内紛があってもだ。自分たちのルーツを否定する友人や同級生はまずいなかったし、自分の国についてある程度、理解して話すことができる子が多かった。事実から目を背けても、現実はいつまでも私たちから離れることはないし、否定したところで何もいいこともない。どう足掻いても私たちの手元に残るのは日本のパスポートであるには変わりない。
仕事をしているとスモールトークから逃げることはできない。いわゆる雑談というやつで、そのどのトピックも自分の国と比較しながら話すこと、それは相手の国を認めるための大切なベースになる。その会話が知識として蓄積され、国際舞台で活かされていく。どんなにエリートでも、このような場数が少ない人は国際舞台に立った時に失礼なことをすることが多いような印象すらある。
日本人が残念なことは、"How about your county?" の歴史的な問いや、文化的な問いに答えられない人がすごく多いことだ。特に政治や宗教、歴史を話すことはタブーで気持ち悪がられる国であるが世界はむしろその逆で、知識関心が自国にないまま世界に出てくることが悪い評価につながる。もちろん語学力は大切だし、覚える勉強やネームバリュー的な高等な教育も大切だ。しかし、このような基本的な部分を海外に行く子どもに話せる親は多くはない。仮に海外の良い学校に行くチャンスを得たところで、愛国心や自国を学ぶことの大切さを「外国人」にわざわざ教えてくれる親切な人はいない。これは国が成り立つ文化の中で、海外の子どもたちは自然に学び身につけているもので、学校の教育にここは入らないので大人は責任を持ってくれない。こういった自国への興味関心、自身が日本人であるという意識づけは、父は国際社会の中で学び、私たち子供にその鱗片だけでもなんとなく教えてくれようとしていたのかもしれないと今では思っている。

2. アジアという団体は強い
これからの時代はアジアだ
「いいか、お前が大人になる時は中国が考えられないくらいに大きな力をつけるだろう。インドもそうだ。人口が多くお金儲けに実直な国は絶対に大きくなる。日本にどんどん移民が押し寄せてきて、日本人がアジアに出稼ぎに行くようになるだろう」
これを父が言ったのは30年近く前のことだ。
当時の日本は、なんでもアメリカとイギリスで、白人至上主義だった。特にアメリカのファッション、音楽、全てがアメリカのエンターテイメントは斬新で派手でポップに映り、なんでもそれを基軸に世の中が動いているように見えたものだ。しかし、世界で働く父はもう違う世界線を見ていたようで当時の私は何を言っているのかわからなかった。衛生面も乏しい、食文化も似通った、物価の安いアジア諸国が世界から一目置かれる時代が来るなんて思ってもいなかったのだ。
ところがどうだろう?今やアメリカも欧米諸国も経済政治を行う上でアジア諸国を無視することはできなくなっている。経済成長率もインドと中国は日本の比べ物にならない。欧米諸国に至ってはアジア外交を無視できない。物流、製造、ITも何もかも外注する先はアジアであり、最近はブレインとなるエンジニアはインドが強い。MADE IN CHINAの中国はもう下請けではなく、自らのブラントでアジアを中心に展開、日本の製品よりも手を伸ばしやすい価格帯でデザイン性も高い。私のウルトラワイドモニターもXiaomi製で、もう何年も使っている。
そんなわけで、車が強い日本、電化製品が強い日本は一昔前の話となった。アジアが技術を学び、どんどん安く品質もそこそこ安定したものを短期間で送り出す、それをファストファッションのように買い替えていく、そんな世界をアジア諸国が作り出しているような印象さえある。
そうとは言っても、長い歴史の中で積み重ねられた日本の技術や丁寧な作業、職人気質とノウハウはアジア諸国の中で群を抜いていることを世界もまだ知っている。だからこそ高い賃金と頭打ちの上下社会に嫌気がさした優秀な人たちが日本から逃げるようにアジアとオセアニアへ出稼ぎに行くようになった。まさに父が私に言っていたことが今現在行われていて、私はその言葉を真に理解できなかったことを若干後悔している。今のトレンドに踊らされず、世界のポテンシャルを見抜く、それが世界で戦う父が肌身で感じてきたことなんだろうと思う。

3. 技術
探究心、こだわりは日本の製品の強み、安く買い叩かせるな
父は兼ねてから日本の技術の高さについて、世界はまだその段階に来ていないと言っている。何度も何度も試行錯誤を重ね、誤差を許さない。一見無駄に見えるような緻密な努力とすり合わせが、信頼のMADE IN JAPANなのだという。これは我らの先人が持つ、こだわる職人気質が培った世界からの信頼なんだろう。
最近の技術は車や電化製品よりも日本食や日本食材技術、すなわち発酵、旨味に関わるものが世界で認められている。街を歩いて日本食がない場所がなくなったし、一昔前はアメリカでフェイクな日本食がたくさん流行っていたけれど、今はお味噌汁に砂糖を入れる場所なんてかなり少なくなったんじゃないだろうか。「美味しいものは美味しい」それは世界の人も分かっていて、日本食を求めに日本に足を運ぶ人も多い。日本に駐在で住んだ人は、大抵日本食の虜になって現地に戻る。豚骨ラーメンは世界で大人気で、渋谷に行けば観光客で列をなしている。
こんなにも日本には売れるものがある。でも、日本のビジネスは値切ることに長けていて、高く正当な値段で海外に物やサービスを売りつけるのが苦手だ。言語や文化の問題もあるだろうけれど、特に技術者の人はお金を儲けることに興味がない。だからこそ、海外の人は日本の良い製品を安価に買い付けられることも知っている。結果的に、日本の製品価値を安売りすることに繋がっており、日本が豊かになることの弊害となっていると父は言う。
「これはこの値段だから出せないなら買わなくていいよ」といったスタンスが品質の保証につながるという考え方が今後の日本に根付いていかない限り、経済は潤わないし、私たちのお給料も上がらない。日本の人材は海外に流出していくのはこう言った理由もあると思う。寿司職人、美容師、看護士などは海外に出ると2〜3倍の給与になる。そして労働環境が緩和されるという。要するにそれだけ日本の技術や丁寧さは海外のニーズがあるということなのだろう。

4.責任
物事には責任が生じる、それをどう扱うかも責任だ
父は何度か責任を取らされている。それは自分の責任ではなく、父の所属しているチームの責任を取らされたり、父の部下がやったことであったりだ。その詳細までは当時わからなかったが、後々知った事実はかなりエグいなと思うようなこともあり、そんなことにも逃げず立ち向かった父はかっこいいとも思えた。人生は自分がしたこと以外の責任を取らされることもあるし、特に企業で働けばそういう他人のしたことで自身が巻き込まれて成功から遠ざからないといけないこともあるようだ。
父がいう責任を担うの種類は色々である。それは駐在だとより子供の目にも分かりやすく見える場面があった。父はアメリカのとある小さい街に出向した。街のダウンタウンと呼ばれる中心部の一番目立つタワーオフィスの中に小さく会社があって、父は唯一の日本人だった。そこのオフィスを閉めるかどうかは日本の東京のオフィスに采配がある。実際こんな感じで、父が任期を終えるときに後任者が来ないこともある。このように小さな都市はアジアアメリカヨーロッパにかかわらず突然本社の一存で、どこかの大きな都市でまとめて管理するために支店を閉じてしまったり、現地の人にその支店を任せたり、はたまた完全に無くしてしまったりを簡単に決断してしまう。
企業の判断と考えれば普通のことかもしれないが、そこで働く人にとっては働き口が突然なくなるのは一大事である。遠い海の向こうの人は、世界に散らばる支店や出向先はチェスの駒の一つでしかないと父は言うのだ。だからこそ、人間が実際に働いていることを知っている現地に派遣された父が、自分を送った本社と自分が守らないといけない現地の従業員の間に立って何度も働きかけてきたことも知っている。そういったことに昼夜構わず邁進してきた父をなんとなく子供たちも知っているのだ。父の最後の駐在地の住まいを片付けに行ったのは私がもう30歳を過ぎたころだった。今回もなんとか支店を保持して現地人に社長を任せられたんだと嬉しそうに呟いた父を見た時は、この人はそうやって責任を最後までまっとうしたのだなと、わが父ながら誇らしく思えたものだ。
こんな父は、私に対してもビジネスライクな節がある。言い方を変えれば、自分の決めたことへの責任に容赦がない。例えば、私が何かをしたいと決める時は基本的にプレゼンが必要だ。なぜそれをするのか、いつまでにするのか、どれくらいの費用がかかって、それを成し得る覚悟と採算はあるのかみたいなことだ。
正直、学生の頃はこの言語化する作業が煩わしく父が疎ましかった。しかし社会人になって感じるのは、仕事で会社のお金を使うのにも関わらず、そんな基本的なことができない人が多すぎるということである。責任の所在をうやむやにしたり、なんとなくでやる人が多い。そして結果が悪ければ反省するふりをして逃げていく人が多く再発防止策を話し合う前に違う仕事で紛らわす。若い世代は教えてもらってない、言われてないなどの言い訳がとにかく多い。考えるよりも言い負かす文化が重要視され、何よりもどうしてそれをするのかを話していることは無駄でありインスタントな風潮がトレンドのような感じがする。リズムやテンポが大事で、世の中で流れる音楽の歌詞に意味がないのと同じように、中身を吟味するふりが上手で、実際はただ風習に流されている中身の薄い会議が山のように存在する。
こんな私の拙い社会人生活だが、父がローカルや部下を守ろうとして自分で考えアプローチする姿勢は、私の社会人生活の行動を大きく助けてきた。仲間に誠実で、自分のするべきことを計画し、達成可能かを判断して業務に取り組む。間違たら見直し、切り替えて進み続けるガッツを持つこと。それは一人の社会人として企業に属す上で必要な資質だと感じている。こういった当たり前だけれど当たり前にできないことを背中で教えてくれた父には、歳を追うごとに感謝しかないなと感じていることだ。

5.人を大切にする
自分さえ良ければいい、それは世界中どこでも自分に返ってくる
その人の気持ちになって考えること。その重要性は両親から昔からしつこく言われてきたことだと思う。子供の頃は、相手が嫌なことはしてはいけないよとよく言われていたし、仲間に入れてあげなさいだとか、仲良くしてあげなさいだとか色々注文の多い親であったと思う。
いつかだろうか。「もしこれが自分だったらどのような気持ちになるのか」と息をするように考えられるようになった。そして、それを人はあまり気にしていないことに気づいたのは。あんなに偉そうにしていた大人たちも、実はそれを自分たちはしていない。自分だったら耐えられないのに、自分は今楽しいから、楽だから、気にしないで自分の快楽に走りがち、それが人である。自分がやられたら怒るのに、人にしてしまう、それも人なのだ。
海外に出ると、私たちはマイノリティーになり、そういった被害のような経験が爆発的に増えることになる。被害者意識を持って、いつも自分が孤独で辛い存在のような気になる人もいるだろう。そうなってくると「自分を守る」が故に自分さえ良ければよくなりがちだ。
残念なことにこう言った思考に入ってしまうと、長く付き合える友達はできないし、教師ともうまくいかなくなる。孤独がまた孤独のループに入るし、少数の友達に「依存」してわがままになったり、過剰に「期待」をして少しのことで裏切られたと嘆く人もいる。そうやって心を閉ざす、人を利用するためだけに近づいてくる駐在員の奥様や、学友、そして仕事の仲間を見てきた。みんなトゲトゲしてマイノリティーとして生きているからこそ、生きることにフォーカスしてしまい、相手を思いやる心を忘れがちになる。
これは長い目で見ると本当の孤独を呼ぶ。だからこそ、私は両親から学んだ「人を大切にする」「人の立場に立って考える」ことをやめないようにしたいと考えているし、社会人でもできる範囲で人の立場を考えた行動を取りたいと思っている。そんな少し暑苦しい私に嫌気がさす人もいる。でも結果、私には幸いにも世界中に多くはないが大切にできる友人や恩師がいて、みんな私を大切にしてくれているし本音で話すことができる。私の愚痴に対して本気で提案してくるアメリカの友人は妹までお世話をしてくれるし、高校の恩師とは日本に帰国してからクリスマスカードの交換を欠かしたことはない。現地で仲良くなった仕事のローカルともSNSで連絡を取るし、日本に遊びにくれば一緒に出かける友人に今はなった。
そんな人を大切にしていいことしかない人生を教えてくれたのは両親だと思っていて、私は裏切られたりしても悲しけれど相対的に見れば良いことの方が圧倒的に勝っていると思っている。特に世界に出れば、正直者で素直に向き合う人の方がわかりやすいし、海外の人はそういう人の方が向き合いやすいと決まっていってくれる。最初は引かれても、最後は違いすぎるからこそそのようなエキストラな感情表現だったり意見交換が功をなすことが多いと思っている。
海を渡るからこそ自分を見つめ直そう
「MAYは今まであった日本人の誰よりもパッションがあるし、日本人っぽくない。何を考えているか日本人はわからないから」と言われることが多い。でも本当はそれは寂しいことだ。だって、日本人はみんなパッションがあるし、みんな考えていることがある。熱い想いだってあるだろうし、彼らの恋愛や家族とのゴタゴタやドロドロ事情を見ていると実に人間らしいじゃないかと思う。怒ったり笑ったりするその自分の中にある感情は相手にだってあって、それと必死に調整を図っていることを私たちは日々やめていない。
ただその人と向き合うパッションを限定的な範囲にして、他の人を人間として見做さない、他人として何か物のような感覚で判断するというハートレスな部分が日本人にあるように思う。隣で危ないことをしている子供を注意しない。巻き込まれたら面倒臭い。政治にも興味はない。でも税金が高くなることは不満だ。そんな受け身文化を享受したまま、英語だけできたり、勉強だけできたりしても、これからの時代は世界の人と向き合うことができなくなる。人生経験がネットとゲーム、そしてごく限られた薄い人間関係では、ビジネスで相手の心を掴むことが難しい。そしてなんだかんだ、みんな一人が嫌だから年齢を重ねると周りに人が欲しくなる。だからこそ、父が言ったように私は人と関わりながら人とビジネスをして、人と交わって生きていく。そうすればきっとわからない文化も、宗教も、そして習慣も、いい塩梅でお互いが譲歩し合える優しい空間を作れるはずだと信じているからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
