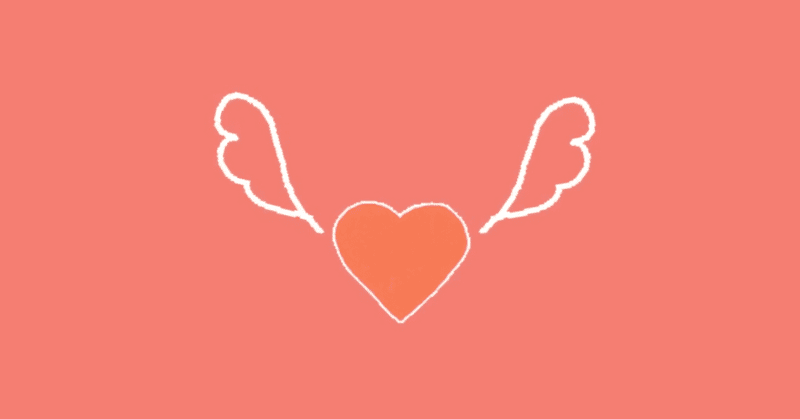
統合失調症の詩学
心の哲学の問題系の一つに、心的原因と物理的原因は同一のものであるか? というものがあります。これは極めて難しい問いで、完全な形ではこの問題の答えは未だに出ていません。
例えば、心的原因なるものが物理的原因から「独立」して存在しているのだとすれば、如何なる物理的原因もが排された場所にも心的原因は存在している可能性があることになります。そうした「可能性」は具体的に何を意味しているのか? 如何なる物理的性質にもよらずに生じ、しかも存在を存続しうるような「何者か」とはとどのつまり何であるのか? ……謎は深まるばかりです。
ここで、もしも物理学の完全性を心の領域にまで敷衍するなら、心的原因と物理的原因の間の差異は消え去るのかもしれません。しかし、物理的な機能だけで、本当に私たちの心のすべてを解明できると言えるのかどうかは、やはり非常に難しい問題であると言わざるを得ないでしょう。
例えば、一般に、大脳皮質に電流を流すと、言語に対しては陽性効果(刺激)と陰性効果(干渉)というような二つの効果が引き起こされますが、いずれの効果の場合でも、「脳」という何らかの物理的な器質があって、その構造の物理性の一部または全体がその主体の「心」に影響を及ぼしているような図式を考えられます。この時に、仮に心的原因と物理的原因が同一であれば、脳と心は同一であると言いうる余地が生じるわけです。こうした事例というのは「心の身体的基礎」を表現するものであるとも言えるかもしれません。
では、そうした「身体的基礎」なるものとは何か? という問いも新たに生じてきます。このテーゼは、そもそも何が心の条件として要請されているのか? というふうにも言い換えられるかもしれません。
また、仮に心的原因と物理的原因の間に何らかの差異があるとしても、それらを現実的に鑑別可能であるかどうかはまた別種の問題ともなります。
例えば、感受性、知能、意志といった現象がそれぞれに別個の心理的実体であると考えられる時に、だからと言って、それらを明確にそれぞれに切り離された形で鑑別可能であるとは必ずしも言えないでしょう。それらは相互に深く連携しており、理論上はこれらの諸概念を切断可能であるとしても、リゾーム状にどこかしこが接続し合っているそれらの間のある種の絆を切り離すことは容易ではないからです。
ジルボーグの『医学的心理学史』には、「天才は狂気でありながら、しかもなお天才でありうる。つまり文明に対する一つの貴重な宝でありうる。必ずしも常に最も貴重であるとはいえないが、たしかに貴重な宝でありうる」という一節が書かれていますが、こうした現象も上記のリゾームの一例に数えることができますし、それと言うのも、天才性と狂気性の単純な切断が不可能であるということを示唆しています。一般に「天才と狂気は紙一重」と言われるのはそれなりに理由があってのことなのです。
精神障害が超自然的であるとする見方と自然的であるとする見方は必ずしも相容れず、しばしば対立さえしていますが、超自然的な賜物に重きを置く宗教的および魔術的な諸派からすれば、時に形而上的でさえあるその現実を絶えず超克していく力強い理論的な経路にさほどの違和感はないようです。一方で自然主義的な見方は主に精神医学に見られます。精神医学がしばしば宗教者を精神障害者に見立てることで攻撃しているのは、そもそもの現象の根にこうした対立関係もがあるためです。そこには一筋縄ではいかない、リゾーム状の関係の束が無数にあり、また複雑に渦巻いてもいます。
精神障害者はナチスによるホロコーストなどの事例に見られるように、史上においてもしばしば迫害されてきましたが、そこには精神障害者たちによる勇敢な「反抗」の爪痕もが作用しています。そうした反抗の「健全性」は精神障害者たちが彼ら自身の「力」を回復していくための一つの経路ではあるのであり、ゆえに彼らは精神障害でありながらも、その攻撃性は本来的に健全なものでもあるのです。
一般に、注意散漫な子供に対する工夫として、抽象性の事物よりも具体性の事物の方を重視することで対処する方略もある一方で、逆に、「注意散漫に見えるが、実は高度に抽象的であり、高度すぎるがゆえに周囲からは具体的にさえ見える」ということも考量してみるべきです。つまり、具体性の現象化、そのいわゆるところの「問題行動」の奥には、花開けば素晴らしいギフトが眠っているかもしれません。ADHD式の問題行動は実は何らかのギフテッドネスの芽吹きであるのだ……ということは常にありうることでしょう。こうした現象的な逆転は多くの事物に関連して想起することができます。
精神衛生の基本的な対処術は主に二つに大別されます。一つは精神衛生に害をなす現象自体を除去することであり、もう一つはそうした何らかの意味で加害的な現象への「耐性」を養うことです。これは天才と狂気の場合のように、緊密に連関し合っている概念の系列ですから、それらの差異を明確に抽出することは難しいです。つまり、とある耐性による受忍が、その実のところでは自分の敵対者の除去、排除として現象するということが常にありえます。ゆえにこそ、精神衛生の問題ではナチス的優生学の持つアポリアが提起されます。つまり、「弱者は強者であり、強者は弱者である」というふうな逆説はその代表的なものです。こうした逆説が絶えずかもし出している「曖昧さ」や物事の「複雑さ」への耐性を喪失することこそが、ナチスの根幹的な要因であるようにも感じます。私たちが精神的な健康を保っているためには、物事を単純に考えすぎず、複雑なものを複雑なままに考慮できる胆力のようなものが要請されます。言うまでもなく、それには高度な抽象化能力もが重要です。そこでは哲学などの諸学問もその力を発揮できるかもしれません。
ジュリア・クリステヴァの『初めに愛があった』によれば、精神分析とは超人の倫理上の裏打ちであり、歯止めであるのだと言います。ニーチェはルサンチマンに対する超人としてのありようを提起することで、この世の価値を転換することを試みていますが、これは憎悪に対する「愛」の優越に比する問題の系列であるとも言えます。つまり、初めにあったのはとにもかくにも憎悪ではなく、愛であったわけです。ゆえにこそ平和が特権的に要求されます。この系列がもしもルサンチマンに敗北して逆転していたのなら、世界は永久に争い、また倫理的にも平和の希求は不可能であるというような恐ろしい事態になっていたものと思われます。精神分析などの正統な心理療法は、そうした愛の系譜の上にあるべきものでもあります。憎悪による害意に駆動されるような心理療法があってはならないのです。
認知的複雑性のポイントもこうした愛による作用を受けて成立します。愛とは主に外部への包摂をその作用の特徴としていますが、これは具体的に見ると、何らか異邦人へのある種の「優しさ」を帰結します。そのことは外部の現象を認識内に取り入れることを可能にするため、情報を構成する要素数の爆発的な増加をしばしば帰結します。それらの要素がさらにそれぞれの思考の処理を受けることで「認知」はさらに複雑化するのです。こうした複雑性はつまり、愛の作用の結果であるとも言えます。しばしば賢者の多くが複雑怪奇な行動なり言動なりをするのも、愛ゆえのことです。そして、そうした複雑性が実は最もシンプルな現象である、愛を帰結しているのですから、世の中というのはロマンチックですね。
この時、諸々の肉体的欲望から「愛」が切断されているわけでは必ずしもありません。むしろ、愛は憎悪ではなく、つまり肉体的欲望を排除しないからです。精神分析の用語で、こうしたシステムを「昇華」などと言うとしても、事情はそれほどには変わらないでしょう。如何に多くの偶像も、すべて唯一の神様に帰結しているのですから、どんなに穢れた場所でさえも美しい蓮華の花を咲かせることができるということでもあります。これは精神障害の場合でも例外ではないのです。
中井久夫は、言語はコミュニケーションの大きな道具であるという側面を見ると同時に、コミュニケーションを「拒絶」する道具であるという部分をも偏りなく洞察していますが、こうした出来事の持つ両義性を正確に見抜くことはあまり容易ではありません。多くの人の場合、そうした現象の複雑さに挫折し、物事を単純化するか、自身の認知を乱す対象を排斥することで狭量な自分の精神衛生の安定を図るか……そのどちらかでしょう。おそらくアレント的な「凡庸な悪」はこうした精神衛生的な恒常性の要請からもたらされることも多いのではないかと私は思います。そこではあらゆるものが単純化され、そのためにあらゆるものが殺戮されるのです。これが強迫的な「清潔」観念の徹底の先にあるものであり、公衆衛生を司る人々はその点によく注意しておくべきでしょう。
さて、私のこの言語は、中井久夫の提起するような仕方で、みなさんを「拒絶」するためのものではないのですが、それでもかなり難しいところもあるかもしれません。つまり、「一見すると拒絶に見える奥にある、本当の愛や優しさ」を見て欲しいと思っています。そうしたコミュニケーションの二重性は統合失調症においては、ベイトソンらの述べる「ダブルバインド」のような精神の拘束具となって、患者を奴隷化させてしまいますが、常に「それでも」と愛する姿勢こそが真に治療的なのだと思います。患者の持つ今にも崩れ落ちそうな世界を、どうか見捨てないであげてください。そのたった一人の世界の中で戦っている、彼らの勇気を嘲笑しないでください。初めにあったものが、何であったのか? どうかそれを思い出してください。
あなたの拒絶が、いつか愛へと平和につながることができるように。祈ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
