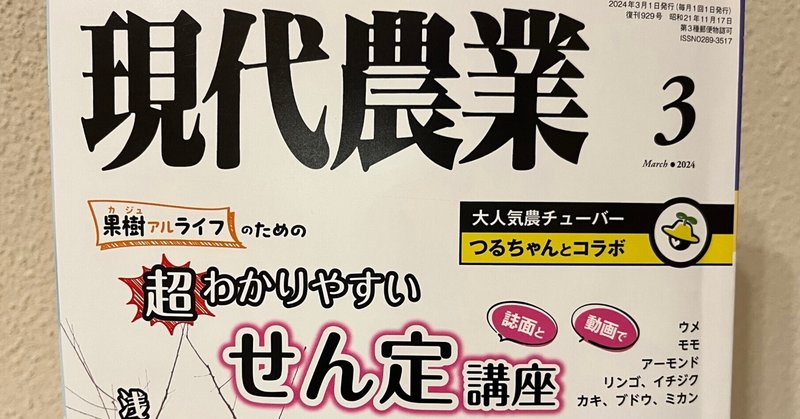
接ぎ木の極意(現代農業より)
現代農業 2024年3月号
農文協
本誌で「接ぎ木の極意」が記載されていたので紹介します。
192ページ
「サンショウの苗木づくりに挑戦」
〜成功率95%! ブドウサンショウの接ぎ方〜
仲里長浩
そもそも、接ぎ木とは?
枝などを切り取って、同種または近縁の他の植物の幹に接ぐこと。接ぐほうの枝を接ぎ穂、根のある接がれるほうを台木という。

接木のイメージは、別々の個体である地下部(根)と地上部(枝)をつなげて1つの植物体を形成することです。
なんで接木をするの?
「2つの品種のイイトコどりをする」ため。
台木は土壌病害に強い品種が選ばれます。
一方、接ぎ穂は果実品質の良い品種が選ばれます。
両者を接ぎ木することで形成された個体は土壌病害に強く、果実品質の良い個体になります。
これが接ぎ木の目的であり、台木と接ぎ穂の「2つの品種のイイトコどりをする」ということです。
接ぎ木を用いることで、
一本の木にミカンとレモンとハッサクを実らせたり、
トマト台木の上にナスの接ぎ穂をつぐ、
なんてこともできたりします。
接木の課題は?
接木は素晴らしい技術ですが、なかなか成功しないことが課題です。
切断した植物同士をつなげるわけなので、失敗しやすくて当然です。
現代農業の記事
さて、本題です。
現代農業の記事では接木の基礎的なポイントに加えて、
「形成層の厚みの見極め」が極意として取り上げられていました。
基礎的なポイント
まずは、基礎的なポイントから。
台木の栽培適応能力
栽培する地域の気象条件に合った品種を選ぶこと。
記事では「栽培地域に近い山林に自生するフユザンショウから種子を採取し、実生苗※を用意することをおすすめします」とあります。
※種を発芽させて育てた苗接木を行う時期
いつ接木を行うかも成功確率に影響します。
記事では柑橘は冬季に接ぎ木するのが一般的だとした上で、サンショウの場合は「氷点下を下回る地域では、氷点下を上回る気温になってから接木する方がよい」とあります。
理由は「癒合部で凍結が起こりやすく、組織が破壊されるために接木が失敗すると考えられている」そうです。清潔な刃物を使う
接木では切断面を密着させるため、刃物の切れ味が大切です。
加えて、刃物を通じてウイルスが感染しないよう「あらかじめ洗剤やアルコールなどで清潔にし」「キッチンハイターを薄めた液を染み込ませたタオルなどで拭くのもおすすめ」とあります。
形成層の厚みを見極める
サンショウにおいて、接木の成功率が60%→95%に改善したポイントは「形成層の厚みを見極める」でした。
台木と接ぎ穂を密着させる際にそれぞれの形成層を合わせて、台木から接ぎ穂へ養分が行くようにすることが重要です。
では形成層の厚い部分を断面に選ぶためにはどうすれば良いか?
「芽やトゲのある部分の側だけ形成層が厚い」

これが重要です。
枝の断面図を確認してください。
上側の芽やトゲのない部分より、下側の芽やトゲのある部分は形成層が厚くなっています。
つまり、「芽やトゲのある部分」を断面にして接木を行うことで、成功率を高められるということです。
これはサンショウに限らず、柑橘やその他の品目でも応用することができると思います。
接ぎ木で台木と接ぎ穂を用意する際に「どこで切れば、大きな形成層を断面にできるか」を意識したいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
