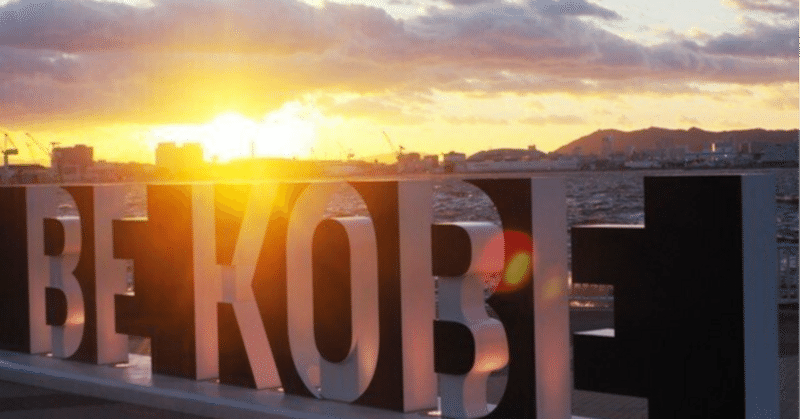
20249508 神戸だんじりの謎
GWはいろいろあって神戸のだんじりはみにいけませんでした。・゜・(つД`)・゜・。まあでもGW
以外にも五月にするところもあるのでそれをみにいけたら…と日程を調べようと思ってふと気づきました。
なぜ神戸のだんじりはGWに開催されるのだろう?
だんじりといえば真っ先に思い出されるのであろう「岸和田のだんじり」は秋のものですし,灘のけんか祭などは「播州の秋祭り」と総称されるように兵庫南部の他の地域でも秋に祭をするところが多い気がします。
この「GWに開催する理由」というのは神戸のだんじりを知るための重要な視点だと思うので今後調べていこうと思いますが,今資料などをみずに勝手なストーリーを考えておこうと思います。
仮説1 都市部で農作業に従事する人が少ないため収穫を祝う秋祭が存在しない
東京集中の今では関西は地盤沈下しておりますが昔は日本一の都市だった時代も結構あったと思うので,神戸市の東灘区や灘区のあたりなどはかなり昔から都市部で農業以外の仕事をしていた人が多かったかもしれません。その場合,神社などは存在していても例大祭として秋祭を行わないところが多く,そのためだんじりも秋ではなかったのかもしれません。
仮説2 本格的な復興は1980年代くらいからであるため
数百年の歴史があるだんじりもあるようですが,おそらく本格的に復活したのは1980年代くらいからのところが多かったようで,それならば「みなが休みやすい時期」としてGWが選ばれるのが分かる気がします。
1980年の頃はまだハッピーマンデーがなかったので秋の祝日は不安定でなかなかまとまった連休はとれなかったのに対し,5月3日と5月5日の間の5月4日も休みにするとなったのは昭和60年の祝日法の改正からのようなので,ある意味その変化があったから,全国的に「GWの5月3~5日の間に祭をしたい!」という動きができて,神戸の場合はそこでだんじりをGWを集中させることになったのではと推測しております。
仮説3 夏は地蔵盆があるため
神戸でも地蔵盆は結構盛んにおこなわれているなあと思われて,おそらくですがだんじりが途絶えていた時代でも地蔵盆は継続されていて祭を担うコミュニティの素地は維持されていたのではないかと。そしてそのコミュニティで「もっと派手に楽しめる祭をしたいね」ってなった時に,だんじりの復活が選択され,夏以外の季節としてどうするかとなってGWが選ばれたのではないかと。
もうこれは何の資料も読まないでの勝手な推測を書きましたが,この問いに答えてくれる文献が見つからなかったとしても,まだご健在であろう1980年代あたりにだんじりブームを復活させた担い手の方々に聞けばこの答え合わせはできるので,なんとかこれは答えをみつけてこのNOTEに書きたいと思います。
【書誌情報】
吉川 勉・阿部経一・石本幸市郎・高西清成・玉城晴也・瑞原 桃・岡本侑佳・野田浩佑・甲南大学久保ゼミ・久保はるか 2018 僕たちが紐解く『魚崎』のキオク -二つの『だんじり』.「大学周辺地域の歴史を知る」シリーズ(甲南大学法学部久保ゼミ), 2, 29 – 36.
魅力的な文献が見つかりましたがあと3分で帰らないといけないのでまた明日読みます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
