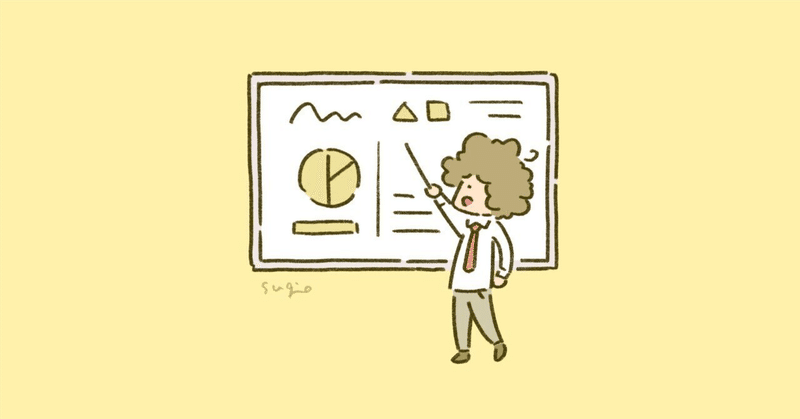
Photo by
shinsukesugie
20240507 教材の発達
今日は日本心理学会の大会原稿に集中する予定でしたがラッキーなことに締め切りが1週間伸びてくれたので明日の授業の教材の改善をすることにしました。1時間くらいで終わるつもりがなんだかんだで数時間かかってしまい祭心理学NOTEを書く時間がなくなってしまいましたが,まあでも教材が発達したと思えばいいとしましょう。
基本的に教材は「最新の知見に対応できるようにブラッシュアップする」という方向で発達していくのだと思いますが,それ以外の要因での変化もやはり多いだろうなと。
私が最近実施することが増えたのが「簡便化して分かりやすくして学生の負担を減らす作業」だなと。「分かりにくいけど口で説明すればいいよね」と思っていた教材では話を聞いていなかった学生が作業に詰まることが増え,そこで投げ出されてしまうのを避けるために作業が分かりやすい教材に変えていくことが増えた気がします。
これはおそらく「学生の理解力の低下」ではなく,小中高の段階での教材の改善が進みまくっているから,大学の教員が片手間で作った教材では不満がでやすく,そのため飽きたり投げたりする率が高くなってしまうのだろうなあと。
大学の教材開発に関する論文もいっぱいあるのでいろいろ学んで教材を発達させることで自分も発達できるようになりたいなと。
【書誌情報】
貝瀬梨菜・小倉 康 2024 実験レポートの「結果」と「考察」の書き方を理解する自習用教材の開発. 日本科学教育学会研究会研究報告, 38(4), 53 – 58.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
