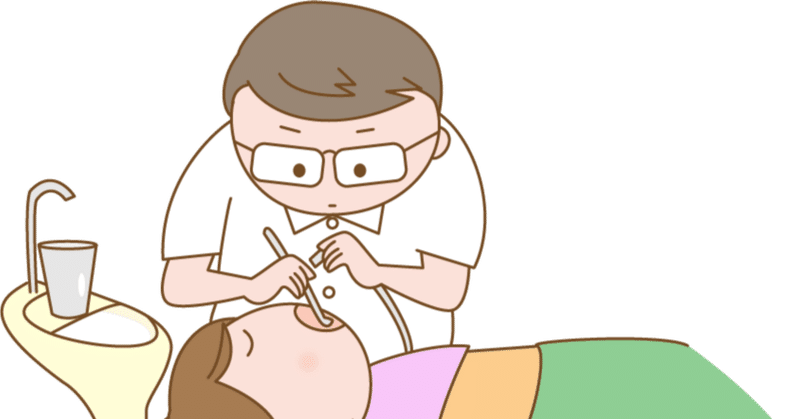
歯周病治療の闇~歯周病は一般の歯科医では治せません!~
歯周病の原因は歯石ではなく、歯周病菌類です!
1.歯周病とは
歯周病は歯肉炎から始まり、歯槽骨や歯根膜に炎症を引き起こし、歯を支える組織を破壊させる疾患の総称で、口内環境の清潔度が低く、歯周病菌類の繁殖が進んだ場合に発症しやすくなります。
※ 日本臨床歯周病学会より
https://www.jacp.net/perio/about/

2.歯周病の症状
歯周病の症状には、歯茎の腫れや痛み、出血、口臭、歯のぐらつきや移動、歯肉から膿が出るなどがあります。
しかし、初期の段階では症状がほとんどなく、気付かないうちに進行していることがありますので、虫歯がなく、普段、歯医者に行く機会がない方は注意が必要です。

3.歯周病の原因
歯周病の原因は、歯垢や歯石などの歯の汚れを放置することによって口腔内に歯周病菌類が繁殖し、歯肉に炎症を引き起こすことによります。
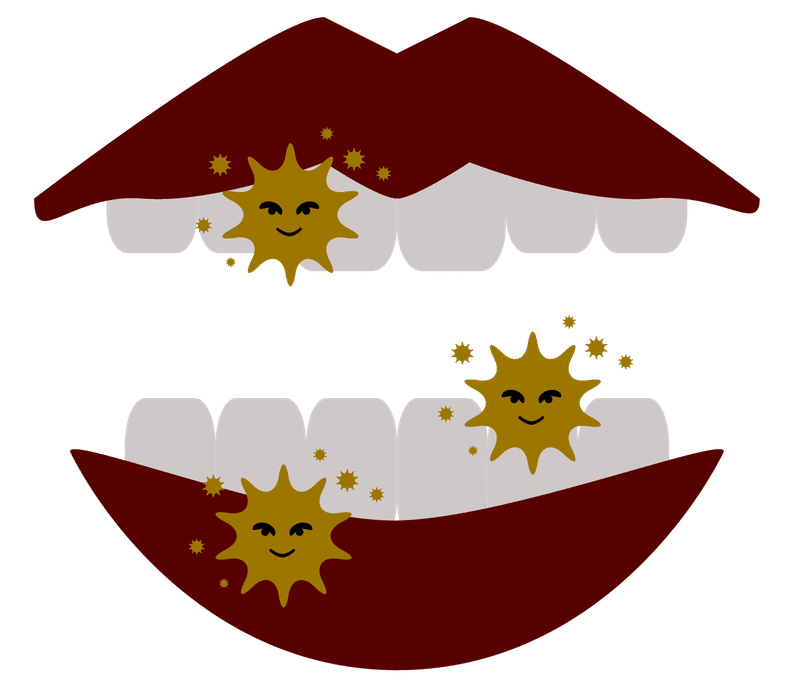
4.歯周病によるリスク
歯周病が進行しますと、歯を失う可能性が高くなります。
また、歯周病により発生する歯周病菌類が血液を通して全身を巡り、心臓病や糖尿病、認知症、各種ガンなど、さまざまな病気の原因になるとの警鐘もあり、まさに歯周病が寿命を決めると言っても過言ではないでしょう。

5.最新の歯周病治療法
歯周病は他の疾病と異なり、口腔内という外部環境に晒された非常に多種類の細菌や真菌、ウイルスが混在する状況において、その原因となるものを特定するのはきわめて困難です。
また、患者により口腔内の微生物叢の状況が異なるうえ、原因が複数あり、さらに、相互作用によって増殖・活性化させることもわかりつつあり、治療薬の有効成分特定や開発に時間を要しています。
ただ、最新の研究では、従来から指摘されてきたPorphyromonas gingivalisをはじめとした細菌による感染だけではなく、ヘルペスウイルスやCandida albicans(カンジダ真菌)も歯周病の病原体となることが明らかとなってきました。
このような状況において的確な治療を行うためには専門学会が推奨する従来からの基本治療法である歯石除去を中心とした対処療法では中度以上の歯周病に対し、進行を抑える効果はあっても歯周病自体を治癒することはきわめて難しいもので、結果として歯を失うことが多いのが現実です。
そこで登場したのが抗菌療法です。
抗菌療法は患者の口腔内の状況を観察し歯周病の原因となっている歯周病菌類を特定したうえで内服薬および歯磨き剤により除菌したのち、従来から行われている各種クリーニング治療を行うものです。
本治療法では口腔内に多数の歯周病菌類が存在しているなかで従来から行われているような歯石除去を中心とした外科施術を行わないため、外科施術によって生じる傷口から歯周病菌類が体内に侵入することによる感染症の抑止にもなります。
ただ、現在のところ保険適用外の自由診療のため、ごく一部の歯科医院でしか治療を受けられません。
※ 抗菌療法(歯周内科治療)とは
団体:一般社団法人国際歯周内科学研究会
理念:歯周内科治療を世界に広め、ペリオのない社会を実現する
使命:・歯周病治療に科学的な検査・診断を導入し、歯周内科治療の世界標準化を目指す
・口腔内微生物叢のコントロールを適正に行い、歯周病の改善と全身の健康増進に寄与する
・抗生剤使用の正しい知識について研究・普及を行う
・安心・安全な歯科医療のために院内感染防止対策の普及につとめる

6.歯周病治療の闇
歯周病は成人の約80%が罹患していると言われ、ギネスブックでは『歯周病は人類史上、最も感染者数の多い感染症である』と認定されています。
このように世界中に広く蔓延している歯周病ですが、他の感染症と異なり、口腔内疾患にとどまらず、長い年月をかけて心臓病や糖尿病、認知症、各種ガンなど、さまざまな病気の原因となることが明らかになりつつあり、その治療に対する重要性はよりいっそう高まっています。
しかしながら、一般的に実施されている治療法は旧態依然の対処療法である歯石除去等の外科施術であり、治療を続けても改善せず、歯を失うばかりか、さまざまな病気により健康を損なうことが多いのが現実です。
なぜ、このような状況が続いているのでしょうか。
その理由は国内でコンビニ以上に存在していると言われる一般の歯科医院では抗菌療法を実施するために必要となる高度な技術や高額の設備に対応できず、歯石除去を中心とした外科施術しかできないからです。
また、専門学会のガイドラインでも抗菌治療は抗菌薬の不適切な使用による耐性菌の発生や増加が問題となっていることから、基本治療は外科施術とし、抗菌治療は以下のような限定的な範囲とすることが明記されています。
① 通常の機械的プラークコントロールでは十分な臨床改善がみられない治療抵抗性および難治性歯周炎患者
② 広汎型重度慢性歯周炎患者および広汎型侵襲性歯周炎患者
③ 糖尿病などの易感染性疾患患者
④ 動脈硬化性疾患を有する中等度・重度歯周炎患者
⑤ 歯周治療を行うことで生じる菌血症に対して最上リスクを有する歯周炎患者
本来、より有効な治療法が登場してきたならば、国や専門学会が歯科医に対する技術指導や設備導入補助などを推進し、新しい治療法を普及させるべきところが、実際には遅々として進んでいません。
先般、国民皆歯科健診制度を導入し、歯周病の早期治療による医療費削減を図る旨の発表がありましたが、旧態依然の歯石除去を中心とした外科施術ではなく、より有効な治療法を普及させることも重要ではないでしょうか。
一人でも多くの方にこのような歯周病治療の闇についてお知りいただき、適切な歯周病治療をお受けいただくことで、歯を失ったり、寿命を縮めることのないよう切に願っています。
※ 特定非営利活動法人 日本歯周病学会編 『歯周治療のガイドライン2022』より
※ 特定非営利活動法人 日本歯周病学会編 『歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライン』より
※ 参考文献
Co-Infection of Oral Candida albicans and Porphyromonas gingivalis Is Associated with Active Periodontitis in Middle-Aged and Older Japanese People
Iori Oka, Hideo Shigeishi * and Kouji Ohta
Medicina 2022, 58, 723.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
