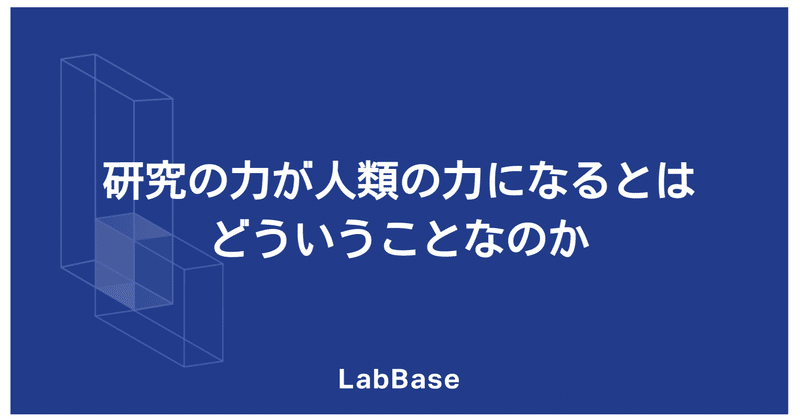
研究の力が人類の力になるとはどういうことか
2022年9月1日に「株式会社POL」から「株式会社LabBase」への社名変更と新Purpose「研究の力を、人類の力に。」の発表がありました。 今回の発表をきっかけに少しでも「研究」について知ってもらえたらと思い、9月1日から1ヶ月間 #研究アドベントカレンダー を実施していきます。
今回は株式会社LabBaseにて事業企画というチームに所属する私、飯田が担当します。
「研究の力を、人類の力に」
というのが私たちLabBaseの掲げるpurposeである。
このpurposeを見て、どのようなことを思い浮かべるだろうか。
「研究の力」が「人類の力」になるとはどういうことなのだろうか。
実はその実例は身近なところに溢れているのではないかと思っている。
私たちの現在の生活が、「研究の力」で出来上がったものだからだ。
このnoteでは、今当たり前にある身の回りのものがどのような歴史をたどり、「研究の力」が「人類の力」になってきたのかについて、いくつか一緒に例を見ていけたらと思っている。
▼CASE1 電球

電球といえばエジソン。
言うまでもなく私たちの生活に電球による照明はかかせない。
だが、電球ができる前はどうやって灯りを確保していたかご存知だろうか。
紀元前から室内の照明はロウソクだった。
貴族や聖職者はミツロウから作られた質の高いロウソクを使ってあたが、庶民が使っていたのは獣脂を使用したロウソクだ。このロウソクは嫌な匂いと煙を出すものだった。
18世紀頃に新たな手段が生まれる。鯨の脳油である。鯨の頭蓋骨の中に大量の油があり(なぜ油があるのかは今でもよくわかっていない)、その油を使ったロウソクは獣脂のロウソクと比べて煙も少なく、火持ちもいい。
この新しい照明が優秀すぎて1世紀の間に30万頭もの鯨が殺されてしまったそうだ。電球による照明が生まれていなければ、鯨は絶滅していたかもしれない。
▼CASE2 冷蔵庫

19世紀初頭。ボストンのテューダーという青年が、ボストンで取れた氷をハバナに船で運んで販売するビジネスを思いついた。
ボストンでは氷は珍しいものでなく、冬にとれた氷を地下で保存し、夏に飲み物を冷やしたり、アイスクリームを作ったりしていた。
ボストンでは氷を買う人などいなかったが、南部の暑い地域であるハバナでは氷を欲しがる人がいるのではないかと考えた。
しかしこれがなかなか大変だった。1つ目の困難は、当たり前だが運ぶ途中で氷が溶けてしまうことである。テューダーはおがくずを使えば氷を溶けずに運搬できることに気づく。
もう1つの困難は、ハバナの人々は氷を見るのも初めてという人が多く、その価値が最初は伝わらなかったことだった。しかし冷やした飲み物を飲めたりアイスクリームを食べたりするなかで、最初は贅沢品として、次第に必需品として受け入れられていった。
氷貿易がビジネスとして成立した時には、既に最初に氷を運ぼうとした航海から30年が経っていた。
このテューダーの努力がアナログの冷蔵庫の発明につながっていく。最初に冷蔵庫の需要が生まれたのはアメリカの食肉産業であった。テューダーが苦労の末に確立した氷の運搬、保存方法を応用して、天然氷を利用したアナログな冷蔵庫が生まれた。
しかし面白いことに、人工の冷蔵庫はまったく違うニーズから誕生している。
テューダーの確立した氷ビジネスは、医療の変化ももたらしていた。氷は患者の熱を下げるためにも使われていたのである。
だが氷貿易は年によって氷が不足することもあり安定的に供給されない。それに困った医師が、当時発展した熱力学分野を応用し人工で冷気を発生させる装置を開発した。
冷蔵庫の始まりは、食べ物を冷やすのとは違う用途で開発されたのである。
▼CASE3 大衆音楽

研究から生まれた成果が、文化にも影響を与えているという少し毛色の違う例を。
20世紀初頭。アメリカのド・フォレストという発明家が「オーディオン」(現在のラジオのようなもの)を発明した。彼の好きだったオペラを誰もがどこにいても楽しめるようにするために。
1910年、世界初の公共ラジオ生放送が行われた。しかし、街のいろいろなところに受信機を設置し大勢の記者を招いて大々的に宣伝したにも関わらず、受信機からは雑音しか聞こえなかった。
ド・フォレストはオーディオンを誇大宣伝した罪で収監されてしまい、弁護料を払うためにオーディオンの特許を格安でAT&Tに売却する。
実は、ド・フォレストが設計したオーディオンの仕組みはラジオの仕組みとしては正しい形にせまっていたものの、本人はその仕組みを完全に誤解していたのである。
特許を買い取ったAT&Tはオーディオンを仕組みを活用しアレンジして精度を向上させていき、ついに真空管(電気信号の増幅装置。真空管ラジオでも使われている)を完成させた。
この真空管の発明がラジオの発明につながり、1920年代にはラジオ放送が普及する。
はじめはニュースなどを流していたラジオ放送から、予想されていなかった現象が起こる。
ジャズの流行だ。
それまでは一部の地域のみで演奏されていたジャズ奏者が、一夜にして全国的なスターになるという現象が発生した。ラジオという発明が大衆音楽というカルチャーを生み出したのである。
さらに真空管という発明はラジオだけでなく拡声器やアンプという発明にもつながっていく。それにより政治集会やロックンロールのライブを行うことが可能になり、政治や文化に大きな影響を与えていくことにのるのである。
最後に
以上見てきたように、研究の力が人類の力となったことで私たちの現在の生活がある。
つまり、今の研究の力が人類の力に変われば、それが未来の生活になるわけである。
LabBaseというプラットフォームがこの人類の営みを前に前進させるものになれたら嬉しい。
本記事の内容は
世界をつくった6つの革命の物語 新・人類進化史
という本を参考に記載しています。
とても面白い本なので、興味があればぜひ読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
