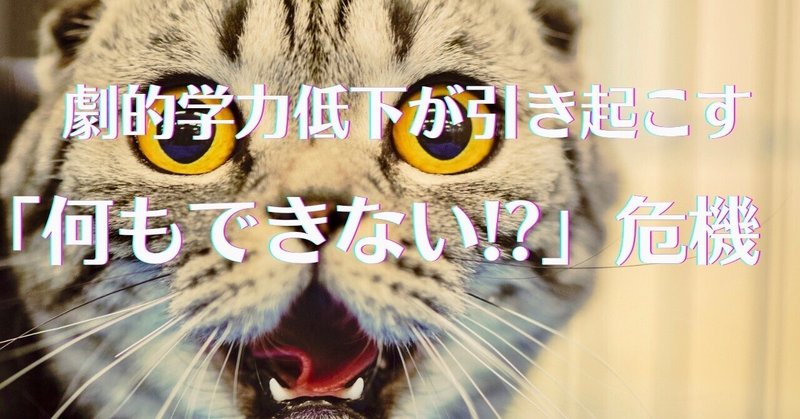
【自分で行う領域で何もできない/学力低下の新たな問題】連投記事その2
連投記事その2
【自分で行う領域で何もできない/学力低下の新たな問題】
さて、学習の次の問いは、現状の学力。
先の記事で、学習では、自ら学ぶ時間が大半を占めるということを書いた。
しかし、ここで現場・現状を見る。
学力は近年、低下の一途を辿ってきた。
このことは、直接、子どもたちの学習指導をされている方で、10年、20年前を知る方なら、すぐにわかることだ。
現場にいても、データを示せとか、そもそもよくわからない人がいるとしたら、それは、一斉講義型指導に慣れ親しんでいて、個々の学力把握ができていないだけのこと。
一斉授業というのは、そのくらい先生の目をぼやけさせるのだ。
話を戻す。
学力低下は、想像していたものを遥かに凌ぐ。
そこで起こることは、かつて想定されなかった事態だ。
それは、
「自ら」行う領域で、そもそも何もできない、
という事態。
日本の小中学課程では留年がないことを考えると、
当該学年で、その内容に全く手が出ない子というのは、これまでも、数%は、いたはずである。
ところが、この数が、今の学力を考えると、半数に近い。
大袈裟かもしれないが、
そのくらいの(段階を追っての)極端な学力低下であることは、現場で見極めがつく方なら同意してくださるだろう。
数パーセントだった時代、その数パーセントに対してできたことは、「できる範囲で、できるところまで、なんとかやろう」ということだったはずだ。
先の記事の通り、個々で先生が対応し、できるだけ、ついて教えるというような形で指導をすると、
時間的に考えても、多くを追えない。
これが、半数近くになった場合、どうだろうか。
半数くらいの子がこうした学力状況の時、
学校ではどうする?
例えば、それだけの人数に対して先生がそれぞれついて指導する?現実的に無理だ。
塾ではどうする?
例えば、家庭教師的1:1指導を選ぶとして、
必要な全教科、全単元を指導してもらう?これも非現実的だ。
時間は足らず、お金も足らない。
そもそも、それだけ一人でずっと付きっきり指導をされて、そのことに耐えられる子など、ほとんどいないだろう。
学力の段階的で極端な低下で、これまでになかった問題が生じたのだ。
まとめると
・学力が低下しすぎたために、自分で行う領域で、何もできない子が多くの%を占めるに至った。
・他人から教えてもらう時間を増やすとしても、時間的、金銭的、精神的問題が大きく現実的ではない。
・果たして、半数近いこれらの層、自分の学習時間に何もできない層に何ができるのか?
このことは、まだ、あまり発見されていない問いでもあるので、ここで先に述べておく。
もちろんここには、何らかの打つ手が必要だ。
(おわり)
本質的な学びの場を
博士や専門家が集う学びの場を
地方のここから。
記事を気に入っていただけると幸いです。NPOまなびデザンラボの活動の支援に活用させていただきます。不登校および発達障害支援、学習支援など、教育を通じたまちづくりを行っています。
