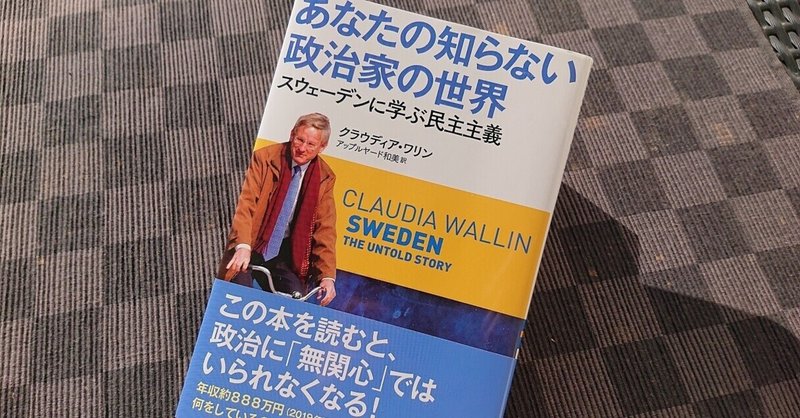
未熟(3の3)【エッセイ】三〇〇〇字(本文)
このエッセイは、(3の2)の続きです。
“政治の話題は避けたい”方にとっては、シンドイ3回シリーズになってしまいましたが、子・孫、いやその先の世代のためかもしれませんが、しっかりと考えたいですね。
次回からは、「暮らしエッセイ」を再開。しかし私にとっては、「暮らし<政治」なのです。
※
スウェーデンのような高社会福祉制度や、政権を厳しくチェックする成熟した政治体制を実現しようとしても、独裁に近い「一強政治」の日本の現状では、無理だ。国会議員の定数を減らすことさえ消極的である現与党が、議員報酬をスウェーデン並みに抑えることなんか、絶対にしない。政府の「隠蔽体質」を批判されても、隠したまま。自分たちに有利な政治構造を維持し続けようとするだろう。そして、「国民は、すぐに忘れる」と馬鹿にされっぱなしだ。
では、絶望するか? 絶望したままでは現状のまま。いや、ますます「後進国」に。より悪化・腐敗することも考えられる。
「じゃ、どうする?」
いまの問題点の原因が、「一強」であることが大きいわけだから、その数を減らしていくしかない。国民の意見に耳を貸さず無視し続けるなら、政権が変わるかもしれないよ。ヘタなことをすれば、政権が変わるかもしれないよ。格差がますます拡がるなら、政権が変わるかもしれないよ、という政治構造にするしかない。国民の30%くらいがその気になれば、5年、10年でもできるかもしれない。その間に、スウェーデンに一歩でも近づく政策を打ち出せる政党を育てること、と思う。
そのことを実現するためには、選挙しかない。しかし日本は、残念ながら「投票しよう」と呼びかけるレベル。投票するのは、基本の「キ」なのだが・・・。
「徳島新聞」電子版(2021/8/2)に興味あることが書かれてある。
スウェーデンから徳島大に留学中のマルムロスさんが気付いたことがあります。「日本人は政府や政治について話さないということ」。スウェーデンでは国政選挙での投票率は80%を超えています。「皆が気軽に政治について話す」と言います。
マルムロスさんがスウェーデンにいたとき、日本人留学生と話す機会がありました。そこで、「投票に行かない」と言うのを聞き、びっくりしたと言います。「スウェーデンではそんなことを公言する人はいない。投票に行かない人もいるけれど、それは人には言わない。恥ずかしいことだから」。もし、そう言う人がいたら、周囲はどんな反応をするかと尋ねると、「そういう人を見たことがないから…」と考え込んでしまいました。簡単に想像できることではないみたいです。
日本では投票率が極めて低いので、「(せめて)投票しようよ」が現実。「投票することが目的」では、「一強体制」を促進させたり、その議員に投じたりするような、逆行することもあり得る。本来は、投票だけでなく、その先について考えなければならない。
「誰に投票して良いかわからない」ともよく聞く。「誰に」ではなく、「どの政党に」なではないか。政党政治なのだから。個人レベルでは、チェックが機能しない。
政権与党と、議席数が接近したチェック役の野党との、政権交代が可能な構造にすることだ。一時期、日本にもあった二大政党制である。国民に約束しておきながら守らなかったり、大きな政策の失敗があったり、決定的な不正があったりした場合には、すぐに政権を交代できるような構造に、である。
民主党政権から安倍政権に移って以来、多くの国民は安定性を求めた。しかし、それは、「不正・腐敗の安定」だったのではないか。もし、いつ交代させられるかわからないような緊張感があったら、貧富格差の拡大、失われた30年の経済の低迷がなかったかもしれない。
「一強の自民」に疑問があっても支持する理由に、「野党がだらしない」「民主党政権の失敗」を理由にあげる人がいる。しかし、そうだろうか、安倍晋三元首相の「暗黒の民主党政権」の口車に乗っているだけではないのか。立憲・共産など野党が上品すぎるのではないか、もっと自分たちがやってきたことを主張しても良いのではないのか。「アンダーコントロール」発言、「118回のウソ」をつきっぱなしのお方を見習えとは言わないが、真面目すぎる。言い換えれば、誠実なひとたちが多いとも言える。
民主党への政権交代が実現された直後の、「2位じゃダメなんでしょうか?」発言の「事業仕分け」。やり方は政権の経験がない分“青っぽさ”があったのは否めないが、国民は当初、注目した(シェキナベイベーの内田裕也も見学に来たくらいに)。民主党にとって大打撃となった「3.11」が、不運だった。自民が進めてきた原発の事故が致命傷だった。尻ぬぐいをさせられたと言ってもいいのに、自民は責任転嫁。新型コロナ”への 対応を見ていると、自民であっても同じ結果だったと、思う。
菅直人元首相が、『民主党政権 未完の日本改革』で、実現したこと、できなかったことを、自省を交えて分析している。子ども手当、介護保険制度の充実、高校無償化、政治主導の諸改革など、現在も引き継がれている(あたかも安倍政権の政策のような喧伝ぶりだった)。必ずしも民主党の全てが失敗とは、言い切れない。
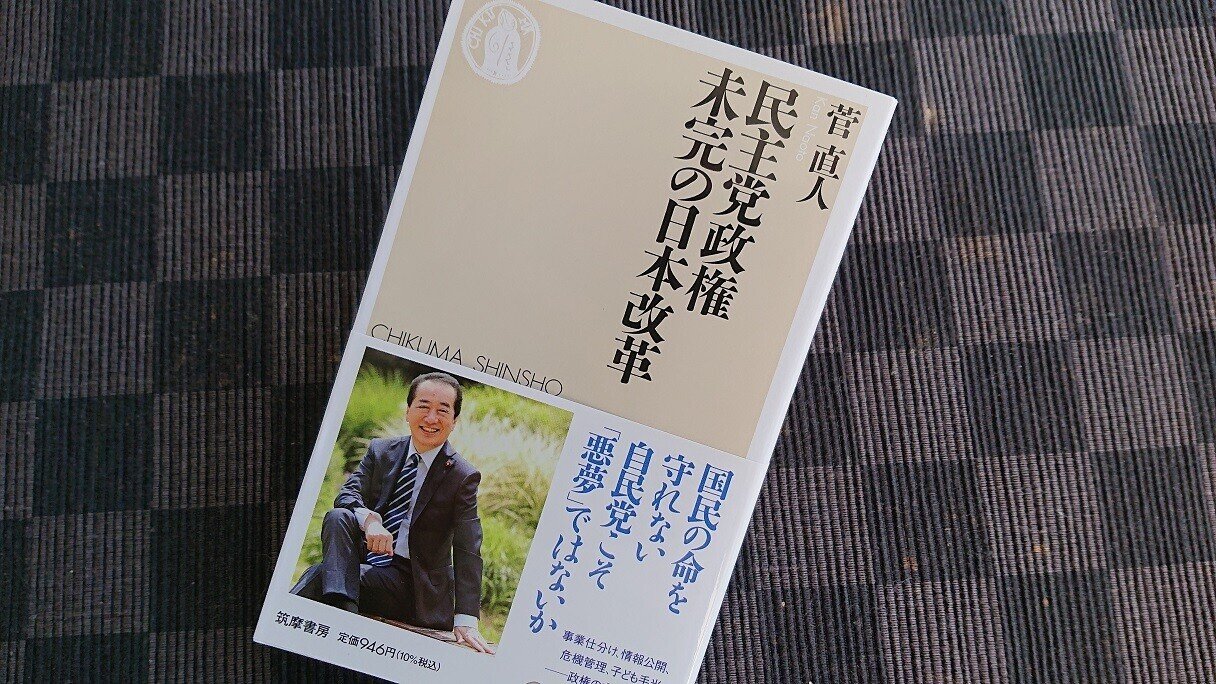
安倍・菅政権の「悪夢の」9年余りが終わり、最初の衆議院選挙。本来の二大政党制が成熟した国家なら、政権交代があって然るべきだった。
「自衛隊日報・モリ・カケ・サクラの公文書の改ざん・破棄・隠蔽」。さらに、「検察法改正案の解釈変更のプロセスの不透明さ」、「コロナ対策連絡会議で議事録が未作成」等々。政権の隠蔽体質が明かになったにも関わらず。結果は自民の絶対多数で終わった。
この透明性に欠く政権を批判する立憲・共産などの野党を、スキャンダルの追及ばかりしていると、行政監視という野党の重要な役割を、政権におもね揶揄してきた維新が躍進するという、皮肉な結果にもなった。立憲は議席を減らし、ますます政権に対峙する政党の存在が薄れてきている。
民主党政権と安倍政権を数値で比較した表がある(詳しくは表をご覧いただきたいと思うが)。目立つ数値をあげれば、安倍元政権がプラスにしたように見えるのは、「株高」と「非正規雇用者数の増加による失業率の低下」。一般庶民が豊かになった数値はない。いやむしろ、下がっている数値の方が多い。
数値で見る民主党政権時代と安倍政権の比較――8分野・78項目
スウェーデンから学び最初にやれることは、「質素な政治家」の考え方と思う。現「一強政党」に対峙する政党は、主張し実行すべきだろう。「議員定数の削減」「議員報酬の大幅な減額」を、まずはアピールしてはどうかと考える。この考えに反対する国民は一部と思う。
日本では、女性や若年層の議員の割合が低い。たぶん、「女や若いヤツは、“青っちょろい”」という考え方が根底にあるのではないか。しかし、“青っちょろい”ことが誠実さにつながるのではないか。むしろ、プロの政治家顔したものたちが、“政治屋”になってきたのではないか。女性と若者の構成比率を高めることは、保守的な政党と一線を画することになると思う。
「“政治屋”はいらない。“青っぽく”てもいい、純粋に政治を考え・行動する誠実なひとを国会に送ろう」
スウェーデンとは、風土も歴史も異なるが、これなら日本でもできることだ。まずは、望まなければ実現しない。
いま日本の政治をスウェーデンに一歩でも近づけるために、まずは、不正をチェックできる仕組み、不正すれば交代があり得るという緊張ある政治構造にすべきではないか。だから、「どこに投票して良いかわからない」人への回答は、「まずは、チェック役になり得る政党へ」と言いたい。「スウェーデン」を学べば学ぶほど、日本の「未熟」さが透けて見えてくる。
スウェーデンの「幸福度」は、天から自然に舞い降りてきたのではなく、国民の行動から生まれたことを最後に記しておく。
トータル8千字を超える長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
(紹介)
Note仲間の更科いつきさん、政治問題について鋭く指摘するコラムを書いていらっしゃっております。29日にアップされたのが、「アベノミクス」の検証記事です。関連するので紹介させていただきます。
(付録)
(3の1)のコメント欄に、note仲間のアルプ・スナフキン氏が、こう書いている。
理想は国会議員も総理大臣も、町内会のような輪番制。
「ああ、今年は当番が回って来ちゃったよ。だけど皆やってんだから俺も仕方ねえから1年間だけ真面目にやっかなぁ…💦」みたいな(笑)
だけど、これが究極の「当事者意識」ってやつでしょ?
スウェーデンは案外近いところまで行ってるのが素晴らしいところです。文化や歴史を論議したって永遠の泥沼にはまるだけだけど、日本だって町内会組織はそうできてんるだから案外可能かもね。
もし、こうなったとしたら、国民の多くが政治について勉強しようと思うだろう。確かに、これが「当事者意識」なのかもしれない。
そもそも、民主主義の原点は、アテナイの市民(男中心であったが)による直接民主制であったと言われる。
(付記)
スウェーデンでは、最近大きな動きがあった。
マグダレナ・アンデション首相は、人道的な「移民・難民の受け入れ」に積極的であったが、世界的な反動潮流となっている自国第一主義を主張する超右派政党に負け、退陣を表明した。今後のスウェーデンがどう変わっていくか、注視したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
