
健康な体作りに欠かせない5大栄養素とは
こんにちは。河本将弘でございます。
あなたは普段、バランスの良い食事を摂る事が出来ておりますでしょうか?
食事の基本は朝昼晩の3食で5大栄養素をバランス良く摂る事が鉄則ですが、殆どの方は頭では分かっているものの、それぞれの栄養素にどういう役割があるのか正しく理解しきれておらず、偏った食事になっているかと思います。
そこで本日は、健康な体作りに欠かせない5大栄養素について解説をしていきますので、食生活を改善してより健康な体を目指したいあなたにお読みいただきたいです。
理想的な食事の構成と5大栄養素

5大栄養素とは、食品そのものに含まれる栄養素を体への働きごとにグループ分けしたものであり、炭水化物、たんぱく質、脂質、ミネラル、ビタミンの5つに分かれています。
そして理想的な食事の構成としては、主食(炭水化物)、主菜(たんぱく質、脂質)、副菜(ビタミン、ミネラル)、汁物(水分)の組み合わせが理想とされています。
5大栄養素のそれぞれの特徴
炭水化物(糖質+食物繊維):1g=4kcal

体や脳を動かす即効性の高いエネルギー源となる栄養素で、不足すると脳に必要な栄養素が届かなくなり、足りないエネルギーを補う為に筋肉や脂肪が分解され、逆に糖質を過剰に摂取してしまうと、エネルギーとして使われずに余り、中性脂肪に変換されて脂肪となってしまいます。
糖質をエネルギーに変えるにはビタミンB1が必要で、豚肉やレバーのようなビタミンB1が豊富に含まれている食品と組み合わせて食べる事で代謝が高まります。
炭水化物を多く含む食品としては、米、小麦、いも類、とうもろこしなどです。
たんぱく質:1g=4kcal

筋肉、皮膚、臓器、脳の神経伝達などの体を作る源となる栄養素で、体内ではアミノ酸となり、これが細胞の基本成分であり、遺伝子情報のDNAもアミ
ノ酸から作られる。
食品中に必須アミノ酸が1つでも不足していると、タンパク質としての栄養的価値が下がるので、食品中のたんぱく質の品質を評価するための指標にアミノ酸スコア(食品中の必須 アミノ酸の配合バランスを点数化したもの)があり、この点数が100に近いほど良質なたんぱく質となる。
たんぱく質を多く含む食品としては、肉、魚、卵、乳製品、大豆などです。
脂質:1g=9kcal

エネルギー源として使われたり、細胞膜や臓器、神経などの構成成分、ビタミンの運搬を助ける栄養素で、その他、体温を保ったり、肌に潤いを与えたり、正常なホルモンの働きを助ける働きがあります。
その為、脂肪摂取を減らしすぎると様々な体の機能が低下するが、摂取量が
多すぎると脂肪として蓄えられ、肥満の原因となります。
脂質を多く含む食品としては、肉や魚の脂身、ナッツ類、乳製品、食用油などです。
ビタミン

上記3大栄養素の代謝を助け、体の機能を活性化させる栄養素で、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分けらるが、ビタミンは体内でほとんど作れないため食品から摂取する必要があります。
水溶性ビタミンは血液などの体液に溶け込んで、余分なものは尿として排
出される。代謝に必要な酵素の働きを補い、脂溶性ビタミンは水に溶けない性質があり脂肪組織や肝臓に貯蔵されます。
身体の機能を正常に保つ働きをするが、摂りすぎると過剰症を起こすことがあります。
ビタミンを多く含む食品としては、野菜、果物、レバー、豚肉などです。
ミネラル

酸素やホルモンの働きを助け、歯や骨の成分となる栄養素で無機質とも呼ばれています。
ミネラルも体内で合成できないため食物として摂る必要があり、不足した場合は欠乏症やさまざまな不調が発生するが、摂りすぎた場合にも過剰症や中毒を起こすことがあります。
ミネラルを多く含む食品としては、海草類、魚介類、乳製品、レバーなどです。
あとがき
それぞれの栄養素には体を健康に保つための重要な役割がありますが、どれかが極端に不足したり、偏った摂取をしていると体調不良が起こりやすくなり、それが続くと将来がんや糖尿病などの生活習慣病に罹りやすくなりますので、先ずは上記で紹介した食品をまんべんなく適量を摂る事から始めてください。
それでも普段から食事が偏っていて、どこから改善して良いか分からない場合は私までご連絡いただければ、あなたの健康に関しての悩みをお聞きした上で正しい食事についてアドバイスを差し上げる事も可能です。
本日はご覧いただきありがとうございました!
今後もプーケットや健康に関してのトピックを定期的に発信していきますので、河本将弘公式LINEにご登録いただけると幸いです。
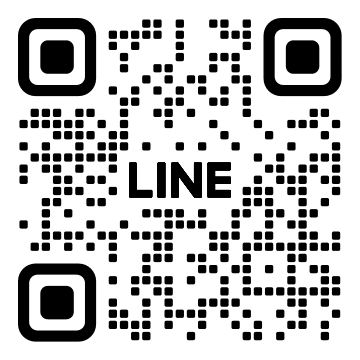
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
