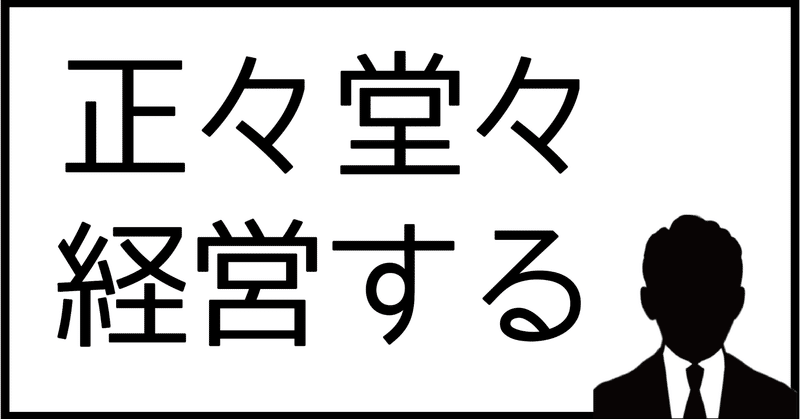
正々堂々とした経営をする
「正直者は損をする」という風潮が強くなってきた気がする。
ブラックとグレーの境目を器用に立ち回れば、得をするかもしれない。
しかし、それは一時的なことであり、結果としては「正々堂々」とした経営をする人が生き残る。
今回はこの辺りについて書き綴っていく。
助成金依存と使途偽装
助成金が大好きな経営者がいる。
そういった人は、何かの助成金制度がはじまる度に助成金の申請をする。
もちろん、正々堂々と助成金をもらうなら全く問題はない。
しかし、よく見るのは以下の2例。
1.助成金のために不要な事業活動をする(無駄遣い)
2.申請とは異なることへ金を使う(使途偽装)
最近は、助成金申請が大好きなコンサルタントとの組み合わせが加速している。
まず、無駄遣い。
これは、助成金の無駄遣いでもあり、時間の無駄遣いでもある。
例えば、大きい助成金だと、無謀な店舗経営をはじめる人もいる。
殆どの場合、すぐに終わる。
喜んでいるのは、コンサルと建築業者だけ。
助成金を出す国からしたら、消費が循環して金が回ることに変わりはないのかもしれない。
しかし、できれば「納税」という形で国へ利益を還元して欲しいところ。
助成金の申請が仕事になっている経営者もいる。
新しい助成金を申請する度に、他の仕事を止めて、助成金申請に労働時間を投入する。
その時間は、助成金の額に見合ったものなのか?
次に、使途偽装。
業者と結託して、助成金の使途を偽装するというもの。
これは、完全にブラックなのだが、普通にやっている人が多い。
その行為は、自らのプライドを傷つけないものなのか?
出し抜き、売り逃げ
人を出し抜いて商品を売り、売ったら逃げる人がいる。
過去に記事を書いたので、こちらを参照して欲しい。
上場企業であっても、出し抜き、売り逃げが増えてきた。
特に、急成長して一気に上場するタイプの企業は、高確率でこのタイプだ。
こういった上場企業を見ると、それに見習った方が得するように思えるかもしれない。
しかし、そういった企業は、衰退も早い。
相性が良いのは、会社をイグジットして売り逃げようとする経営者であって、「100年続く企業」を目指す経営者向けではない。
報酬削減
これが一番深い。
社内給与であっても、仕入や外注の費用であっても同じだ。
――― 適正な報酬とはいくらか?
これが難しい。
経営者の悩みどころだと思う。
まず社内給与については、以前に書いた記事を参照して欲しい。
今回は、仕入や外注といった業者としての話を書き綴る。
まず、過度な価格交渉や値引き要求はやめた方が良い。
薄利多売を目指す大手企業の真似をしてはいけない。
そもそも、一定以上の値引きの代償は「手抜き」となって表れる。
表面上は整えられたモノが納品されたとしても、中身は分からない。
業者も一つの会社であり、経営を成り立たせるためには、これを絶対に避けられない。
結果、最後には発注者を苦しめる。
ニュースとして取り上げられる「外注先の不祥事」というもの。
かなりの確率で何かしらの「無茶」が依頼されている可能性が高い。
「金」は、その中で一番分かりやすいものだと思う。
そもそも、私は「値下げ要求」という行為自体をしないようにしている。
業者から届く見積は、業者がしっかりと仕事をするための経費、さらに満足する利益を乗せてある。
これは、真剣に検討した結果、積算された見積金額のはずだ。
そもそも、軽い気持ちで見積を出してくる業者とは付き合わない方が良い。
見積が届いたら、まずは内容をしっかりと確認する。
そして、高いと思うなら、断る。
妥当だと思うなら、依頼する。
安いと思うなら、念入りに内容(品質)を再確認する。
本来、契約というのは、こうやって決めるものだと思う。
値下げ要求をした時点で、見積内容に変化はなくても、中身は変わっていると思った方が良い。
労働者への転嫁
先日、まっちゃん氏がこんな記事を書いていた。
ぜひ読んで見て欲しい。
日本では、個人が直接納税する機会は殆どない。
勤務先の企業が納税を肩代わりするからだ。
消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税などいった税金も個人が直接納税するわけではない。
その結果、税金、年金、保険などに対する知識が足らない人が多いと思う。
学校で「直接税」と習った税金ですら「各個人が直接納税する」というルールになったら、今の日本は税金の回収不能が続出し、3年以内に崩壊する。
大袈裟ではなく、本当にそのくらいの状況だ。
ただ、これは「素晴らしい仕組み」ゆえの無知から来るもの。
それを逆手にとった行動をする経営者がいる。
・社会保険をやらない
・社員を個人事業主にする
・給与明細の額面を偽装する
・従業員から徴収した費用を納付していない
――― 他にも挙げれば、まだまだある
できれば、会社の経営は2年、3年のスパンではなく、20年、30年のスパンで考えて欲しいと思う。
一過性の犠牲的な利益ではなく、周囲が納得した継続性のある利益を目指すべきだ。
そうすれば、自然と「正々堂々」とした経営になると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
