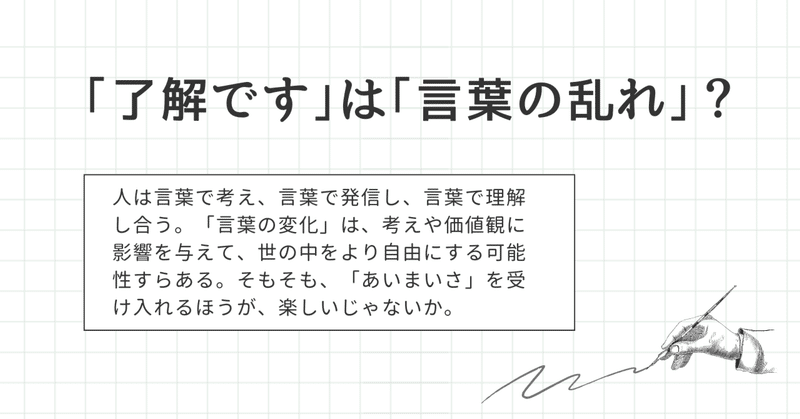
「了解です」は「言葉の乱れ」?
上司や先輩に「ご苦労様です」ではなく「お疲れ様です」と、使い分けている人は多い。ところが……
「了解です」ではなく、「承知しました」と答える人は少ない気がする。「了解です」と言う人の中には、「OKです」と答えるところを「ていねいに話している」と思っている人もいて、違和感が拭えない。
とはいえ……
「言葉の変化」を、「言葉の乱れ」と嘆きたくはない。それでは「今どきの若い奴は」なんて、ぼやくオヤジと変わらない。そんなの、イヤだ。
かといって……
「時代の流れ」や「環境の変化」だの「自分とは関係ない話」を持ち出して、当然な顔で「仕方ないんだ」と言うのも悔しいじゃないか。
じゃあ、どうすればいいんだ……
「了解」の「本来の意味」から言えば、ぼくの違和感に根拠がないわけでもない。しかし「適当」や「全然」など、「本来の意味」から離れた使い方が一般的になっている言葉は意外と多い。
「本来の意味」から「離れる」のではなく、「広がる」と考えてみたらどうだろうか。本来は誤用だけど新しい用法も無視しない。そんな「あいまいさ」を受け入れる発想だ。
人は言葉で考え、言葉で発信し、言葉で理解し合う。
「言葉の変化」は、考えや価値観に影響を与えて、世の中をより自由にする可能性すらある。そもそも、「あいまいさ」を受け入れるほうが、楽しいじゃないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

