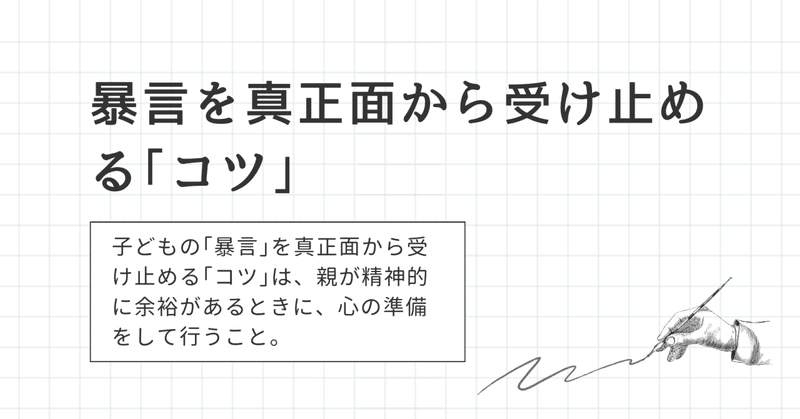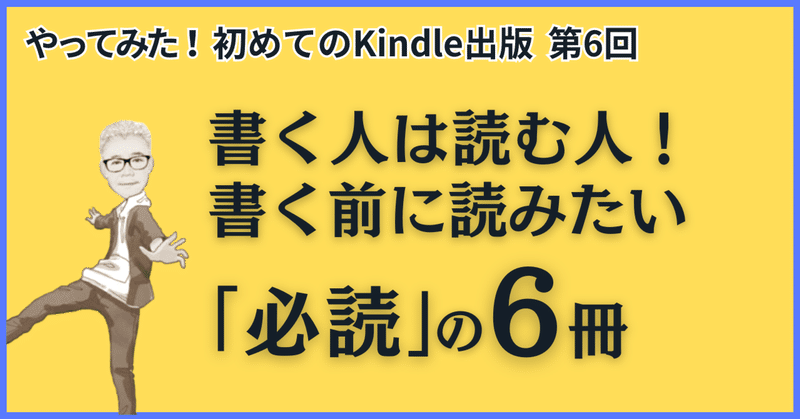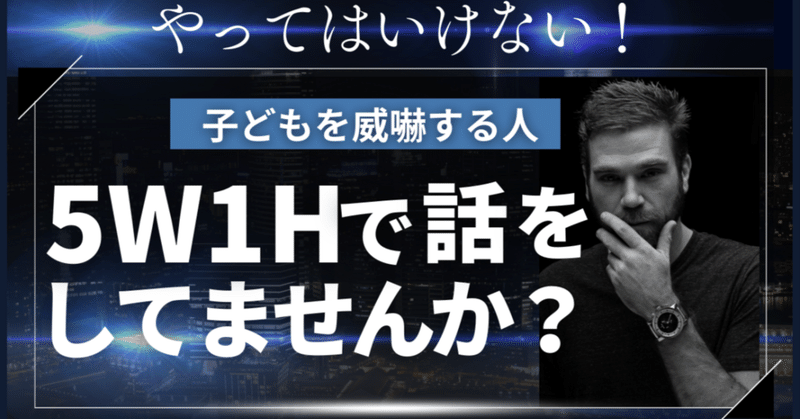記事一覧
暴言を真正面から受け止める「コツ」
子どもの「暴言」を真正面から受け止める「コツ」は、親が精神的に余裕があるときに、心の準備をして行うこと。
反抗期の「暴言」に毎回、まともに取り合うことなど、現実にはできない。
とはいえ、暴言を真正面から受け止めて冷静に問いただすことがあってもいい。
大切なのは「今なら言える」というタイミングを判断すること。親が「カッとなったとき」にやると失敗する。
「ちょっと待って、たいていのことには目を
子どもを威嚇する5W1Hの「話し方」
5W1Hを押さえたコミュニケーションによって、過不足のない情報伝達を実現できます……これは「5W1H」で検索したときに、トップに表示されたサイトの「説明」だ。
だけど、説明を信じてバカ正直に実行したら、家庭で居場所がなくなるのは間違いない。
そもそもコミュニケーションは、「猿の毛づくろい」に似ている。実際のスキンシップがなくても、心がふれあった「実感」があればいい。
コミュニケーションに「過