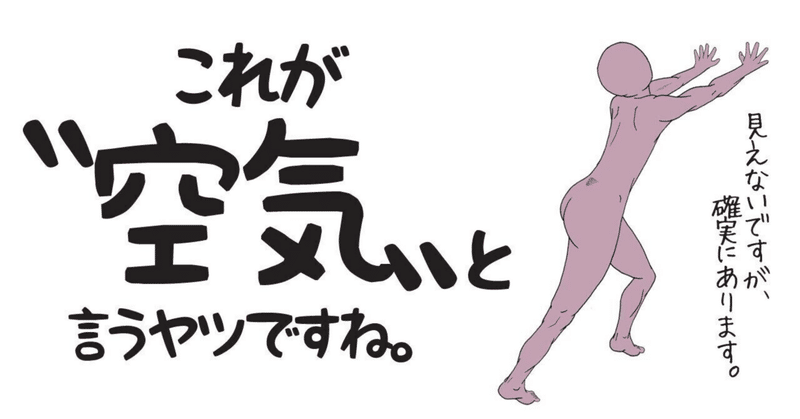
複業人材の壁は既存社員?
日本共通の課題である人口減少。人口減少が進む事で生産する人、消費する人ともに減少していき、かつ、東京一極集中のなか、地域の持続性は難しくなっていく。そのため、地方創生をテーマにし、関係人口の増加、移住定住支援、ワーケーションなど、コロナを経た働き方意識の変化もあいまって、働き手確保に向けた施策が各道府県では盛んになっています。
足下では、人手不足倒産による倒産が昨年より8割増加し、特に中小企業ではその影響が目に見えて現れてくるようになりました。
今日は働く人を増やす方法の一つである複業についての記事。
副業解禁から5年
日本国内で副業が解禁されて、すでに5年。副業を認める企業の割合は増加(約半数)しているが、正社員の副業実施率は1割未満、横ばいもしくは減少傾向にすらあります。
※あくまで大企業中心で構成された経団連会員企業向け調査の結果
パーソルイノベーション株式会社が2022年に行った調査を見てみると、中小企業の認可は約3割、スタートアップは7割と、企業規模により考え方が異なる事がわかります。
受け入れ側を見てみると慎重な企業が多く、受け皿が足りない。副業経験を本業に活かすという理想には程遠い状況。
受け入れ側のメリット
※ここからは私の考えです。
副業人材を活用する場所は、自社にとっての新規事業(もしくは社内にとっての新たなチャレンジ)ではないかと。そもそもリスクが高い新規事業に中途社員もなかなか希望の人材が現れない、新入社員を雇っても育成に最低3年はかかる。と社内に人材がいない。副業人材であれば、ジョブ型雇用に近いので、社内の新規PJT領域で力を借り、うまく波に乗れば継続、難しそうならばリソースごと撤退できる。言い方がダイレクトすぎるが、失敗時の切り離しが容易なのは大きなメリットだと思います。副業人材側からしてもダラダラと成果の上がらないところで時間を割くよりも次!と切り替えやすいのではないでしょうか。
二つ目のメリットは、やはり社内にはない文化や視点、視座を社内に落とす事ができる。特に管理職のプロパー社員の割合が多い場合は、硬質化しており、現状維持か社内にフォーカスを当てた改善活動が活発になるが、その進化は微々たるもの。意見が同質的になり、イノベーションが起きにくい。例えば、2021年のコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の改定においては、「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」について記され、中核となる人材の多様化を求めています。
副業人材活躍の壁
※私の仮説です。
そもそも家族経営の形が多い中小企業においては、副業人材という一般社員と同等の役職で社長が連れてきた人間と一緒に仕事をすることにおいて、悲しいかな、要は部外者と見なされ、家族に入れてもらえない、もしくは慣れるまでに相当の時間を要するのではないでしょうか。特に、関連部門長や部署長にプロパーが多い場合、その壁はかなり高い事も予想されます。なので、完全外部の人間として見られる『コンサルティング』と呼ばれる人が中小企業に1人いる場合が多いですね。最初からそもそもの認識が違うので、副業人材が家族なら、コンサルは『先生』のような感じでしょうか。同質性が高い企業が多いからこそ、副業人材の壁は至る所に発生していると思います。
副業人材を取り入れる最初のポイント
やはり、社内のプロパー社員に納得してもらうのが手っ取り早いですね。なぜ我が社において副業人材を取り入れなければならないのか。その先に向かう未来は何があるのか。を副業人材を探し始める前に、関連部門長、部署長を巻き込んだ戦略作成を通じて、同時に社内の受け入れ体制を考えていく。副業はあくまで戦術と捉えいただき、その先に目指す姿で合意形成をする。この時、撤退を考える時期と判断基準も同時に作っておくと良いと思います。
人口減少で何が起こるのか
人口減少は日本の大きな課題です。すでに2100年には、8,000万人の国家が予想されています。
日本の中小企業数は、2040年予測で295万社、対して、2022年生まれは77万人。恐ろしいほどの売り手市場、新卒採用の激化が予想されます。
時代に合わせた事業展開をしている企業は学生から魅力的に見え、首都圏の大手に確保されていきます。人がいなければ、消費も労働も回らない。稼げない地域は福祉も社会保障も低くなっていく。
人口減少の本当の影響にぶつかるのは、今中間管理職や若手社員の皆さんかもしれません。
※多分、今の50代くらいはそこまで体感せずに年齢的に退職されていきます。
副業人材の活用を任せっきりにせず、できれば議論に入ってみてください。
お読みいただきありがとうございました!
知見、経験のある方のコメントお待ちしております!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
