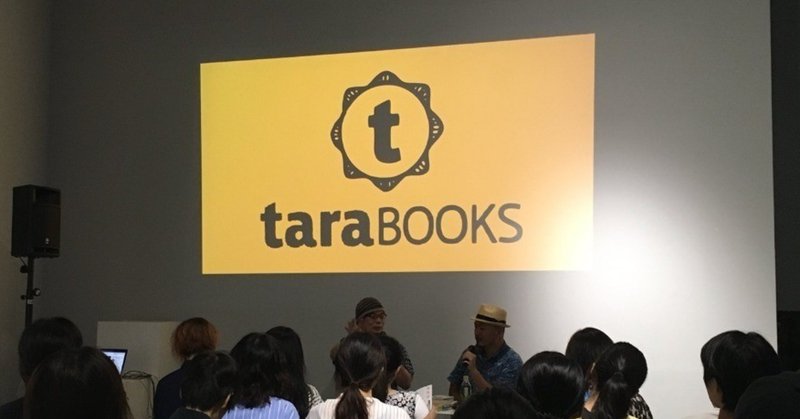
主催者レポート!【インドと京都、時々東京。異色の装丁家の暮らしと仕事とタラブックス】稀人アカデミアvol.6
昨日、稀人アカデミアvol.6 【インドと京都、時々東京。異色の装丁家の暮らしと仕事とタラブックス】開催しました。中学生含む計28名の方にご参加いただきました!
稀人アカデミアとは?⇒稀人アカデミアの1年。名もなき物書きが始めたトークイベントの顛末。
今回は小学生の時から不登校、中学1年で「退学」し、14歳の時にインドに渡った異色の装丁家、矢萩多聞さんがゲスト。トークの前半は、多聞さんの「明るい不登校児」時代から約500冊の書籍の装丁を手掛ける売れっ子装丁家になるまでの足跡がテーマだった。
多聞さんの話を聞いていて感じたのは、不登校を否定せず、インドに行きたいという普通に考えれば無茶な願いを聞き入れたご家族の存在の大きさ。もともとユニークなご家族なんだけど、ポイントはそのユニークさではなくて、息子を全面的に支える、無条件に信じるという絶対的な愛によって、今の多聞さんが育まれたのだと思う。
もうひとつ、学校教育のなかで幼いころから大好きだった絵を描くことがつまらなくなり始めた時、インドのミティラー画の作家と出会ったことも転機になったと感じた。作家の「出来上がりではなく、描く過程を楽しむ」という姿勢が、「枠」にはめられそうになってもがいていた多聞さんを解放したのだろう。

20歳から現在に至る装丁家としての道のりも、さまざまな出会いが道しるべになっていた。インドでは、「暇な人がたくさんいるから」いつも誰かに話しかけられるという。14歳から多感な時期をその環境で過ごしたことで、恐らく多聞さんは人間という存在に対して警戒心よりも先に好奇心を抱くようになった。
もちろん、多聞さんの感性や仕事への姿勢が前提だけど、日本人には珍しいそのオープンなマインドが多くの出会いを呼び寄せ、「一度も営業をしたことがない」のに500冊もの装丁を手掛けることにつながったのだろうと思った。
後半は、職人による手作りの絵本が世界で人気となり、「奇跡の出版社」とも呼ばれるインドの独立系出版社タラブックスと、最近、2ヵ月を過ごしたインドのお話。

タラブックスの絵本
インドの書店でタラブックスの絵本と出会い、買い集めるようになったという多聞さん。今では、日本におけるタラブックスの伝道師のような存在になり、昨年、日本で大規模な展示があった時にも大きな役割を担った。多聞さんがスライドで見せてくれたタラブックスのオフィスはおしゃれで、先進的で、居心地がよさそうだった。

インドといえば発展途上国というイメージもあるけど、日本の出版社でタラブックスと比肩するようなオフィスを持つところはほとんどないのではないだろうか。この環境だからこそ、アート作品のようなタラブックスの素敵な絵本が生まれるのだろう。狭苦しい、息が詰まりそうなオフィスでは、まず無理に違いない。
多聞さんの話で印象的だったのは、世界中から注文が入っていてもあえて規模を拡大しないこと。現在は20人の職人が1ヵ月で1000部ほど刷っている。それを40人にすれば2000部になるのだが、いやいや今のペース、今の人数でいいじゃないかと。大きな工房でシステマティックにやるのはなんか違うよねと。そういう姿勢がむしろ好感を得ているから、タラブックスを求める人たちは、何カ月でも待つのであった。
2ヵ月のインド滞在については、インドで神輿を担いだという話から福井の「紙の神様」を祀る神社でも神輿を担いだという話になり、またインドで450年続く人形劇団を訪ねたら弟子入りしたくなったという話になり、僕は多聞さんの腰の軽さ、そして改めて日本人離れしたオープンマインドを感じた。
そうそう、最初はいち読者、いちファンに過ぎなかったタラブックスとも関係が深まり、9月に発売される『つなみ』という絵本では、多聞さんがデザインを担当したそう。この話からも、一見、仕事とは無関係に見える出会いや体験全てが巡り廻って、多聞さんの仕事に脈打っているのだと感じたのであった。

イベント後、参加者の感想を読んでいたら、胸を打つコメントがあった。どなたか特定されてはいけないので詳細は書かないけど、問題を抱えているご自身の子どもに対して「(多聞さんの話を聞いて)元気でいてくれればいいやと思うことができました」とあった。このコメントだけで、多聞さんとこの回を開催してよかったなと心底思った。

多聞さん(中央)、初回から稀人アカデミアを協力サポートしてくれているコンセントの千々和さん(右)と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
