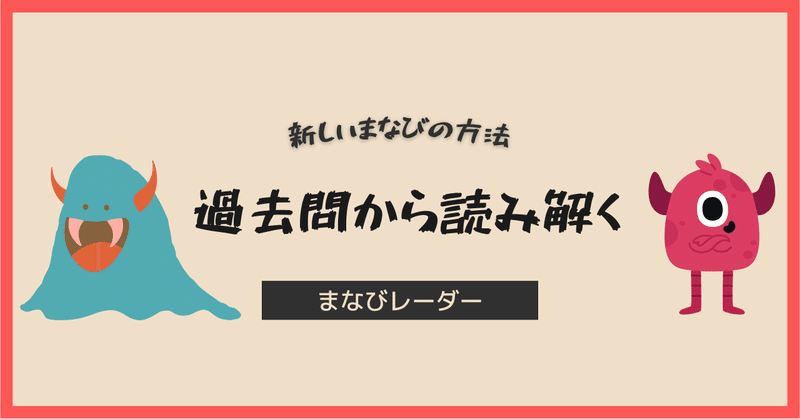
過去問対策の心構え
適切なタイミングでの志望校対策
受験勉強をすると、志望校対策をしなければなりません。そのタイミングはいつでしょうか。それは受験開始時期からです。「すべての単元が習い終わる小6からでは」と思う方もいるでしょう。それも一理ですが、準備は早ければ早いほどいいに越したことはありません。
小学校低学年での準備と対策
小学校低学年で準備ができるものがあれば、その準備をするべきです。たとえば、女子学院の問題は早い処理能力が求められます。だとしたら、早く計算する、早く図や表を書くなどの訓練が必要です。そして、これらの練習は小4からでもできるでしょう。
また、難解な図形問題が出題されるのなら、図形に慣れるようなパズル問題や、コンセプトを理解できるような学習をすべきです。大手集団塾では、受験範囲を全部勉強するためのカリキュラム消化が最優先です。そのため受験には直接出ないが重要な内容や、基礎すぎる内容だが反復して習得しなければならないものに時間をかけれらません。そのため難解な図形問題を解くことができないのです。しかし、これらの内容は、ごくごく基礎的なものですので、実は小4からでも勉強はできます。
規則性の問題なら、ごくごく初歩的な規則を見つける問題、そしてその規則を延長していく問題を練習する小学校低学年向きの教材も市販されています。これらで早めの対策をするのがいいでしょう。
過去問分析の重要性
このように小学校低学年でも、難関校の対策は始められますよね。そのためには過去問分析が重要です。
方法は、最低10年分の過去問を分析します。出題分野を分析することはもちろんです。そして、その分野の裏にある学校の考えを見抜いていきます。学校は、受験問題で「私たちの学校が欲しい生徒の種類はこうだ」と宣言しているわけです。たとえば、「生徒を東大に合格させます」と宣言する学校は、東大の問題を解ける能力がある生徒を合格させます。だとしたら、出題予測をするときに東大の問題分析も必要となります。他にも、渋谷教育学園渋谷などは、模擬国連への参加を重要視します。それなら、受験問題も模擬国連から逆算して出題します。
過去問分析では、合格得点の配分も重要です。合格するため、どのように点数を取るかを設定します。そうすると、どのような問題を解き、どのような問題を捨てるのかも決まってきます。そして、必ず解かなければならない問題の基礎を小学校低学年でやっておけば、実際に塾で本格的に勉強したときに「もう一度やってるな」と思えるわけです。
解法にも注意を
ここで重要なのは、問題の解法についてです。
問題も解ければいいのではありません。
難問を解けるような解法があります。
その解法も、低学年のうちから練習しておくことをおすすめします。
よくあることが、小学校低学年・中学年で使用していた解法と、高学年で習う解法がちがうことです。
これは、車の右ハンドルと左ハンドルの違いのようなものです。
似てますが、歴然と違います。
そして、似ているからこそ、混乱したりもします。
だとしたら、早めの筋のいい解法を習得するべきです。
これらのことを含め、過去問対策をしていきましょう。
最後まで読んでくださり、誠にありがとうございます! サポートも嬉しいですが、「スキ」ボタンや「コメント」が励みになります。 ぜひとも、よろしくお願いします!
