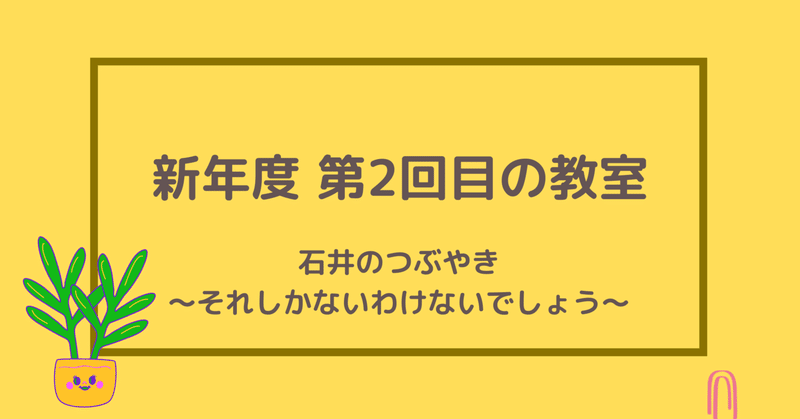
『それしかないわけないでしょう』子どもたちに語るべきこと✎by石井
みなさん、こんにちは!
マナビファクトリー代表の石井です。

新年度になり、別れの季節と出会いの季節の節目ですね。
教室には昨年度は卒業学年の生徒はおらず、
新規の生徒さんが月に2~3名ぐらいで加わっています。
教室にただ一人の小学生の男の子は、漢字がとても好きで、
宿題を終えて時間が余ったらひたすら漢字練習をしています。
中学生たちは、2年生と3年生なので、そろそろ進路のことも考え始め、
少しずつ内申点を意識し出しています。
高校3年生たちは、ついに本格的に受験年度生となり、
月単位で計画を立てている真っ最中です。

3月までは半数近くが学生だったマナビファクトリーのスタッフたち、
4月からこれで大半が社会人になりました。
忙しいながらも、それでも活動に参加してくれているスタッフたちに、
本当に感謝しかありません!
さて、私個人も新年度を迎え、実は大きな変化がありました。
昨年度いっぱいで正社員として働いていた学習支援系NPO法人を離れ(マナビファクトリーではないですよ)、
非常勤職員として働いていた小学生の放課後居場所支援の社会福祉法人を離れ、
学習支援&居場所支援はこのマナビファクトリーでの活動に専念しつつ、
生活の基盤を整えるためにこの4月から一般企業に転職しました(何せマナビファクトリーは無料塾ですので私の生活は守れませんので笑)。
人生初めて一般企業(しかも教育業界ではない)への転職…
学校法人や、NPO法人という特殊な業界で計12年働いてきましたが、
新しい自分の可能性を見出せそうでワクワクしております(^^)
自分の「想い」にとらわれること
~それしかないわけないでしょう~
私と息子が大好きな絵本作家さんに、
ヨシタケシンスケさんという方がいます。
その方が描いた「それしかないわけないでしょう」という絵本があるのですが、
これがなかなか大人が読んでも響く内容でして。
主な登場人物は女の子とおばあちゃん。
ある日、女の子はお兄ちゃんに「自分たちが大人になるころには大変なことしかない」と言われ、
意気消沈してしまいます。
ところが女の子がおばあちゃんにその話をすると「だーいじょうぶよ!」と、おばあちゃんは満面の笑みを返すのでした。
未来がどうなるかは誰にもわからないし、大変なことだけじゃなくて楽しいこともたくさんあるのだと。
「これとこれどっちにする?」と大人は言うけれど、選択肢はそれだけではないのだと。
「それしかないわけないでしょう」と。
その話を聞いた女の子は、ユーモアたっぷりにいろいろな未来を思い巡らせて…というようなお話です。

皆さん、自身を「こういう人間だ」とか、
自分の人生を「こんなもんだろう」と決めつけてしまうことって、ありませんか?
私はよくあります笑。
私は高校に入るまでは、ものすごーーーく勉強が苦手で、平気で「1」を取ってしまうような子どもでした。
「自分はどうせ勉強とは縁のない人生を生きるから」「方程式とか三単現とか一生使わないし」みたいな、
まあ、子どもが勉強から逃げる時の言い訳ワードはひと通り言ってきたつもりです。
そんな私に「勉強って面白い」と思う時代が訪れ、
勉強をするようになって一浪を経て大学に行き、
アルバイト代に惹かれたという単純な動機で塾講師のアルバイトをし、
やがて高校教師になり、その後は学習支援のNPO法人に勤めて、
そして自分で仲間たちと学習支援の団体を立ち上げて…こんな人生、だれが想像したでしょう?
私は私を「勉強をしない人」「どうせわからない人」と勝手に定義づけていました。
その結果、かなり遅れて「勉強」というものに出会うことになりました。
また、今回の転職活動もそうでした、
自分自身を「教育に関する仕事をしてきた人」と定義づけて、その軸だけで仕事を探していました。
順調に選考が進んでもどこかしっくりこず、自分がなぜ教育に関する仕事をしてきたのかを考えた末、
「あ、そうか、自分は結局、人の役に立てる自分が好きなんだ」ということに気づきました。
原点ですね。
私は、どのようなジャンルであっても「人の役に立てる仕事」・「そこに対して自分の強みを発揮できる仕事」ならば、
正直、何でもよかったんです(^^;
もちろん、理念も含めて納得感を感じられる仕事であることは大前提ですがね。

生徒たちとかかわるときに、
「どうせ」「自分は○○が嫌いだから」「△△は一生使わないし」…
というようなフレーズを本当によく耳にします。
おいおい、昔の自分かよ…と思いつつ、あまり笑えないんですよね。
なぜなら、私は大人になっても「自分は教育関係の仕事しか向いていないんだ」と思い込んでいたわけですから。
大人も子どもも、自分を定義づけてしまうことって、本当によくあると思うんですね。
うまくいかなかったことがわずかにでもあると、回避したい本能で「そのこと」に近づかなくなったり。
うまくいかない → 回避の積み重ねで、自分の可能性をどんどん狭めていってしまう…。
自己肯定感の低い子たちならば、なおさらその傾向は強いです。
そのような想いに縛られている子どもたちに、私たち大人はまず何をすべきなのでしょうか。
自分を決めつけてしまっている想いを一旦は受け止めてあげつつも、
その言葉を「キャンセル」してあげられる大人たちが必要ではないでしょうか。
「そうじゃないよ」「そんなことないよ」「それしかないわけないでしょう」と。
もちろん、いつでも楽観的にいればいいというものでもないとは思います。
重くとらえねばならない問題、たくさんあります。
マナビファクトリーの活動も「大変な課題」が世の中にあるからこそ始まったわけですから。
ですが、私たちは真剣ではあっても、陰気ではないようにすることが大切だと思います。
使命感は大事、でも悲壮感はいりません。
皆さんは、子どもたちに何を語りたいですか?
私は、希望を語れる大人でありたいと思います(^^)
子どもたちにとっての未来である、今この大人としての日々も、大いに楽しんでいきつつ!
子どもたちと、若いスタッフたちのことを、引き続き応援よろしくお願いします!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
