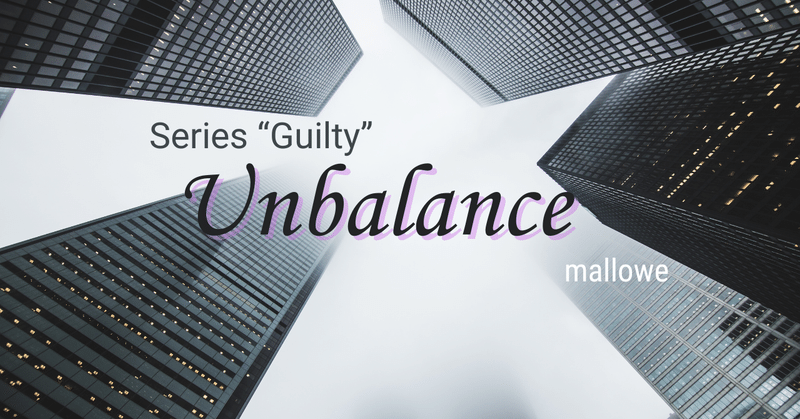
【シリーズ連載・Guilty】Unbalance #2
上がった息で彼の美しい胸が上下している。指先で触れるとしっとりと吸い付くようだ。私の身体の芯もまだじんわりと熱く、深い余韻が残っている。
やがて微睡が訪れる…彼の首筋に鼻を寄せて瞼を閉じ、ほんの束の間、目を閉じる。
それは本当に小さな、細やかな幸福の時間だった。私は頭の中で彼と夫を比べている。
背徳は全てにおいて優越を感じるものだと。
それが単なる新しいもの…若さへの一瞬の迷いだとしても。
やがて彼は静かに身体を起こす。そして床に無造作に散らばった服を拾い、身に着けていく。どんなに深夜になっても、彼がこの部屋で朝を迎えることはない。
「相変わらずシャワーも浴びないの? あれだけ汗かいたのに」
「いい。面倒くさい。帰ってから浴びる」
「女の家から出勤するのが、そんなに嫌?」
ベッドの中からそう言うと、彼は振り向きもせず「別に」と言う。
「家で待っている人がいるわけでもないのに」
「そうだけど」
「リヤドにいる旦那が殴り込みに来る事もないし」
「…」
まさかそんな事を恐れているとは到底思わないけれど、それでも彼は黙々と服を着、スーツのジャケットに袖を通す。
余計な事を言ったと後悔する。
「タクシー呼ぼうか」
「いらない。通りに出れば拾えるから」
「そう…」
ジャケットの襟をピシリと引き締めると、ようやくこちらを振り返って言った。
「じゃあ」
またね、なんて言わない。私はベッドの上でヒラヒラと手を振る。
玄関の扉の閉まる音。遠ざかる靴音。
部屋の明かりを消し、こっそりとカーテンの隙間から外を見下ろす。彼が通りに向かって颯爽と歩いていく後ろ姿が見える。女の部屋で情事に耽っていたなんて思えない、まるで今からでも戦いに行くみたい。
もちろん振り返りなんてせず、大通りの灯へと吸い込まれていった。
***
彼、野島遼太郎は取引先の営業マン。新卒入社後、うちの担当として先輩社員に連れられて来て今年で3年目。当初から態度は堂々としていた、とは私の前任者談。
この1月に私が異動して担当となり、初顔合わせしてから3ヶ月。前任者も「自頭のいいヤツ。裏表なさそうで、へつらうことがない。好みは分かれると思うけど俺は嫌いじゃない」と評していた通り、なるほど、初回の打ち合わせからそれがすぐにわかった。きれいな顔して生意気な男だな、と。
黙っていれば彼は相当な美青年だ。
意外だったのは、ただの生意気な美青年ではなかった。打ち合わせが終わった後の接待の席でのことだった。
彼の目…とんでもない速さ頭を回転させ、状況を処理してる時の冷徹な目。かと思えば、会話のエアポケットで不意に見せる表情。どこか遠くに飛んでいき、少年のような危うさを灯す。彼の中でさえも持て余す不協和音…そんなアンバランスを湛えた目を移ろい見せることだった。
不意に見せる表情、その脳裏に、何が過るのか。
だから思わず顔合わせ会の後の接待の席で上席たちの目を盗んで、私から声を掛けた。一瞬よぎる海外滞在中の夫の顔を彼方に追いやって。
*
「野島遼太郎…さん。いい名前だね」
会がお開きになり、私たちはこっそりと2人だけで2次会に行った。そこで昼間受け取った名刺を眺めながらそう言うと、彼は「九園紗都香だっていい名前だと思いますよ。品がある」と言い、私を驚かせた。
「いかついでしょう? 名前負けしてるわ」
「そんなことないですよ。京都のご出身で?」
「いいえ、祖父母は京都だけど、私はこっちの生まれ」
「なるほど。ということは旧姓を使っているんですね」
鋭いところを突くな、と思う。ここに来る前に指輪は外していたが、昼間の打ち合わせで見られていたのかもしれない。
「お互い、もういい大人だから、別姓で仕事しているのよ」
「そうでしたか」
「ね、遼太郎くんって呼んでもいい?」
彼はウイスキーグラスに口を付けながら「お好きにどうぞ」と答えた。
「遼太郎くん、ずいぶん大人っぽい香りがする。香水?」
そう訊くと彼はカバンから小さなボトルを取り出し、私に見せた。
「Maison Malgiela…REPLICA…Jazz Club? 初めて見るわ。彼女からのプレゼント?」
「いえ。貰い物には変わりないですが」
「えぇ~怪しいなぁ~。だって大事に持ち歩いてるんでしょう?」
しかし彼は澄ました顔をしてそのままカバンにしまい込むと、再びグラスを傾ける。ウイスキーで濡れた唇、その舌先を覗かせた時、この男が欲しい、と身体の奥から突き上げるような感情が沸き起こった。
「さっきの宴会で、たまにすごくつまらなそうにしてたでしょう」
「僕ですか?」
「心ここにあらず、な顔してる時があったわ。かと思えば」
「…なんですか?」
「すごく冷静に会話を処理している様子もあって。頭が良くて、面白そうな子だなって思ったのよ」
「そういうもんじゃないですか。ずっと同じ顔してるわけじゃない」
「猫の目みたいにクルクルって変わるのよ。あなたの頭の中、どうなってるんだろうって興味が湧いたの」
私は彼にピッタリと身体を寄せた。彼も慣れているのか避けもしなければ動揺もしない。若いくせに相当遊んでいるのだとわかる。お互い様なんだろうと思った。
「紗都香さんの旦那さんは随分寛大なんですね」
「堂々と一体何をやっているんだ、この女は、って軽蔑されちゃったかしら」
「そういう意味じゃないですよ。素直じゃないですね。面倒くさいタイプの女性なのかな」
私がムッとすると、彼はフフっと笑った。
「そうね、寛大かもしれないわ。世の中達観しているような歳だし、お仕事で海外にいることが多くて。お陰で自由なの、私」
「だから1人くらい遊び相手が増えることくらい、別に構わないってわけですか」
「そういう遼太郎くんだって、女の子にモテそう」
「そうでもないですよ」
「またぁ、ご謙遜でしょう?」
「俺、嫌な奴ですからね。もうわかってるかと思いますけど」
「まだ、わからないわ」
そう言って私は彼の肩に顎を載せ、彼の目を覗き込んだ。
「もっと、教えてよ」
その夜。
私はJazz Clubのラストノートの香りを知った。
*
単なる遊び相手のつもりだった。
彼は24、私は37。一回り以上も歳が離れているのだから。何なら夫と彼は親子ほど歳が離れている。
夫は海外を飛び回り、離れて過ごすことが多い、そのための暇つぶし相手を、私は何人か持っていた。
そう、だから遼太郎くんの事も軽い気持ちだった、はず。
社会人3年目とはいえ、私から見れば学生に毛が生えたような男の子だもの。おまけにきれいな顔してプライドが高いときたら、からかうしかないでしょう?
それなのに。
襟足の黒い髪が白い首筋にかかっている。耳たぶからその襟足のラインに沿って舌先で撫でると、彼はくすぐったそうに肩を竦め、拗ねて見せる。でも、甘ったれの顔のようにも見える
そんな表情とは裏腹な気怠いJazz Clubが鼻腔を突く。
『私、あなたの舌先に惚れちゃったみたいなの』
冗談でもあり本気でもあるそれを伝えると、彼は "どういうこと" と笑った後『じゃあ、好きなだけどうぞ』と言って舌を細く出した。
唇が触れない距離で互いに舌先を弄ぶ間、彼は細く目を開け、冷ややかに私を見ていた。
私の中で亀裂が走り、破裂した。
彼の中のアンバランス。
それは透明な灰となって彼の背中に、私の顔に降り注ぎ、汗で張り付く。
本当は今だって信じたくはない。
こんな生意気で、危うい若造に、夢中になっていることなど。
#3へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
