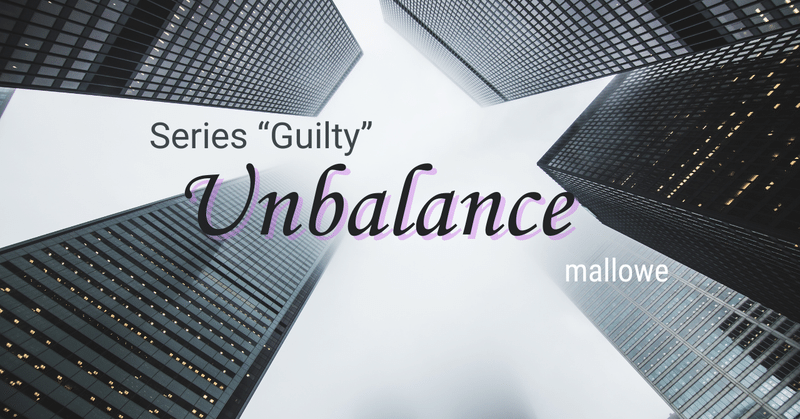
【シリーズ連載・Guilty】Unbalance #1
~九園紗都香という名の女性、の巻
時刻は午後8時半を過ぎた。
営業職の彼にしてみれば、客先との突発対応などで約束の時間を30分過ぎることは致し方ないだろう。私の目の前のギムレットは空になる手前で止めている。
「紗都香さん、何かお作りしましょうか」
このバーは私の馴染みの店だ。バーテンもグラスを見てさり気なく声を掛けてくる。
「ううん、まだ大丈夫。ありがとう」
そう答えるとバーテンはほぼ全てを察してくれ、密やかに微笑んだ後は適度に放っておいてくれる。現に指輪を外して来る時はさりげなく連れ合いとの会話に配慮してくれる。そんな信頼もあって、デートではこの店を利用する。
再び時計に目をやる。8時40分。連絡は入らない。彼は大体こんなパターン。仕事はきっちりやるのに。
思わずため息が漏れてしまう。流石に連絡が入らず1時間待たされたら店を出よう。そう考えた。
「いらっしゃいませ」
入って来た客に、バーテンは控えめに挨拶をした。彼かもしれないと思ったけれど、はしゃいだりしない。素知らぬふりして前を向いたまま、ギムレットのグラスを傾ける。
しかし背後にいる別の客の連れ合いだとわかると落胆する。私らしくもない。あんな若造に振り回されるなんて。
いよいよグラスが空になってしまった。バーテンと静かに目が合い、私は思わず苦笑いを浮かべてしまう。
「お待たせ」
その声は突然、右後ろから飛んで来た。
「あっ…遼太郎く…びっくりした…」
彼…野島遼太郎は静かに微笑むと私のグラスを見て「ちょうどいいタイミングだったかな」と遅れたことをこれっぽっちも悪びれずに言った。
黒に近いダークなスーツ、ライラックカラーのネクタイはセミウインザーノットで締め、振る舞いのスマートな彼を引き立てている。
彼は近づくバーテンに「テキーラ」と告げる。ネクタイに手をかけ緩めながら隣の席に着く際、ふわりと男性的な香りが舞う。彼が纏っている香りはMaison MargielaのJazz Clubというフレグランス。ラムの甘さとペッパーのスパイス感、まだトップノートに近い香りだ。私に会うために付けたのだと思うと自尊心がくすぐられる。そういう所は素直で、彼はとにかくチグハグ…アンバランスな男だ。
まだ若い彼にはそぐわない香りな気もするが、逆に若さゆえの背伸びのようにも思えて、微笑ましい。と同時に、悩ましい。
バニラとタバコの甘くて気怠いラストノートが彼の汗と混じると、脳髄の奥深くにまで入り込んでくる。それを思い出すだけで身体が熱くなる。
まさに媚薬そのものだ。
彼の前に透明な液体が入ったショットグラスが置かれる。グラスの縁のライムをつまんで指を湿らせ、塩を付け舐める。その舌先を見るや、思わず目を逸らす。
彼は何食わぬ顔でショットを一気に煽る。最後にライムを齧ってグラスの中へ放った。バーテンに人差し指を立て「もう1杯」と合図する。
「駆け付けで威勢がいいのね」
「食前酒ですよ。俺、腹減ってるんです。ここじゃ腹にたまる飯ないし。店変えますよね」
「えぇ、まぁ…」
自分は1杯しか頼んでいないことが返って申し訳なくなってしまったが、勢いよく彼が2杯目のテキーラを煽ると私たちは店を出た。
だいぶ温くなった夜風が、さざ波のように都会の喧騒を流れていく。
「桜もあっという間に終わっちゃったわね。遼太郎くんと夜桜を眺めたかったわ」
「そんなしおらしい趣味があったんですか?」
「どういう意味よ? 日本人なら桜を愛でたい気持ちはあるでしょう」
彼の腕を取って軽く睨んでも。涼しい顔だ。
「そもそも遼太郎くんにそんな雅な日本人の心がなくても不思議じゃないけどね」
「随分な言い方ですね」
「あら、風情を嗜んだりするのかしら?」
「まぁ、下を向いて歩くことはありませんからね」
そう言って彼はどこか遠くに視線を投げた。「ただ…」
「ただ?」
「桜は、苦手なんです」
「あら珍しい。そんな人もいるのね。どうして?」
それには答えず、彼は軽く笑みを浮かべた。
「紗都香さん、何杯飲みました?」
「1杯だけ」
「ほんとに? だって1時間かかりましたよ」
「わかってるんだったらまず "遅れてすみません" があってもいいんじゃない? 事前に連絡だって」
「今の時期は新入社員のOJTでたて込むの、わかりますよね。それに俺がそんなマメで聞き分けの良い男だなんて思ってないでしょ」
「本当に。仕事はきちんとしているのに、まるっきり人が変わるわね、あなた」
「そんなに変わらないですよ」
そう言って笑う顔は清らかだ。私は鼻で小さくため息をつく。
「じゃあ、何食べようか」
こんな風にルーズになりがちな私たちの約束は、よほどのことでない限り店を予約することはない。
「そうですね」
彼は呟くように言い、腕時計に目をやった。今日は木曜日、明日も仕事がある。
「今日もウチに、来る?」
私がそう尋ねると、はにかむように口角を僅かに上げ「うん」と頷いた。
そういうところ、可愛げがあって困る。彼は自分の魅せ方をわかっているのだろうか。今のところ確信犯なのか、無頓着なのか、よくわからない。
彼はクルクルと、表情や態度を変える。
悔しいけれど、してやられっぱなしだ。
近くの小さなイタリアンバーに入った。そこで白ワインのボトルとサルメリア(ハムやサラミの盛り合わせ)、オイルパスタにピッツァまで頼む。若い彼は清々しいほどモリモリと、時折リスのように頬を膨らませながら食べる。ニンニクが入っていようが、気にするはずもない。
そしてまるで水を飲むようにガブガブとワインを飲む。
私は呆れた振りして見るけれど、本当はその魅力に私が飲まれている。
だってバーではあんなに艶めかしかったのに、今は正反対なんだもの。
「そんなに俺、食べてる姿、おかしいですか?」
見惚れていた私に彼が訊いた。
「おかしいって?」
「複雑な顔して見てるから。はしたない食べ方しているのは自覚しているんです」
「はしたないわけじゃないわ。若いって良いなぁって思いながら微笑ましく見ていただけよ」
「紗都香さんだって十分に若いですよ」
「さすが営業さん。その辺の口振りは抜かり無いわね」
彼はフン、と口元に皮肉っぽく笑みを浮かべた。
「遼太郎くん、普段の食事はどうしてるの?」
「ほとんど外食ですよ。俺が自炊するような男に見えます?」
「意外な所があるからね、あなたは」
「幸い、最寄り駅降りたら冷蔵庫代わりになる店がたくさんあるんでね。キッチンいらずですよ」
「あなたのお陰で街は繁盛しそうね」
「大袈裟な」
「でも、外食ばかりしていると身体壊すわよ」
「根拠に乏しいこと、言わないでください」
あっという間に白のボトルを空け、2本目の赤、プリミティーヴォを注文した。
*
22時。食事を終え、私の家へ。そしてシャワーも浴びずにそのままベッドへ。
彼の肌。
女性も羨むほど白くシルクのように艷やかで、無駄な毛など無い。細く見えても胸や背中の筋肉はそこそこついており、撫でるのが心地良かった。それともちろん、匂い。体臭とあの香水の混じった匂い。洗い流してしまってはもったいない。
「遼太郎くん、着痩せするタイプよね」
「最近またちょっと鍛えているんです。Tシャツで仕事した方が、箔が付きますかね?」
「身体で見せなくても、あなたの態度で十分でしょう」
彼はフフッ、と笑う。本当に生意気な顔をすると思う。
不意に彼は雄の目つきに変わり、私の左手を取り薬指の付け根…微かに残る指輪の痕…に唇を押し当て、舌先でなぞる。あなたは、またいけないを事しているんだよ、と言わんばかりに。
「紗都香」
そしてベッドの上でだけ、私を呼び捨てにする。あなたは本当にアンバランスな男。
私は彼の耳の後ろに舌を這わせる。甘い香りのくせに、苦い。
そして何を考えたって無駄だと白旗を上げて、身を委ねる。
#2へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
