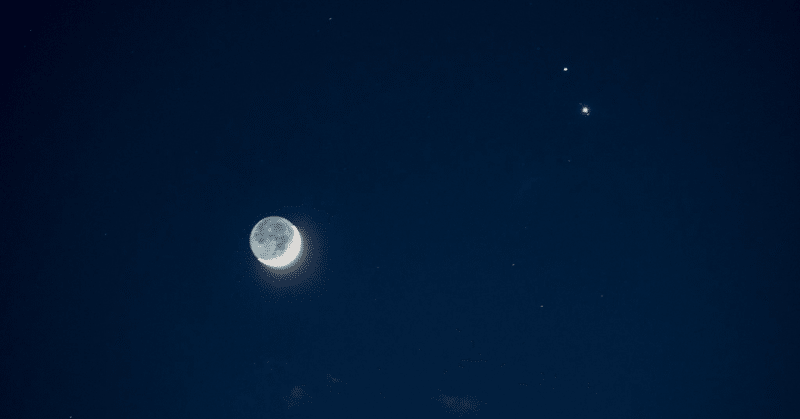
「和して同ぜず」と「多体問題の安定解」
昨日は「雑」という言葉の奥行きを探ってみた。雑は多様性につながり、多様な存在の重なり合い、共通部分はゆらいでいる。そのようなことを思ったのだった。
「ゆらぎ」という言葉から、「多体問題」が頭に浮かんでくる。多体問題とは「互いに相互作用する3体以上からなる系を扱う問題」(Wikipedia)である。3つ以上の物体(あるいは存在)が互いに相互作用するとは、何かしらの関係性、つながりを持っているということに他ならない。
多体問題の定義を眺めていると、物理的な枠組みを超えて、日常それ自体が多体問題なのだと気づかされる。私たちは真空状態の中で孤立して存在しているのではなく、自分を取り巻く他者、環境と関わり合いながら自らの存在を維持している。
浅田秀樹『三体問題 天才たちを悩ませた400年の未解決問題』から言葉をいくつか引きながら「多体問題」と「ゆらぎ」の響き合いを探ってみたい。
天体の個数が「1個」と「2個」、これら二つの場合は解決済みの問題です。「3個以上の場合」はすべて未解決問題です。解決済みの1個と2個の二つの場合のみが例外であり、3個以上、つまり、それら以外のほとんどの場合(こちらのほうが大多数)は未解決です。2個と3個の間で大きな境界があるのです。(中略)実際に、天才たちによって「特別な状況」を仮定した場合においての「三体問題」の解は発見されています。しかし、「一般的な条件」での解を見つけることには、ことごとく失敗したのです。
ポアンカレは何と、平面上の制限三体問題に対する解を級数表示すると、その級数が一様収束しないことを証明してしまったのです。一様収束する解が存在しない場合、近くの異なる2点から出発した二つの物体の運動は、ある時点まで似ていても、長時間経てしまうと、互いに全く離れた位置にあるのです。それまで科学者たちは、特異な衝突解の場合を除いて、ニュートンの万有引力における運動はなだらかに変化するため、その運動方程式に対して、常に逐次解や級数解が存在するものだと信じ込んでいたのです。ポアンカレを除いて、誰一人それを疑う者はいませんでした。結果として、「三体問題」は厳密な解を与える求積法だけでなく、無限級数の形の方法さえも退けてしまったのです。これが、「三体問題は解けない」といわれる所以です。(中略)このポアンカレによる業績は「カオス理論」の始まりとされます。
しかし、ポアンカレの定理は「三体問題の解が構成不可能」だということを主張してはいません。あくまで一様収束する、つまり任意に長い時間にわたって正確な無限級数の解が存在しない、ということが彼の定理からの結論です。「三体問題」における任意の時刻での天体の位置を、何らかのある関数を用いて表示することが不可能だとは主張していません。(中略)ポアンカレは、著書『科学と方法』の中で「証明するのは論理によってであるが、発明するのは直観によってである。」と述べています。ポアンカレ以降も、科学者たちは閃くことで「三体問題」に対する新しい特殊解を見つけています。
「三」という小さな数でも、互いに関わり合う世界において、一般的な条件のもとで時間と共に変化する位置関係(解)を特定できない。そして、それは「カオス」つまり深淵な「混沌」世界の入り口になっている。
このことは、3つ以上の存在がつかず離れずの関係にあるかぎりでは、その将来の関係性(相対的な位置)がどのようなものであるかを予測することが極めて難しく、不確定であることを意味する。この不確定性は「ゆらぎ」につながっているように思える。
三つの存在のうち、いずれか2つが接近して同化すれば、三体問題が二体問題へと変化する。二体問題は一般的な条件のもとで将来の位置関係(解)が与えられることからすると、将来に未知の関係性、可能性を生み出すことは「三体以上の関係性・問題を作り出してみる」と言えるのかもしれない。
著者は「ポアンカレ以降も、科学者たちは閃くことで『三体問題』に対する新しい特殊解を見つけています」と述べているけれど、三体問題の安定解(の一部)の極めて美しい描写、表現に出会ったので、ここで紹介したい。
In 1890, Henri Poincaré proved the non-existence of the uniform first integral of the three-body problem and the sensitive dependence to initial conditions of its trajectories.
— Massimo (@Rainmaker1973) January 3, 2024
Yet, stable solutions to it do exist and these are some of them.pic.twitter.com/haECKnWsfp
三体が描く軌跡は、つかず離れずの関係において見事に調和している。
人間も同じではないだろうか。時に重なり合いながら、時に離れながら、動き続けながら調和、落ち着く関係を見い出し続けている。
逆に、調和の破壊としての支配や服従は、他の存在を従属、隷属させることなのだとしたら、それは三体以上の問題(関係性)を、二体問題、あるいは一体問題へと縮退、変容させることと言えるのかもしれない。
調和的な軌跡、運動を眺めていると、じつにみずみずしく生命的であるし、ゆえに生命は「ゆらぎ」に支えられている。そう思えてならない。
同一直線上にない(一次独立な)三点があれば、平面を支えることができるように、調和や安定の源は「三以上」の複数性にあると思うと、「多様性」という概念の奥行きが一層感じられてくる。
ああ…三体問題の安定解の軌跡を眺めていると、「和して同ぜず」とはまさにこのことなんだなと直感した。たえまなく動いている、ゆらいでいる意味では不安定なのだけれど、その不安定性の中に「安定」と「調和」の息吹が聴こえる。
「多体問題」と「ゆらぎ」が響き合う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
