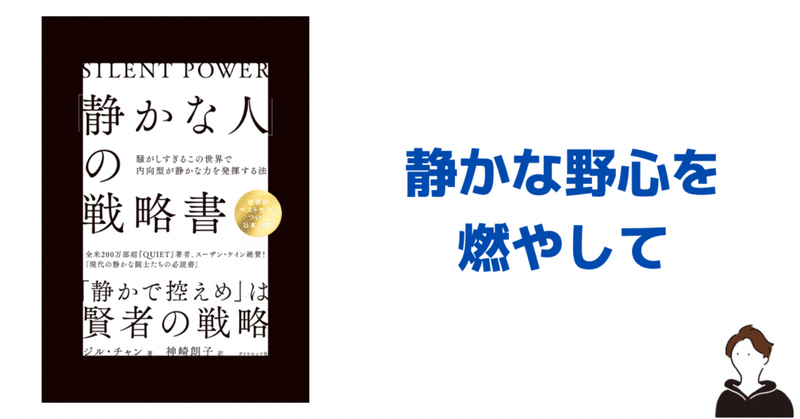
【ヒトコト読書】「静かな人」の戦略書-騒がしすぎるこの世界で内向型が静かな力を発揮する法/ジル・チャン
【ヒトコト読書】はワンフレーズだけでもアウトプットすることをテーマに色んな一冊を紹介する記事です。
↓今回はこちらの本を紹介します
①この本を読んだ理由。
この本の著者であるジルさんと同じように、私はパーティやちょっとした雑談がとても苦手で、完全なる内向型人間です。
これまで営業職として配属され仕事をしてきましたが、根本的に自分には向いていない職種なのだろうな…と常に感じて来ました。
ただ待っていても同じ日々が続いていくだけ。自分のキャリアは自分で形作る必要があります。
「内向型」の特徴と戦略を知り、強みを活かして活躍したいなと思い、そんな時に魅力的なタイトルを見つけ、この本を手に取りました。
②ありのままの「強み」を活かす。自分を過小評価しない。

真面目で遠慮がちな内向型人間は、自分の能力を過小評価しがちです。
しかし、ありのままの自分を受け入れて強みを活かし、自分に合った方法でキャリアを実現させていくことは十分に可能。
内向型の強みの例として、「深く考えられる」「話を聞くのがうまい」「ひとつのことに集中できる」「粘り強くやり抜く」ことが挙げられます。
表現力と社交力を武器に、自信満々に話を繰り広げて成果を残す「外向型」は目立って見えます。しかし、内向型から外向型に無理に変わろうとする必要はありません。
自分の強みは何かをしっかり把握し、その上で価値を生み出す方法を考えれば「内向型」のあなたを必要としてくれる人がきっと現れます。
③内向型にも野心がある。

野心と性格には何の因果関係もありません。内向型人間であっても、成功したいという思いは存在して当然です。
無理な自分を演じて他人の評価を得る必要はなく、自分の能力を発揮すればキャリアは実現可能です。
しかしどんな仕事であっても、他人とのコミュニケーションを断絶することはできません。価値観の異なる人とコミュニケーションを取る時には、対立姿勢を捨ててお互いに相手の意見や考え方を尊重するように努めます。
この時、内向型の人はその場を収めるために、自分の感情を無視してしまいがちです。しかしこれでは長期的な対人関係としてマイナス効果になるだけでなく、心身の病気にもつながるおそれがあります。
④内向型コミュニケーションのコツ。

コミュニケーションにおいて重要なことは、「自分が伝えたい情報を相手に理解させる」ことです。次の順番を意識すると、内向型でもうまくコミュニケーションがとりやすくなります。
1.共感を伝える
2.中立的な情報を伝える
3.要求を伝える
まずは相手の気持ちに理解を示すこと。そして、その問題を解決するために中立的で客観的な事実を伝えること。最後に相手への要求を伝えます。
例えば、別部署から無理な要求をされた時には、
「〇〇部が忙しくて大変なことはすごくわかります。しかし、この要求に応えるには○○時間と○○人の人員が必要です。ですので○○日の時間をください。」
このように順序立てれば、苦手だと感じているコミュニケーションも円滑に取れるようになってきます。
人間関係の摩擦は誰にとっても苦しいものです。摩擦の主な原因は「双方の期待がズレている」こと。摩擦がひどくなるとそのせいで会社を辞めてしまう人も出てしまう程です。
人間家計の摩擦を少なくするためには、「正しい方法で自分自身のことを率直に伝える」ことが非常に大切です。相手に対しても偏見を持たず、お互いを尊重しあう意識を常に持ちましょう。
⑤内向型が評価を勝ち取るために。

「脚光を浴びているスーパースターが真の影響力を持つとは限らない」ことが、スポーツを始め多くのデータで証明されているようです。目立たない静かな人でもチームに必要な役割を果たします。
内向型人間は自分の弱点を知り、個人よりもチームの利益を優先し、つねに努力を怠らないという性質を持つことが多いです。そしてそれが周りのメンバーにも影響、伝染していきます。
「スタープレイヤーへの投資よりも費用対効果が高い」ことが証明されつつあり、これは私たち内向型人間にとっては、嬉しい限りの傾向ですね。
実際に会社やチームで内向型が評価を得ていくためには、「小さな貢献も記録して成果を伝える」ことがコツの一つです。数字にあらわしにくい業務もできる限り数値化・可視化して、記録していくことが重要。
上司からの評価を得るためには「上司や上層部にとって最も重要な3~5個の目標を理解」すれば、自分のリソースをどのように配分していけば良いかが判断しやすくなります。
売上拡大なのか費用削減なのか、組織によって多様な目標が存在するはずです。評価者が何を重要視しているのかを把握し、それを叶える動きをすることで自身のキャリアも拓けてくるはずです。
⑥私の個人的な感想。
内向型でもこんな風に活躍していけるんだなぁという自信が生まれるとともに、「同じような悩みを持つ人がこの世界に数多く居るんだ」という心強い気持ちになれる作品でした。
就活や転職活動でも「外向型」が求められがちな雰囲気があると感じてきました。しかし無理に外向型になろうとしても成果は上がらず、心身にも悪影響だと思います。
自身の強みを把握して、それを活かすキャリアを自ら形成していくこと。「自分を信じて頑張ろう」と前向きになれる一冊でした。
最後までお読み頂きありがとうございました。次回の記事もぜひご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
