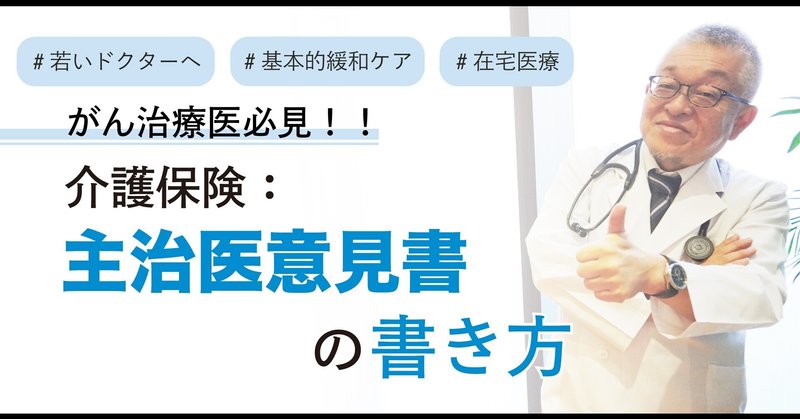
主治医意見書の書き方で患者さんの運命が決まります!【医】#36
こんにちは、心療内科医で緩和ケア医のDr. Toshです。緩和ケアの本流へようこそ。
緩和ケアは患者さん、ご家族のすべての身体とこころの苦しみを癒すことを使命にしています。
今日のテーマは「介護保険:主治医意見書の書き方」です。
動画はこちらになります。
先日のことです。緩和ケアチームの看護師が私に言いました。
「産婦人科の若い先生から、介護保険の主治医意見書の書き方がわからないと相談を受けました。先生、相談に乗ってくれませんか。」
私はその先生に主治医意見書の書き方の何がわからないのか聞きました。先生は言いました。
「私の担当しているがん患者さんですが、抗がん剤治療が終了し、今後は在宅で最期まで生活したい人がいます。そこで、介護保険が必要となり、主治医意見書を主治医である自分が書かなくてはならなくなったんです。
以前2年上の先輩が、一緒に診ていた患者さんの意見書を書いたのですが、どうも書き方が悪かったみたいで、低い介護度になってしまいました。その先生が、そのことで上司に怒られていたところを見ていたので、そうならないようにしたいのですが、どう書いていいかがわからないのです。教えてくれませんか。」
この質問に、皆さんならどう答えますか。
がん患者さんが在宅療養するためには、介護認定が必要になってきます。そのためには、主治医が、主治医意見書を書かなければいけません。
しかし、がん患者さんの介護認定のための主治医意見書の書き方には、実は他とは違う、とても大事なポイントがあるのです。
今日はがん患者さんの介護認定の主治医意見書の書き方についてお話します。この記事の中で、具体的な主治医意見書の書き方も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
今日もよろしくお願いします。
がん患者さんの主治医意見書に必要なこと
冒頭の話に戻ります。質問をしてきた先生の先輩が書いた主治医意見書はなぜ、低い介護度にしかならなかったのでしょうか。
おそらくですが、今の、現時点での患者さんのADLをそのまま書いてしまったからではないかと思われます。
抗がん剤治療終了時点の患者さんは、まだ比較的元気で、ADLも落ちていない方が多いのです。がん患者さんは、亡くなる1~2か月前までは、比較的元気に過ごされることが多いからです。退院の時点でのADLを意見書に書いたのでは、せいぜい要支援の介護度しか出ません。
しかし、がんの患者さんは、終末期、最期の1か月近くになると、急速にADLが下がってきます。そんな時に要支援程度の介護度では役に立ちません。介護度の再申請をしないといけませんが、そのころのがん患者さんの病状のスピードは急速に進行しているため、再申請認定に間に合わなくなることが多いのです。
そうならないためには、どうしたらよいでしょうか。
それは、介護保険の主治医意見書に今の患者さんのADLをそのまま書くのではなく、今後急速に状態が悪化する可能性が高いことを書くことが大事なのです。
このことを書いてあるかないかで、終末期のがん患者さんが、十分な介護を受けられるかどうかが決まるといっても過言ではありません。このポイントを決して忘れないでください。
抗がん治療が終わった患者さんが、最期まで安心して自宅で過ごすためには、介護保険はなくてはならないものです。充分な介護保険を受けるためには適切な介護度の付与が必要なのです。そのための最大のカギが、主治医意見書なのです。
在宅で安心して最期まで過ごすためにとても大事な主治医意見書を、主治医であるあなたが、責任をもってしっかり書いてあげてください。
主治医意見書をどう書くか
それでは、具体的な主治医意見書の書き方についてお話しします。
まず知っておいてほしいことは、介護保険は、がん患者さんなら40歳以上から受けられる、ということです。また以前は、介護保険は末期がんのみが対象と規定されていましたが、今は末期でなくても受けられるようになっています。したがって、末期がんと表記しなくてもかまいません。
40歳以上のがん患者さんが受けられる介護保険を、患者さんが受給するためには、役所から主治医に送られてくる「主治医意見書」が必須です。この書類に主治医が記入し、役所に送り返さなければいけません。
役所に届いてから、役所による認定調査が行われ、その後約1カ月で患者さんの介護度が決定し、介護保険が利用できるようになるのです。主治医が意見書を書かなければ、認定調査ができないので、患者さんが介護保険を利用できません。したがって主治医は、できるだけ早く意見書を書いて役所に送る必要があります。
先ほど申し上げたように、主治医意見書は書き方に工夫が必要です。そのことをもう少し詳しくお話します。
介護申請時には、患者さんのADLが保たれていることが多いため、今の患者さんの状態をありのままに書いたのでは、要支援程度にしか認定してもらえません。
がん患者さんは、終末期になると急速にADLが低下するので、要支援程度の介護度では、その時に必要な介護の支援が受けられなくなってしまうことは先ほど申し上げました。
ADLが低下し、横になっていることが多くなった患者さんには電動ベッドが必要ですが、要介護2以上の介護度でないと、電動ベッドは導入できません。したがって主治医意見書の意見欄に、今後急速に状態が悪化する可能性が高いことを明記してください。
特に以下の部分に注意してください。「1. 傷病に関する意見(3)「最近介護に影響のあったもの」の欄です。
この欄で大事なのは、 具体的な治療内容などではなく 「どのくらい介護に手間がかかるか」を書くことです。
例えば、神経障害による歩行障害が顕著で, 今後6カ月以内に常に見守りが必要になる可能性が高いとか、肺転移があり今後進行すると呼吸困難の症状が悪化し、自分では動きにくくなる可能性があるので、今後6カ月以内に介護の手間が増す可能性が高い、などです。
「5.特記すべき事項の欄に書く書き方」も重要です。この欄では、 なかなか数値化できない介護の手間や主治医が考える必要なサービスを書いてください
具体的には、夜間のせん妄が強くなり、同居の家族が眠れなくなり、疲労がたまってくる可能性が高い。下肢の筋力低下が急速に悪化しており、転倒の危険性が高くなり、今後見守りが欠かせなくなる可能性が高い。全身の倦怠感が強くなり、今後、布団からの起き上がりが困難になり、電動ベッドが必要になる可能性が高い、などと具体的に今後起こりうることを書いてください。
いずれにしても、「今はADLが保たれているが、今後急速に低下してくるので、その時は介護が必要である」という点を強調することが重要なのです。そのことを役所の担当者に伝える、という気持ちが大事だと思います。
そして、必要な介護度の認定が下り、その結果、患者さんが最期まで安心して家で過ごすことが可能になるのです。ぜひそのことを心に描きながら、主治医意見書の記入をしていただければ、幸いです。
あなたに伝えたいメッセージ
今日のあなたに伝えたいメッセージは
「がん患者さんの介護保険の認定における主治医意見書の書き方には、特別なポイントがあります。今後急速に状態が悪化する可能性が高いことを必ず明記するということです。これがあるかないかで、終末期のがん患者さんが、十分な介護を受けられるかどうかが決まるのです。」
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私は、緩和ケアをすべての人に知って欲しいと思っています。
このnoteでは緩和ケアを皆様の身近なものにして、より良い人生を生きて欲しいと思い、患者さん・ご家族・医療者向けに発信をしています。
あなたのお役に立った、と思っていただけたたら、ぜひ記事にスキを押して、フォローしてくだされば嬉しいです。
また、noteの執筆と並行してYouTubeでも発信しております。
患者さん・ご家族向けチャンネルはこちら
医療者向けチャンネルはこちら
お時間がある方は動画もご覧いただき、お役に立てていただければ幸いです。
また次回お会いしましょう。さようなら。
ここまでお読み頂きありがとうございます。あなたのサポートが私と私をサポートしてくれる方々の励みになります。 ぜひ、よろしくお願いいたします。
