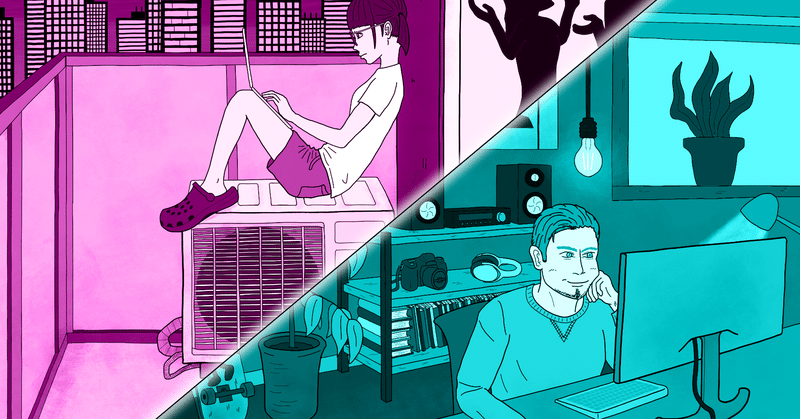
notoに記事を1年7ヶ月毎日投稿してみて、初日の僕に教えたい8つの知恵
2020年4月の、noteデビューする僕に、今の僕が教えてあげたいことを綴ってみます。
noteを始めたばかりに方には、ホンの少し参考になると思います。
僕の体験や主観を書きますので、どなたにでも参考になるとは言えません。その点はご了承ください。
1.タイトルに「第○○話」は失敗だった
僕は、このnoteを「10年続けよう」と思ってスタートしました。
僕のnoteは全て、『妻に捧げる3650話』というエッセイなのだ。いろいろなことを書くけれど、その全ては「エッセイ」だ。そう考えて、書き始めたのです。なので、タイトルにいちいち、「第○○話」と付けました。
これは失敗でした。
僕自身が、そのようなタイトルの記事には"ハードルの高さ"を感じ、読もうとしないのです。例えば、「第15話」ならば、未読の14話を全て読まないと理解できない可能性があります。そんな思いが頭をかすめるのです。
意識し配慮すべきは、「はじめて訪れてくれた読者さん」です。
連続モノを書く場合でも、"その1記事だけで満足していただける工夫"を、するべきでした。
ありがたくも「最初から読みたい」と、そう思ってくださった方のために、第1話のリンクやマガジンのリンクを、記事の最後に据えるべきでした。
今は、自分のための「第○○話」は、記事の1番最後に変更しまして、我ながら「やはり、こうだよなぁ」と独りごちています。
2.マガジンを、すぐ作って失敗した
マガジンは削除はできます。マガジンがなくなるだけで、記事は残ります。でも、「コレとアレとを1つにして~」というような作業が、超~面倒なのです。
カテゴリー別に分類しようと、そう思う方も多いかもしれませんが、僕はその思考の結果、マガジンがどんどん増えてしまいました。
「あの記事は、どのマガジンに入れたっけ?」と、マガジンのパラドックスに陥ったのです。
僕の肌感覚では、1年くらいは作らない方が良い気がします。どうしても、何がなんでも必要だというマガジンを、1つか2つだけに絞るべきでした。
理由は、1年も継続すると大抵は、「こうなるとは、当初は想像すらできなかった」というnoteになるハズだから。
ライティングの力も磨かれ向上し、初期の記事を書き直したくなるのも、『noteあるある』でしょう。
1年間継続すると間違いなく、自分のnoteの、しっかりした方向性が見えてきます。
カテゴライズは、それからの方が良いと思います。
3.継続のコツ
僕の継続のコツは、『2人の方の言葉』の実践です。
まずは、キングコング西野さんの言葉。
「継続したいのなら、『努力とは言えない小さなこと』を『毎日』やる」
歯磨きレベルの『習慣』にしてしまうのが1番楽チンなので、『毎日』です。決まった時間が望ましいですね。
そして、毎日やるためには、大きい計画や、中くらいの計画ではダメなのです。しんどくって、習慣になるまえにサボってしまうから。
だから『努力とは言えない小さなこと』、なのです。
僕は、こんな手抜き記事も書きました。
この他にも、「体調不良で今日は書けません」という、ほぼそれだけの記事があったはず…。(探したけど見つかりませんでした)
こういう『努力とは言えない小さなこと』で良しとすると、一体なにが良いのか。
僕は、この手抜き記事のおかげで、「毎日投稿してきた」と、自信を持って言えます。誰かに対して言うのではなく、僕が僕自身に言えるのです。
この効果って、皆さんが思っている以上に、凄く大きいです。
もう1人は、誰だったか忘れちゃいました。確か、作家さんかライターさんでした。
この言葉です。
「10年続ければ、大抵は飯が食えるようになる」
良く、1ヶ月や1年を目標にする方を見かけます。
1年続ける人って、けっこういます。でも10年なら、きっとその「10年」に価値を感じる人がたくさんいます。
この「10年」の良さは、半年や1年で達成感を感じないところです。下手に「やった~!」と達成感を感じると、そのあとモチベーションの継続が大変になると思うのです。
まとめますと、僕の継続のコツは、
「努力とは言えない小さなこと」「毎日」「10年」という、この3つを自分に言い聞かせることです。
4.記事のネタ
最初の1月は順調でした。書きたいことがあって、このnoteを書き始めたからです。
でも、約1ヶ月でネタが尽きました。
「今日は、何を書こうか?」というのは、かなり苦しかったですね。
今は、まったくと言って良いほど、ネタに困りません。スキルとまでは言えませんが、ネタに困らないように僕が心がけていることを書きます。
①分割
1つの記事が長くなったなら、僕は分割します。書かなかったことは、翌日以降の「ネタ」になります。
②ヨコ展開
1記事の関連することや、似たことを考えてみる思考です。明智光秀展に行ったなら、織田信長や豊臣秀吉の記事も候補になりますし、可児市や土岐市も記事の候補です。ご当地の名産品に思考を巡らせば、栗きんとん、五平餅、美濃焼なども、記事の候補に挙がってきます。
③深掘り
横にはズラさずに、「なぜ?」「本当だろうか?」「この情報の根拠は?」と、Wikipediaやネット検索を駆使して、どんどん詳しく書こうとする思考法です。(長くなったら、①の「分割」を使います)
④メモ
何か閃いたときには、即、メモを取りましょう。閃きは、たった2~3秒で脳の奥に消えることがしょっちゅうです。
僕は、グーグルのメモアプリ『Google Keep』を使っています。スマホとPCとを同期できますし、音声でもメモできる優れものです。
⑤インプット
やはり、アウトプットする以上、インプットは必須です。インプットは思考の『ヨコ展開』にも『深掘り』にも繋がります。
5.僕のインプット先をご紹介します
①西野亮廣エンタメ研究所
キングコング西野さんの、オンラインサロンです。Facebookからですと、980円/月額です。内容は「メルマガ」みたいな感じです。毎日、Facebookグループに、西野さんが2000~3000文字の記事を投稿されています。
これだけです。
しかし、この内容がビジネスやエンターテインメントの最先端の情報ですから、思考がバンバン刺激されます。
②Voicy
キングコング西野さん、鴨頭義人さん、安倍照雄さんの、3人の配信を毎朝聴いています。全部無料です。音声は「ながら聴き」ができるので、非常にありがたいです。
③YouTube
両学長。平日のみ毎朝配信されています。お金の勉強と、本質的な『ものの見方・考え方』なども学べます。
本の要約・解説チャンネルで、学識サロンさん、サムさん、サラタメさん、中田敦彦さんの動画を、紹介される本に興味がある場合、視聴しています。
④YouTubeメンバーシップ
キングコング西野さんのメンバーシップです。2週間に1度の配信です。
約1時間の動画で、ゲストと西野さんとの『飲み会』なのですが、毎回、物凄い刺激になります。勉強にもなります。590円/月額です。
⑤本(読書)
僕は、Amazonオーディブル → kindle → 紙の本、という優先順位で本を購入します。何度も繰り返し聴きたい内容なら、Amazonオーディブルが最高のツールです。そしてkindle。kindleにない場合、致し方なく紙の本を購入します。
購入する約6割は、YouTubeの『本要約・解説チャンネル』で知り、興味を抱いた本という感じです。
6.ライティング能力の向上のために行ったこと
①本
まず、本を読みました。文章術のハウツー本です。
5冊くらい読みまして、これ!と思うのは、この本です。
『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』
著者:藤吉豊、小川真理子
基本が学べるのです。基本は実行可能です。
そして、基本は大事です。実感です。
②ストアカ講座
1000円の講座でも、もの凄い学びがあります。稀に「あれ?」、という講座も無いわけではありませんが、それは、超~~~稀です。
くどいようですが、基本は、ちゃんと学んだ方が良いと思います。
この講座は、たった2000円ですが、僕の評価は「神講座」です。
7.便利ツール
①マインドマップ
僕のイチオシの便利ツールです。下書きに最適です。
こんなやつです。
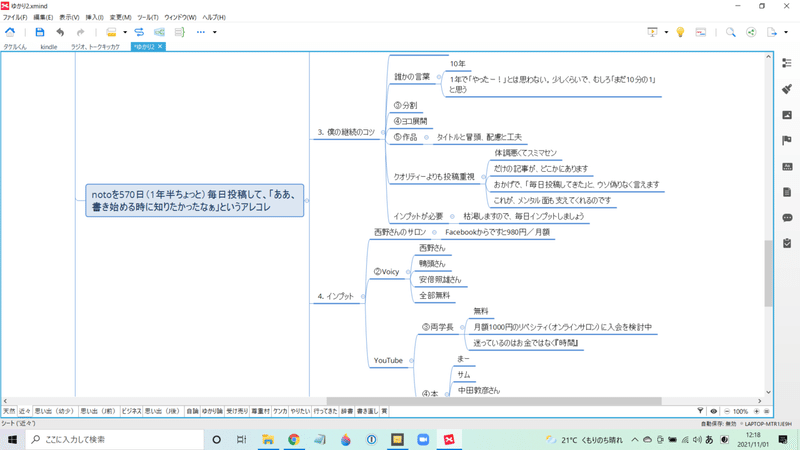
この記事も、マインドマップで下書きしました。
このツールを使うと、否が応でも論理的な記事になります。
そして、noteにコピペができるんです。もちろん、体裁を整えたらり、文章化したりという作業は必要ですが、記事は、圧倒的に読みやすくなります。
思考を箇条書きにできるのですが、その、箇条書きを、アッチやソッチに簡単に移動できるのです。
これは、起承転結を考えたり、横道に話が逸れたことを直したりするのに、超絶に便利なのです。
思いのほか長くなりそうなら、例の『分割』も、ここで思考できます。
マインドマップは、何種類もありますし、無料で使えるものがほとんどです。IT音痴の僕でも、感覚的に使えるようになりましたので、ほぼ誰にでも問題なく使いこなせると思います。
②Canva
僕は、このnoteにはCanvaを使っていません。時間の節約のためなどです。
でも、Instagramのために使い出しまして、少し慣れつつあります。
慣れますと、noteトップページの画像や、各記事のアイキャッチ画像が簡単に作れちゃいます。アイキャッチ画像は、noteに「Canvaで画像を作る」という選択が組み込まれていますから、メッチャ便利ですよね。
ちなみに、スライドなどの資料もパワーポイントより簡単に、かつ、見映え良く作れそうな感じです。
8.プロフィールについて
プロフィール記事は、なるべく早く書いた方が良いと思います。しばらくは固定記事に据えましょう。
やがて「これ!」という記事が書けたなら、その記事を固定記事とします。このタイミングでプロフィール記事を、晴れて「プロフィール」に据え直します。
これがイイと、僕は思います。
そして、プロフィールは、何度でも書き直しましょう。
「編集」で書き直さずに、新たな記事で書き直すことをお勧めします。
自分の成長という、大切な『記録』になります。
◆〆
推敲のため読みなおしてみましたら、なんか偉そうですね 笑。
ゆかりちゃんに叱られないよう、今から頑張って、kindle本を執筆します。
僕は、ゆかりちゃんが大好きなのです。
※この記事は、エッセイ『妻に捧げる3650話』の第578話です
コメントしていただけると、めっちゃ嬉しいです!😆 サポートしていただけると、凄く励みになります!😆
