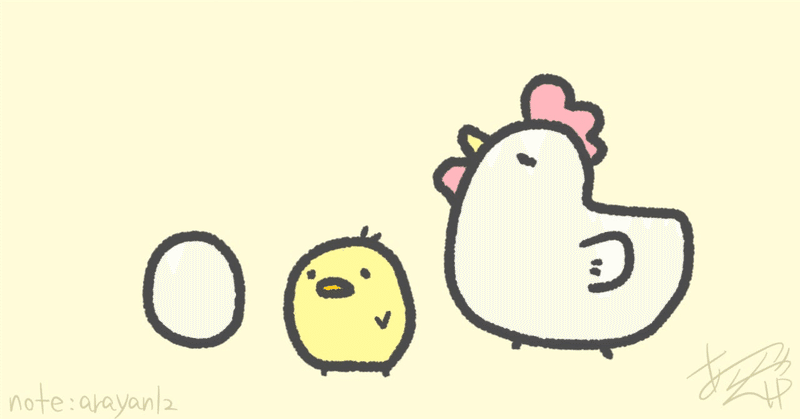
親という幻想について
このところ「親」である自分について、ずっと考えています。
きっかけになったのが、以下の記事です。
この方はどういうわけか、いつもボクの思考の味噌蔵をかき回してくれる記事を書かれるのです。
記事の中で、育児記録は自分の中の「良き母」を強化するためのものだったと振り返っておられます。
ほかいろいろと興味深い洞察をされていました。
はて。
振り返ってみて、自分は「良き父」だったのだろうか。
以前に、家事育児は出産と母乳授乳以外は全部人並み以上にこなしたと豪語(?)した覚えがあるのですが、その度に「父親」という自覚はあったのだろうか。
風呂に入れた、離乳食を作った、公園に散歩に連れてった、一緒に遊んだ、などなどの小タスクはそれなりにこなしました。
しかし親として何かを教えたっけか。
親としては無自覚だったかもしれない。
そもそも「育てた」のか。
勝手に「育った」のではあるまいか。
義母が何度か「鷹揚に育てている」と称していたのを思い出しました。
あれやこれや・やいのやいのと言ったときもありましたが、すぐにメンドくさくなって言わなくなったように思います。
いわゆる「しつけ」や「お手伝いをさせる」なども、ほとんどしませんでした。
そのあたりは保育園とベネッセ(しまじろう)に任せてしまったのかもしれない。
いろいろな経験をさせてあげようとかも、あまり思わなかったかもしれない。
息子は中二くらいまでは成績優秀だったのですが、どうやら低きに流れとるな、と傍観していたら、高校受験失敗、大学受験も失敗、一浪後も志望校に行けず、今は一留中、ああやっぱり案の定だったという感情しかありません。
自分の中の「親」が発現していれば、途中で何とか食い止めたかもしれない。
低きに流れたのは自分自身だっかも。
子どもたちもボクのことを、一緒に過ごし、たまにパスタを作り、たまにアホなことを言うオッサン、くらいにしか思ってないかもしれません。
さて、思考の味噌蔵に迷い込んで前頭葉から煙が出てきたら、ボクはいつも太古の昔に思いを馳せることにしています。
だいたいのことは、この時代が解決してくれます。
現生人類がまだ小さな群れで行動していた旧石器時代です。
まず夫婦という婚姻関係は無かったはずです。群れを作るような類人猿はたいがい乱婚状態だからです。
なので親子関係というものは、母子関係しかなかった。
そしておそらくですが、群れとして子どもを育てていたでしょうから、その関係も濃いものだったとは思えません。
いつまでも母子べったりだと妊娠の機会が減るので、母子は離す力学が働いたはずです。乳母などが近代でも各地で残っていたのはこのためでしょう。
母性愛が出現したのは資本主義社会からという説があるそうです。
ボクはそんな最近でもないと思っていますが、少なくとも有史以降にできたものでしょう。人類史にとって、ごく最近です。
つまり旧石器時代が終わって、国家らしきものができて以降でしょう。
国家の施政者・統治する者にとって、旧来の「群れ」は解体しなければならない存在です。
なので代替となる「家族」を発明した。
宗教という道具を用いて、永遠の愛に価値があるとして一夫一妻制か一夫多妻制を推奨した。
女性には「良き母」という幻想を抱かせ家庭を守らせ、男を労働や戦争など使役しやすいようにした。
そうして「家族」を維持させて「群れ」の再生を防止したのです。
要するに「良き親」像は(夫婦も)社会の要求によって作られたものなのです。
それが幻想であると暴かれつつあるということは、社会よりも個が強くなったからと考えています。
個が強くなると、かえって太古の昔へ戻っていくようなこともあるのだ。
以前に、個が強くなりリベラル化が進むと、エントロピーが増大して低きへ流れるようになり、ロングテールな社会に突き進むと書いた覚えがあります。
「夢を追い、自分らしく生き、巨人の足を見上げる」
もう人類は、晩婚化、少婚化、少子化を止めることはできないかもしれません。
いみじくも、さきほど息子の顛末話で「低きに流れたのは自分自身だっかも」と書きました。
うーむ。
となると夫婦関係も、、、、
と、また遠い目になる。はーあ。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
