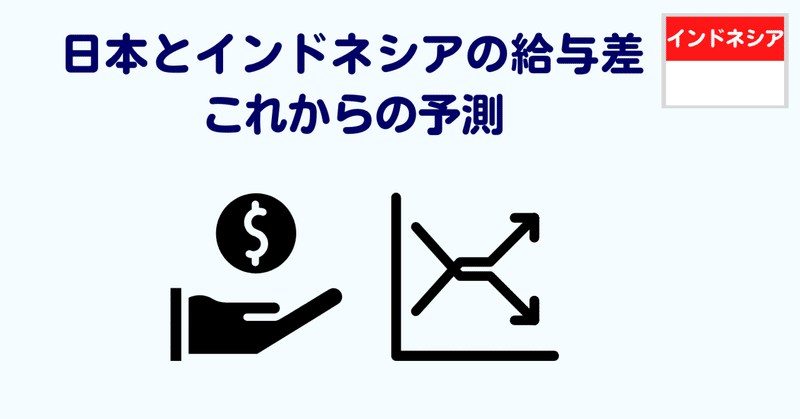
日本とインドネシアの給与差をめぐる級友との会話
授業のあとクラスメイトと、ストリートフードの日本めしを食べながら経済にまつわる話をしました。なんで同じ仕事をしているのに給与にこんなに差があるのか、物の値段はそこまで変わらないのにという話です。
それらしい話になっていますが、適当なことを結構言っていますので、二人の世間話だと思って聞いていただければ。
友:前にも聞いたかもしれないけど、インドネシア人が日本で働いたら給与はいくらくらいもらえるだろうか?
私:職種によるね。そうだな、よくあるのは農業、漁業、病院、介護職だけど、最低でも月に2000万ルピア(20万円)はもらえるだろうね。でも、生活コストもかかるから、その分無くなるよ。
友:前にインドネシアの稲作の生産性は日本より高いと言っていたじゃない(インドネシアは3期作なので3回転するため、仮に面積あたりの収穫量が日本の半分でも年間の収穫量は日本の1.5倍になる)?なんで日本の農業の方が高い給料を払えるのだろうか?
私:米はちょっと特別かな。政府が高く買い上げている。米の値段は日本とインドネシアでは4、5倍は違うからね。でも日本とインドネシアの給与差は、生産性や付加価値の差を反映していないのは確かだね。
友:生活コストがかかるからその分給与も高くなるんだとよく言うんだけど、その理屈がいまいち分からないんだよね。給与は生産性や成果物で決まるものなんじゃないんだろうか。そうじゃないと、誰かが損をしたり得をしていることにならないかな。
生活コスト高いから給与も高くしないと大変だというのも分かるけど。
私:あー言いたいことが分かってきた。給与は国をまたぐと生産性はあまり関係なくなるね。物と違って人は動かせないからバリアで守られているんだよね。
人を介さなくなればなるほど物の値段って世界共通であまり変わらないじゃない。電気製品や車もそうだし、原料や肉や穀物も市況があるから。
場所に関係ないのは基本より高く売れる場所を求めて移動するから、アービトラージが働くでしょ。人は移動できないじゃない。
友:バリア?物の値段にあまり差が出ない話はわかるけど、日本の給与がインドネシアの給与より高い話とどう関係するのかよく分からない。
私:たとえばホテルやレストランの従業員の給料が、生産性に関わらず日本とインドネシアで大きく違うでしょ。インドネシア人を物のように自由に移動させて日本で働かせれば、給与は似たようになっていくはずだよね。そうならないのは国がバリアや障害を設けているからでしょ。
友:あーそのバリアね。言っていることが分かった。バリアがない職種もあるよね。遠隔でオンラインでできてしまう職種とか、どこに住んでいても通信環境さえ整えればあまり生産性は変わらないはず。そうなると給与は生産性に従って決まるようになるはずだよね。
私:プログラマーとかそうなっているというよね。実態は分からないけど。どこに住んでるとかは成果物と関係ないから、その人の生産性で給与が決まってくるんだろうね。
友:そうなんだよね。本来であれば報酬は成果物で比較すべきなのに、インドネシアの生活コストは低いからお前の報酬は低くていいだろと言われて、報酬を下げられているんだよ。なんかごまかされている気がして納得いかないんだよね。
私:遠隔の仕事でそういうことを言われるの?どんな仕事?シンガポールの会社とか?
友:オリンピックに出る学生のプライベートレッスンを受け持っているんだけど、インドネシアは生活費が安いからと言われて、仲介業者に報酬を安くさせられているんだよね。
ネゴシエーションのクラスで勉強したことを活かして交渉してみようと思う。
私:オリンピックって、数学オリンピックのこと?(こいつ頭がいいと思っていたけど、数学オリンピックの出場者に数学を教えられるくらいできるの??)
ー 話はネゴシエーションに続いていく ー
日本の給与が近隣諸国より高い時代がいつまで続くのか分かりませんが、今のところ日本の給与が高くてうらやましいという話はインドネシアでよく聞きます。
ちなみに、この差は昔と比べると縮まっていますので、20年くらいたつと様変わりしていると思います。さらに、給与差が縮まっているのに合わせ、日本の物価はデフレで下がり続け、購買力平価でみると差はかなり縮まってきています。
2045年はインドネシアのGDPが日本を抜くと言われています。昔は2050年に抜かれると言われていましたが、追いつかれるペースが上がっています。
わたしは日本の人口減のペースを見るともう少し早く追いつかれるかもなと予想しています。
1990年代の初めにバブル景気が崩壊した直後あたりの頃でいうと、わたし(大学生)が日雇いバイトで稼ぐ日給1万円と、中国の上海で一家を支えるアラサーのサラリーマンの男性の月給が同じでした。
1992年にホームステイ先の家庭で聞いた話です。今だと職種にもよりますが月給50~100万円はもらっているんじゃないでしょうか。日本より上海の方が平均給与は高いと思います。
物価でいえば、水餃子や小籠包が1籠(ロン)1元、ビール大瓶1元、計2元で飲み食いできました。ビールはぬるかったですけどね。
当時は1元25円、93年94年は1元17円くらいで、今よりずっと元は高かったんです。
1万円を闇両替(93年まで兌換券の時代でした)したら1か月では使いきれなかったです。
2004年から2009年にジャカルタに駐在したとき、最低賃金は月100万ルピア(当時のレートで1万円くらい)を切っていました。2024年は500万ルピア(今のレートで5万円)を超えたので、5倍以上になっています。
わたしが当時もらっていた給与は、おそらく今同じポジションで行っても変わらないはずなので、差はかなり縮まったと言えます。
当時我が家は住み込みのメイド1名、子守りの通いナニー1名、妻用の運転手1名、計3名の雇用を生み出していました。それでも月額3万円くらいのコストだったはずです。
未来の給与と社会を予想する
日本もようやく賃金上昇の時代に入ったように見えますが、周囲の国々の賃金はもっとハイペースで上がっているので、差は縮まり続けると思います。
日本より給料の高い国だらけという時代がやってくるでしょう。
日本は物価が安い国になり、外国人観光客向けの高級レストランやホテルとローカル向けの店に分かれる途上国のような光景が広がるかもしれません。
今もそうなりつつありますが日本を出て外国で稼ごうという野心的な若者が増えるんじゃないでしょうか。わたしが若ければ絶対にやると思います。
逆に今後は日本に出稼ぎに来たいという外国人は減ると思います。日本に来るのは日本のことが好きだったり興味がある人たちが中心になるでしょう。
そうなると、日本はますます労働力不足に陥って、背に腹は代えられず移民を増やそうとするでしょうが、そう思ったときはもはや手遅れになっているような気がします。ちょうど少子化政策が手遅れになっているような感じのイメージです。
高齢化で労働者不足に陥る国は増え続けますから、中国、韓国、台湾、シンガポールとも取り合いになるでしょう。
そのころわたしは70歳を超えて病院や老人ホームのお世話になっているかもしれません。そして、わたしのお世話をしてくれる人はもはや人間ではなくロボットになっているんじゃないでしょうか。
あるいは、それさえもなく、老人同士で支え合う時代になっているかもしれません。
どこかのベンチャーが開発したモビルスーツを着用し、軽々と老人を持ち上げ入浴させたり、物を移動させたりできるようになっているはずなので、何も心配はいりません。
そして、そのころインドネシアは全盛期を迎え、わたしのクラスメイト達は40代で大活躍しているかもしれません。
わたしは彼らの活躍を楽しみに余生を送っているでしょう。
また妄想の世界に入ってしまいました。お付き合いいただき申し訳ありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
