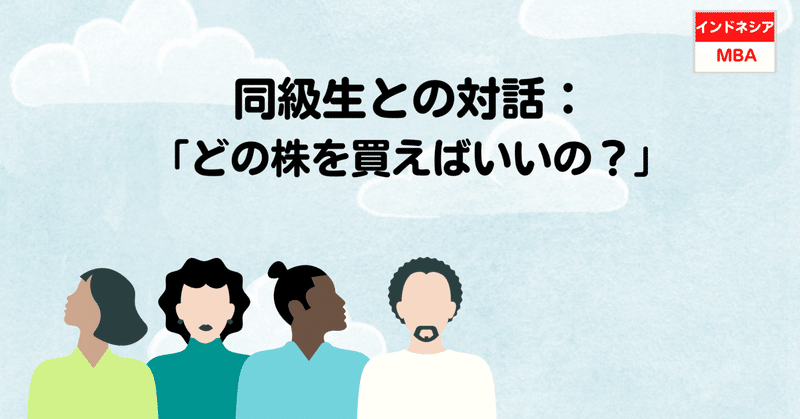
個別銘柄の選び方の実例(インドネシア編2005年)
クラスメイトに個別銘柄をどうやって選んでいるかと聞かれ話をしましたので、記事にします。
インデックス投資100%で全く問題ないのですが、それではおもしろくないので、半分までなら個別投資に回すので問題ないと思うよというところから始めています。
また、この話は今から20年前のインドネシアの話を元にしているので古い話になります。
ただ、古い話とはいっても、考え方を今の時代に当てはめれば役立つだろうと考えて話をしました。
このやり方は、わたしが日本アジア投資にいた時代に、インドネシアの投資先を探すのに使っていました。なので、仕事で必死で考えたことを利用して個人の投資に応用したことになります。未上場企業に投資をするか上場企業に投資をするかの違いだけです。
1.インドネシア人が豊かになると何にお金を使うか考える。
エンゲル係数という言葉がありますね。
家庭で消費する費用のうち何割を食費に使っているかという数字です。
貧乏人はこの数字が高くなります。
豊かになるということは、食費以外にお金を使うようになるということを意味しています。
ただ、それだけでは足りません。もう少しひねる必要があります。
同じ食べるでも、食べるものの内容がどう変わっていくかまで考えを及ぼさないといけません。
例えば、貧乏人が食べるものは糖質=炭水化物です。これは万国共通で、アメリカでもそうです。糖質抜きなんてお金持ちの発想ですよ。お腹いっぱいになるための必要コストが何倍も違います。
そして、変化を想像すると同時に、今のインドネシア人が日本だとどの世代に当たるのかを考えるのも大事です。例えば、祖父母の時代だなとか、両親が若い頃だなとか、わたしの学生時代だとか、当てはめるのです。
そうすると、彼らの食事風景まで思い浮かぶようになり、より具体的に詳細に投資対象をイメージできるようになります。
食べ物でいえば、わたしの両親の世代、新入社員のころの役員の世代はアメリカかぶれをして洋食が好きでした。パン、コーヒー、紅茶ですね。わたしの祖父母の時代に当てはめれば卵や乳製品がまだ高級だった時代です。こういう流れが輻輳(ふくそう)して来ている感じでした。
こういう現象を総合して、わたしが当時立てた食生活の仮説はざっくりと以下の2点でした。
①肉をたくさん食べるようになるだろう。
②乳製品の消費が増えるだろう。
この2つが起きたときに業績が伸びる会社はどこかという視点で探しました。
①だと、牛、豚、鶏のうち、インドネシア人の圧倒的に食べるのは鶏肉だから鶏肉に絞りました。養鶏場、卵の会社、鶏の飼料、外食産業のうち、鶏の飼料で圧倒的にシェアナンバーワンの会社だった、チャロンポカパンインドネシアに投資をしました。鶏肉の消費が増える➔養鶏場が増える➔エサが必要になる。
チャロンポカパングループはタイで3本の指に入る巨大財閥で、インドネシア法人を持っていたのです。
チャロンポカパンインドネシアは鶏の飼料からスタートし、養鶏場を次々に参加に収めながら急成長しました。この株はなんと100倍になっています。わたしが買ったタイミングからは50倍近くになっています。
②だとインドミルクをやっているインドフードがターゲットになりました。ここには結局投資をしませんでした。競合先があり、2番手、3番手の位置づけだったからです。売上はトップだったかもしれませんが、ブランドイメージはそんなに良くはなかったです。
それと、コングロマリットディスカウントという考え方があり、インドフードの主力事業はインスタント麺だったので、乳製品は一部門でしかなかったというのも投資を躊躇した理由です。
当時中国ではモンゴルミルク、ベトナムではビナミルクが上場して無茶苦茶株価が上がっていたというのもあります。インドネシアにはこの流れは当てはまりませんでしたね。抜群のマーケットがありながら、そこに当てはまるプレーヤーがいなかったのです。こういうところは難しいです。
その後、製パンが上場したので買おうと思いましたがやめました。ヤマザキパンみたいな会社になるぞと期待していたのですが、あまりに株価が高くなりすぎていたので、ちょっと待とうとなり、今に至っています。Nippon Indosari Kopindoです。
社名に日本とついているのは、もともと敷島製パンのJVを母体にしているからです。ブランド名はSari Rotiです。
食べ物以外でいえば、わたしは美容が伸びると思いました。具体的には化粧品ですね。特に、ローカルブランドの化粧品が、日本の資生堂、カネボウ、コーセーみたいに育つんじゃないかと期待しました。
ベンチャーキャピタルとしても探して当時上場していた会社に投資をしようと検討したことがあります。結局しませんでした。マルティナベルトという会社です。
いい会社ではあったので、日本のアットコスメ(株式会社アイスタイル)に紹介したこともあります。
他にも美容整形的なクリニックがいけると思い探していました。
わたし個人としては、マンダムのインドネシア法人の株を買いました。女性用の化粧品はローカルブランドはなかなか育たず、海外ブランドが主流だったのに、男性化粧品は圧倒的にマンダムで、しかも急速に伸びていたんです。
日本に輸出するという安定売り上げもあるし、経営もしっかりしてそうだったので選びました。ここは手放してしまいました。売ったときからさらに倍以上に上がりました。久しぶりに株価をみたら、なぜか私が買ったころの株価に戻っていますので、何かあったんでしょうね。
2.日本の高度成長時代の消費行動を参考にする。
当時わたしは何度も「会社の寿命」「続会社の寿命」という本を読み返しました。そこには年代ごとのトップ100社がリストになって本て、成長期ごとに主要な産業が入れ替わっていくのがよく分かります。
3種の神器とか、3C、それらのブームが生まれた背景、オリンピックや万博のような国際イベントがあるとか、新幹線や高速道路網ができるとか、新卒の給料が当時いくらでどれくらいのペースで上がっていったのかとか、複合的に考えます。
あの会社が何位から何位に上がったんだ、へーで終わらせてはいけません。なんでなんだろうと考えるのが大事です。ライフスタイルの変化があったり、日本経済の状況、インフラが変わったり様々な背景があるのです。
有名なのが、一人当たりGDPがいくらになったら何が売れ始めるのかという法則です。わたしはこの数字をいろいろな国に当てはめながら、インドネシアにはどのように当てはまるのかを考えました。
当時は雁行(がんこう)経済と言われていました。
雁というのは隊列を組んで飛んでいきます。先頭を飛ぶのは日本、次を飛ぶのがNIES(韓国、シンガポール、台湾、香港)、次がASEAN6か国、という感じです。同じ道をたどりながら順々に経済成長していくというわけですね。
日本企業のアジア進出もこの順番で起きていて、最初は縫製業、次に繊維が進出、次に家電の組み立て、家電部品、自動車の組み立て、部品と進んでいきます。縫製は安い賃金を求めてさまよいます。設備投資がミシンくらいなので動きやすいのです。
話を戻し、当時わたしが絞ったのは自動車産業でした。3C(カー、カラーテレビ、クーラー)の一つです。クーラーとはエアコンのことです。わたしはいまだにクーラーと言ってしまい、年寄臭いと言われています。
経済学では、消費者が豊かになって低級から中級、高級に代替が進むという考え方があります。いままで貧乏人はスクーターに一家4人で乗って移動していたのが、ファミリーカーを買って車移動に変わるという流れです。
道路の建設も増えていくモータリゼーションの時代です。一人当たりGDPが3000ドルから5000ドルで起きると言われています。

当時シェアトップはトヨタ、2位はホンダ、ダイハツだから、これらと組んでいるアストラインターナショナルがよさそうだとまずは考えました。
しかし、調べていくうちに、アストラインターナショナルは素晴らしい会社なんだけど、インドフードと同じようなコングロマリットディスカウントがある、要は多角化しすぎているのが気になりました。投資したくない産業も含まれているわけです。
なので、100%自動車産業にベットしている、アストラオートパーツに投資をしました。アストラインターナショナルが80%の株を持っている上場企業です。
ここは、多くの自動車部品企業がインドネシアに進出するときのJV相手にしている会社です。なので、自動車部品ファンドに出資をしているようなイメージの会社ですね。
決算書も一風変わっています。単独のビジネスはほとんどなく、合弁先の連結収益を合わせたものがこの会社の収益になっています。
ここは思ったより株が上がりませんでした。利益が伴わなかったのです。日産の下請けいじめが問題になっていますが、完成車メーカーに利益を吸い上げられ、部品会社は売上の伸びに比べるとそこまで利益を出せなかったのです。
予想と外れる展開は常時起こりかつおもしろいので,、いつかご紹介したいです。
そうはいっても、売り上げはかなり伸びていて、株価もインデックスよりは上がっています。
あとは、アストラグラフィアという、富士ゼロックスの代理店に投資をしました。わたしは日本にいたとき、富士ゼロックスの経営とビジネスモデルにとても興味を持っていて、富士ゼロックスのようにこの会社も成長するんじゃないかと期待をして投資しました。
ここも思ったより伸びませんでした。インデックスの上昇を下回るレベルです。ここはたぶん経営力の問題ですかね。紙が減るという全体的な流れをもう少し考慮すべきだったと反省しています。
3.高度成長のときに株価が上がる業種は何か考える。
高度成長のときに伸びる産業というのは、インフラ整備にかかわる産業です。具体的には建設会社、セメント、鉄、造船、海運、運輸などです。それとGDPが伸びるときは同じペースで銀行が成長するという法則もあります。
要は、全産業が成長していくと、それだけ成長資金も必要になるし、庶民の余剰も増え預金残高も増えていくから成長するんですね。
それでいろいろ調べてベンチャーキャピタルとして、建設会社とセメント会社に出資しました。
個人投資としては銀行に出資しました。ベンチャーキャピタルとしてもファイナンス会社に投資をしようといろいろ探して、特に物販が伸びるので割賦販売のクレジット会社がいいんじゃないかとか、オートバイではなく4輪車のオートファイナンスが伸びるかもとかいろいろ周りましたね。
ベンチャーキャピタルとして出資をした金融業は、オンライン証券です。イートレーディングというまだ売り上げ1億円の会社が黒字が見えてきた段階で出資しました。創業2年目のタイミングです。
業界トップというか、当時その会社以外にオンライン証券はなかったです。今では業界で1位、2位のトランザクションを争う会社になっています。日本アジア投資が投資をしたあと、大宇証券がやってきて投資をして、日本アジア投資がリーマンショックで厳しいときに、大宇証券に売ってしまいました。具体的にどれくらい儲けたかは言いませんが数倍になっています。IRRはVCのターゲットである30%をはるかに超えています。
大宇証券はその後Mirae証券に買収され、イートレイディングはMirae証券に名前を変えています。
個人で買った株はBank International Indonesia (BII)で、もともとシナールマスグループの銀行でした。アジア通貨危機で痛んで、私が買ったあと、半年くらいでマレーシアの国有銀行May Bankに買収されてしまいました。買値の倍です。
まったくインサイダーではなかったのですが、当時Maybankとシャリアファンドをやろうという話が持ち上がっていて、何かの縁かとは思いました。
わたしのルールでいけば、本当は業界トップのBank Central Asia(元サリムグループで今はタバコのジャルムグループ)に出資をすべきだったんですが、高すぎました。当時から銀行のなかでも図抜けて高かったです。今も高いままです。何度か買おうと迷って買っていません。
PERが高い割高株だと思って避けても、そういう株は永遠にPERが高いとよく言われていて、この株はその典型です。
4.世の中の動きに対する感度を高める方法
いくつかやり方がありますので、おススメの方法をいくつかご紹介します。
(1)定点観測をする
これはわたしはずっとやっています。今は近所のインドマレットというコンビニ、ボルマというスーパーマーケット、CiWalkというモールに定期的に行き、売り場とテナントをチェックするのと、どんな客層かも見ています。
どんな服装か、年齢構成、だれと一緒に来ているかなど。支払金額、支払い方法も観察しています。スマホ決裁、カード決済、現金払いとか。
シャープで働いていたときは家電売り場です。毎月家電量販店に行き売り場を観察していました。あとはリサイクルショップですね。売れ筋が変わるのか売り場の変更があったりするのがとても参考になります。
どの売り場が混んでいるとかですね。
三菱自動車のときも週末の決まった散歩コースがあり、三菱自動車、ホンダ、トヨタ、日産と各ディーラーをめぐり、リサイクルショップ、スーパーマーケット、駅前商店街を回っていました。道を歩きながら走っている三菱自動車の数を数えるというのもやっていました。
特定のブランドの車の数を数えるのはバンドンに来てからもやっています。バンドンでは現代自動車と五菱自動車の数を数えます。韓国と中国のメーカーで、少しずつ日本メーカーの牙城を切り崩していっています。
同じ場所を時間を変えて訪れ観察すると、必ず何か変化していることがあります。それらを見つけ、なぜかを考える癖をつける訓練です。場所や対象はもうなんでもいいです。人それぞれに得意分野がありますから。
お金儲けのうまい人は、風が吹けば桶屋が儲かる的な連想力がある人なんです。これが伸びるということはあれも伸びないとおかしいとか、次にこういうことが起きるだろうと予測できる人です。人より先に気づいて動くことで儲けます。
この能力を高めるのに、定点観測を利用しながら考える癖をつけるのです。
(2)ビジネスモデルを掘り下げる
そういう環境にいないと難しいかもしれません。
わたしは学生時代、起業家を目指していたのでバイトを通じてなんでこれをしないのかとか、ここを変えたらよいんじゃないかとよく考えていました。
ベンチャーキャピタルに入ってからは、たくさんの経営者に会い、いろいろな業種も見るので、とても勉強になりました。先輩も教えてくれるし経営者も教えてくれるのです。
儲かる会社というのは仕組みがある会社です。再現性を高めるには誰がやっても同じ結果がでる仕組み化がとても大事なんです。しかもコロンブスの卵的な言われてみれば確かにそうだと分かりやすいシンプルな仕組みは天才にしか作れません。
経営の天才としてはリクルートの創業者の江副さんがいます。彼が作った広告を取って雑誌を売るビジネスモデルは、対象を就職情報から転職、バイト、住宅、クルマ、結婚と横展開できるほど秀逸なモデルで、リクルートはこのモデルしかできないんじゃないかというくらい稼いでいるのは全部このモデルでした。
また、世界各地、全国各地にこのモデルを使ってマチコミ紙を展開する元リクがいたくらいです。
他にわたしが天才と思うのはブックオフの創業者で、俺のフレンチの創業者でもある坂本さんですね。複雑に見えるビジネスを儲かるところに焦点を当てて切り出して単純化する天才です。
例えば、リサイクルショップは今はもう少し高度になりましたが、ブックオフが革命的だったのは、古本屋につきものだった査定を一切しなかったことです。定価の1割で買って半額で売る、ただそれだけをやって一気に拡大しました。
あとは本を綺麗にするとか、古本屋特有の据えた匂いや薄暗さを消すというのもやりましたが、仕入れと販売を単純にしたところが一番のみそです。
わたしがベンチャーキャピタル時代に投資をしたフォー・ユー、今のセカンドストリートですね、この社長はさらに単純化して、本の重さだけはかって仕入れ値を決めていました。ゲオに会社を売却して、今は非上場になっています。
「俺のフレンチ」は、回転こそが収益拡大の源泉と考え、価格を下げて原価率を上げても回転させれば勝つはずだというビジネスモデルで、革命的です。
ビジネスモデルをよく考える、どうして儲かるのか仕組みを考える癖をつけ、すぐに理解できるようにセンスを磨くことはとても大事です。
人の考え方、結び付け方を勉強して、自分なりのやり方を身に着けるのが早いと思います。パターンはありますので、知識や経験を蓄積してどんどんレベルが上がっていきますから、最初は全くできなくても大丈夫です。
(3)自分の知人のなかでイノベーター理論の当てはめをする
マーケティングにイノベーター理論という非常に有益な理論があります。新しい物事が普及するときの順番を法則化したものです。全部この通りいくという訳ではないですが、1つの基準としてとても使いやすいものです。
ちょっと失礼な話ですが、わたしはイノベーター理論のイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティー、レイトマジョリティー、ラガードにそれぞれ当てはまる人を、対象分野によって柔軟に変えながら頭の中に持っています。
この人がこういうことを言い始めたぞ、次の段階に移行したようだなとかですね。
これをやると、世の中の動きがより実体を持って自分の中に入ってくるようになります。
例えば、電気自動車が売れ始めましたというときに、誰がどんな表情でどんな会話をしながら誰と乗っているかとか、どういう使い方をしているか、人に見せびらかしていそうだなとか、どういう文句を言っていそうかとか、人と結びつけると複合的な情報として入ってくるのがいいところです。
投資のタイミングはアーリーマジョリティーに入ったか入らないかくらいがベストです。事業リスクが大きく減るタイミングです。
当然競合先もいくつか出てきていて、そのなかで一番勝ちそうなところを選びます。
少し長くなりすぎたので、この辺で打ち止めにします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
