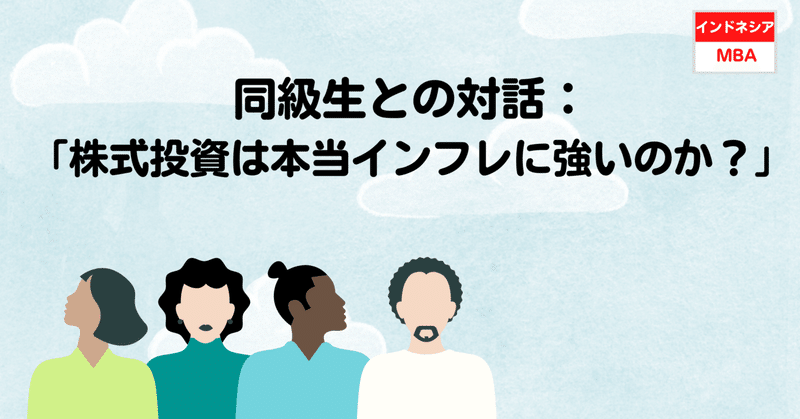
同級生との対話 株式投資は本当にインフレに強いのか
授業でファイナンスを習ったあと、今経済学をやっています。わたしがバンドン工科大学の学生は本当に優秀だなと感じるのは、授業で習ったことを自分の身の回りの出来事に応用したり、これまでの知識と組み合わせてさらに理解を深めようとするところです。
頭が良いだけでなく、知的好奇心があり、また様々な知識や出来事を複合的につなげていく能力がとても高いのです。優秀な人間の特徴を示しています。
本題に戻しますと、インフレと株価は本当に連動しているのか、腹落ち感がないうえに、実際の値動きも違うように見えるけど、という話です。
インドネシアはインフレの国です。インフレがどうして起こるのかといえば、通貨が弱いから輸入材の価格が上がっていくというのと、人口ボーナスの影響でしょう。
生産年齢人口(15~64歳)に対する従属人口(14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口の合計)の比率が低下し、経済成長を促すこと。人口ボーナス期では豊富な労働力を背景に個人消費が活発になる一方、高齢者が少なく社会保障費用が抑えられるため、経済が拡大しやすい。逆に従属人口の比率が相対的に上昇することを人口オーナスという。
さらに、労働力が増えてインプットが増える効果と、増えた労働力が収入を得て消費が増えることで需要が増えることで需要供給曲線が動いて価格が上がるという原理です。

他にも政府が最低賃金を上げることで、政策的に需要供給曲線を押し上げるという現象もみられます。インドネシアでは将来も給料が上がり続けるという期待値も高いです。
そういうわけでインドネシアではインフレが進んでいるのですが、クラスメイトから「なぜインフレで株が上がるのか、直近の現状だけ見るとインフレ率の方が株価の上昇率より高い気がするが、それはなぜなのか」と質問があり質疑応答しましたので書いてみます。
1.なぜインフレになると株価があがるのか
友:インフレ時に資産を守りたいのであれば株に投資をすればよいと聞いたが、インフレになるとどうして株価も上がっていくのかよく分からない。金の値段や不動産が上がってくるのはなんとなくイメージできるんだけど、どういう仕組みなんだろうか。
私:あくまでも理論上の話であって、実際には個別事情もあるから必ずそうなるというわけではないけど、インフレになると株価は上がるのは正しい。
例えば、インドフード(インスタント麺で世界最大の会社)で考えてみようか。
2007年にわたしがジャカルタにいたとき、インドミー(有名な袋麺の商品)は700ルピアだった。今はいくら?3000ルピア?15年で4倍くらいになったということだね。
もし販売数が同じ、Gross margin(粗利益率)が変わらないとしたら、売上と利益はどうなる?例えば100億個、30%だったとしたら。
友:100億×700が、100億×3000になるから、売り上げは4倍になるね。利益率が変わらないなら利益も4倍になるね。
私:株価はどうなる?2007年と今と同じPER(株価収益率)だっとしたら。
友:株式発行数が変わらなければ、EPS(一株当たり利益)が4倍になるから、PERが同じなら株価は4倍になるはず。
私:そうだよね。じゃあ、もう少し複雑にして、レストランにしようか。米、鶏肉、卵の価格が15年で4倍になったとしたら、レストランのCOGS(原材料費)は4倍になるということだよね。人件費の上昇もあるけど単純に4倍になったとして。
レストランは一定の利益が出るようにメニューの価格を設定するから、原価率を同じにして価格改定したとしたら、売り上げと利益はどうなる?
友:COGSが4倍でCOGS率が変わらなければ、値上げをして、売り上げは4倍、利益も4倍だね。それで、PERが変わらなければ株価は4倍になるね。
~インフレと同じように株価が上がっていく仕組みは理解した~
実際、Indofoodの株価は15年で4倍になっています。インドネシアのIndexも4倍ですから平均的な上昇率ということです。要はインフレによる売り上げ増はあったものの、販売個数を増やせていないか、インフレコストをうまく価格転嫁できずに利益率が悪化しているか、PERが下がったか、いずれかの現象が起きたのでしょう。
2.インフレ率の上昇の方が株価の上昇よりも高く見えるのはなぜ
ここ最近の話です。ロシアウクライナ戦争のせいで、小麦価格が上がる、原油があがる、アメリカがドルを引き締め始めたせいで対ドルでインドネシアルピアが弱含み、輸入材の価格が上がる、という現象が起きていて、いわば日本と同じ状態にあります。
日本の株式市場はインフレ以上に上がっていますが、残念ながらインドネシアの株式市場はインフレ率と同じようには上がっていません。
それはなぜなのか、いくつかの仮説を説明しました。
インドネシアの株式市場が魅力に欠けるから
インドネシアの株式市場は、特に大型株になればなるほど外国人投資家の比率が高いよね。
(そうだね。授業でも出てきたね。)
なんでインドネシアに投資をするのかといえば、わたしもインドネシアに投資をしているから分かるんだけど、成長力が高いからでしょ。人口ボーナスはまだ続くじゃない。
(2040年まで続くと言われているね。)
でも、インドネシア投資はリスクもあるでしょ。例えば、授業でも出てきたけど、上場企業なのにファミリー企業並みのガバナンスだったりするじゃない。公私混同がすごいし、不透明なグループ取引だらけじゃない。
それに、インドネシアの証券市場は流動性が低いから、いざ売りたいと思ったときに売れないんだよね。外国の機関投資家が抜けた穴を、じゃあインドネシアの機関投資家や個人投資家で埋められると思う?埋められなかったらどうなる?
(場合によるけれど、機関投資家が引くタイミングだときついね。需給バランスが崩れて株価が暴落するんじゃないかな)
だよね。流動性は低い、価格のボラティリティーが高いとすると、ダモダラン(NYUのDamodaran教授のこと。Valuationで習う)じゃないけど、より高いリターンを求めるじゃない。高いリターンを求めると株価はどうなる?
(リスクプレミアムの話でしょ。割引率が高まるからNPV(現在価値)が下がる、株価が下がる、という計算になるね。実際インドネシアはカントリープレミアムつけられているしね。)
アメリカは今金融引き締めに入り始めたから、ドルは高くなっているし、相対的にドル建て投資の利回りは上がるとなって、投資資金はアメリカに流れるでしょ(ドルキャリーの解消:ドル売り現地通貨買いから、現地通貨売りドル買いに戻す)。この局面であえてリスクを取る必要もないなとなるじゃない。
まずい状態になると、株も通貨もたぶん債権も下がる、トリプル安というやつだよね。そうなると逃避が始まっている証拠だから気を付けないけど、個人が投資を始めるには絶好のタイミングだと思うよ。
インフレによるコスト増を価格転嫁できず利益率が悪化?
これはあくまでも可能性なんだけど、よいインフレと悪いインフレでいくと、今は悪いインフレだから株価が上がらないということは考えられる。
経済学では価格は需要曲線と供給曲線の交点のEquivalentで決まるよね。需要曲線が高まって自然と価格が上がっていくのはよいインフレなんだけど、需要増を伴わない価格上昇の可能性が結構あるよね。今回は戦争の影響によるコストアップだから、供給側の一方的な上げでしょ。
そうなると、商品の性質(価格弾力性)にもよるけれど、需要が下がる、供給したくてもできない、仕方なく利益を犠牲にして価格を下げて販売量を確保しにいくという可能性がある。
しかも、価格が高くても買わざるを得ない商品(価格弾力性が低い)があって、そっちに可処分所得が分配されてしまうから、他の消費はさらに影響を受けてしまうよね。価格弾力性の高い商品を扱っている会社は価格に転嫁できず、利益は下がって株価も落ちると思う。
悪いインフレを需要曲線で描くとこんな感じです。

三角形の面積が小さくなっていることがわかりますでしょうか。Consumer surplusとProducer surplusがともに減少し、経済活動に伴う利益が減少します。個人消費が落ちているんです。その分世の中をめぐるお金が減っているということでもあります。
同じインフレでも、需要の増加に伴って価格が上がる時はこの三角形の面積は大きくなります。個人消費が伸びてお金ががんがん世の中をめぐっている感じです。
でも長い目で見れば大丈夫。株価はこういう上げ下げはいつものことで、結局は上がっていくのは歴史が証明している。気にせずに投資をしてください。
話はどういう株に投資をすべきか、やはりインデックスに投資をすべきかの話に続いていきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
