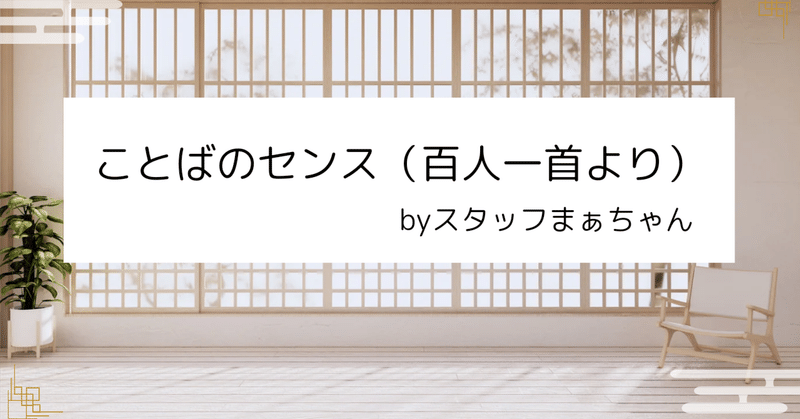
ことばのセンス(百人一首より)byまぁちゃん
こんにちは!スタッフのまぁちゃんです。
最近、大河ドラマを観ながら「しばらく古典を読んでないなぁ~」と思い立ち、久々に、百人一首の本を開きました。
高校時代、授業や受験勉強で学ぶ中で、古典、特に平安時代前後の作品が好きでした。
言葉選びのセンスと、表現の豊かさや品の良さにグッとくるんですよね。
何とも言えない人間くさい感情、ささいな季節の変化、自然の美しさを、豊かな表現や「くすっ」と笑える表現で描かれた作品がたくさんあります。
本音を言うと、この時代の作品は恋愛モノが多いので、そこにテンションが上がる恋愛オタクなだけかもしれませんが…笑
教科書にはマジメな体裁で載っていますが、惚れた腫れたの男女模様が描かれていることも多いので、おもしろいと思います。
※以下現代訳や解説は、ざっくりとでとらえてくださいね!
今回は、百人一首から1つご紹介します。
「春の夜の 夢ばかりなる手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ」
(春の短い夜の夢のように、すぐに醒める一夜の手枕のせいで、つまらない浮き名が立ったりしたらもったいないではありませんか)
★「かひなく(甲斐なく)」に「腕(かいな)」がかかります
二条院で貴族たちが集まって、夜通しおしゃべりをしていた時のこと。
周防内侍(すおうのないし)が何かに寄りかかって「枕がほしいものです」とつぶやいたところ、大納言・藤原忠家が「これを枕にどうぞ」と自分の腕を差し出しました。
「私と一緒に一夜を明かしませんか?(ワンナイトしませんか?笑)」という、さらっとした口説き文句の冗談。(みんなの前でのことなので、ジョークですね)
それに対して詠んだのがこの歌。
相手を落とさず、自分の下げず、「ご冗談を…笑」と軽くいなしつつ、センスの効いた歌がさらっと出るのがなかなかなところ。
平安時代、宮中はこういったセンスのある会話を楽しむ場でもあったそうです。
まぁ、今だとセクハラで訴えられそうですが笑
ちなみに、これが忠家の返歌です。
「契りありて 春の夜ふかき手枕を いかがかひなき 夢になすべき」
(前世からの深いご縁があるのに、この春の夜ふけの手枕を、ただの春の夢にしてしまうのはもったいないじゃないですか?)
口説き慣れしてそう…笑
百人一首は、ある貴族が歌人の藤原定家に頼んで、別荘のふすまに100首の和歌(当時の和歌ベスト100的な?)を書かせたもので、一人一首×100人分で「百人一首」。
「かるた」になったのは400年後です。
当時の知性がつまった作品集。
ぜひ、気軽に触れてみてくださいね!
★メンタルに興味のある方はこちら↓★
オンラインサロン「パートナーシップ教室」https://lounge.dmm.com/detail/6595/
オンラインサロン「ココロの教室」https://lounge.dmm.com/detail/6614/
Madoyaca公式サイトhttps://www.madoyaca.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
