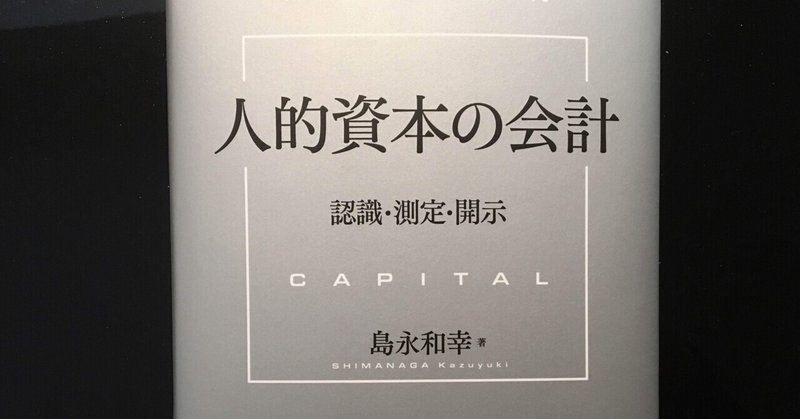
「人的資本」は投資家向けの非財務情報のコアとなる
会計の観点から人的資本を論じた著者の意欲が伝わってくる本です。
「人的資本」という言葉が我が国の企業経営者・企画部門の間で注目が強まったのは、2021年6月に東京証券取引所の「コーポレートガバナンスコード」が改訂された時からです。
コーポレートガバナンスコードとは企業統治指針ともいいます。企業はこれに従う必要はありませんが、これを満たしていない企業は投資家から見放されるので、実質的な拘束力をもつ指針といえます。
欧米企業は以前から「社員」について「Human Capital」という言葉を使っていました。「人=資本」という考え方はアダムスミスが「国富論」で展開していることが源流だと考えます。
経営の観点からは「人=人件費=費用」と捉えがちになりますが、最近では「人財」というような言い方もされてきました。コーポレートガバナンスコードで人は「資本」であると明記したことは我が国の企業人に対して社員に対する捉え方を変える契機になるものと考えます。
コーポレートがバンスコードは次のように改訂されました。
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである。
改訂点は、「人材投資」⇒「人的資本への投資」に変わったことですが、人を資本と捉え、これを非財務情報として開示することは投資家にとっても非常に有益なことです。
会社の有価証券報告書では、社員の平均年齢、平均給与、などが公開されていますが、これだけでは社員の年齢分布、多様性、などが分かりません。
定年の延長を検討している企業も多くなり、また終身雇用制も変わり、ジョブ型雇用などを導入する企業があるなか、その会社の実態を外部から観察できる情報としては、現在の開示情報では不足しています。
社員とのエンゲージメント、教育支援、離職率、年齢別分布、外国人社員、それらの男女別分布、などが分かるとその会社の勢い、多様性、能力開発などが分かり、投資家の投資判断の材料になります。
エンゲージメントの状況は、社員の意識調査を行っていることが第一歩になりますので、「意識調査を年1回行っている」という非財務情報を有価証券報告書に記載するだけでも、この会社は「人=資本」を意識していることが推察されます。
離職率が高いか低いかは、同業種の数値を比較することで相対的なことだけでも投資家には有益な情報になります。
年齢別分布からは、ベンチャー企業のような会社では若い人がどの程度いるのか、技術的専門性が高い会社では熟練の人を処遇しているか、などが推測することができます。
人的資本を会計上で計測することはなかなか難しいでしょうし、本書でもいろいろな試みをしていますが、こうした取り組みが多くなれば「会計」としても一定のルールが確立することでしょう。
数値化しやすい項目としては社員の教育費用などがありますが、コーポレートガバナンスコードの「人的資本」は会計上の取り扱いまで企業に求めていません。
会計上の開示には限界がありますから、非財務情報として開示することの方が投資家の投資判断の重要な材料になり、企業は「人的資本」をますます意識することになり、企業価値向上のつながるものと考えます。
昨今、議論されている他の非財務情報(TCFDなど)に対し、「人的資本」の関連情報は従来から投資家が求めていた情報、と考えます。
「人的資本の会計 島永和幸 同文館出版」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
