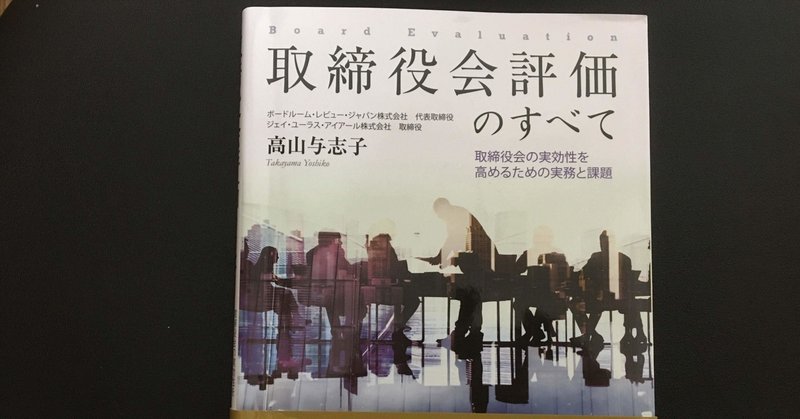
社外取締役の評価
良書が出版されました。実務的な観点からの現状分析と、欧米企業の例から我が国のコーポレートガバナンスの将来的な潮流を示しています。
我が国の社会の諸制度が欧米のそれを土台にしていることから、コーポレートガバナンスについても欧米型をフォローしていくことは仕方ないかもしれません。
その1つが取締役の評価です。社外取締役の評価をどうするか、と言ってもいいかもしれません。
「欧米とアジアの主要企業において、取締役会評価の歴史は長く、現在では一般的なプラクティスとなっている。他方、日本では、2015年に制定されたコーポレートガバナンスコードによって初めて取締役会評価が一般に知られることとなった」
東証が発表した取締役会評価の実施状況は、2018年12月末で82.5%の実施率です。
評価の方法について、JPX日経400の直近の状況は、筆者によれば、自社によるアンケート実施が208社、第三者によるアンケート実施が49社。さらに、その49社のうち、第三者インタビュー実施は15社、です。
第三者による社外取締役評価とはどのようなものでしょうか。
私が就任していた欧州企業では、紙ベースの自己評価とは別に、エグゼクティブリサーチ会社が第三者評価を行っていました。その会社から来訪を受け、インタビューを受けます。
インタビュアーはまず取締役会に出席し、実態を確認します。その上で来訪し、質問形式で2時間ほど。今の取締役会について、議長・副議長について、他の社外取締役について、自分自身について、と。
他の社外取締役についてコメントするのは気が引けますが、そのコメント内容も評価されますから、遠慮なく言わざるを得ません。彼のあの時の発言は議論を混ぜ返しただけで建設的ではなかった、とか言いました。
当然、自分自身についてもヒアリングを受けます。自己分析のようなコメントを求められました。語学力はどうしようもないハンディキャップですので、それについてコメントしました。「ハンディキャップだとは分っている」と。取締役としての利益相反についてもコメントを求められました。
こうした評価は、次の取締役会でインタビュアーから報告されます。書面とコメントによるフィードバックです。ああ、これは自分のことを言っているな、とか分かる内容です。
この評価そのものがアニュアルレポートに記載されたり、これを理由に解任されることはありませんが、自分の改善するべき課題だと認識することができます。
それ以外には、自分の専門性についてアンケートがあり、これも取締役会で報告されます。これは、取締役会メンバーの専門性が偏っていないことを公表するためです。地域的・性的にも専門性でも、多様な構成メンバ-になっていることを公表します。
我が国では、第三者による評価、特に社外取締役に対する上記の評価は少ないでしょうが、筆者は以下の3点が今後の我が国に与える影響だと記載しています。
①第三者評価の実施企業の増加
②第三者機関の名前の開示、および、当該企業とのその他のビジネスにおける関係性の有無の開示の要請
③第三者評価の質の確保のため、評価プロセスと評価の結果に関するより詳細な開示の要請
私の経験からもまったく共感する内容です。評価する側からするとビジネスチャンスかもしれません。
取締役会評価のすべて 高山与志子 中央経済社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
