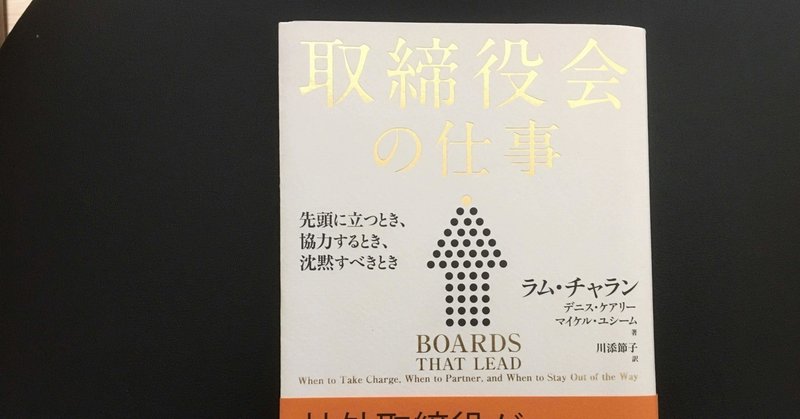
社外取締役の仕事 3つのポイント
本書が日本で発売されたのは2014年12月です。翻訳本ですから欧米のコーポレート・ガバナンスを前提にしています。
我が国では2014年に有識者会議が開かれコーポレートガバナンス・コードの議論が開始し、2015年にコードが策定されました。そこでは、上場会社は社外取締役を2人以上起用することが事実上義務化されています。
コーポレートガバナンスについて会社法では、取締役会設置会社、委員会設置会社、などを規定していますが、この中でも指名委員会等設置会社における委員会では、その委員の過半数が社外取締役である必要があります。
日本ではまだまだ社外取締役が過半数を占める会社は少ないのですが、欧米の企業では、社外取締役が過半数を占めるのは普通のことです。
本書はそうしたことを前提に書かれていますので、「取締役の仕事」といっても、「社外取締役の仕事」と言い換えることができます。
取締役には、注意義務と忠実義務があります。取締役は合理的な注意を持って自らの責任を果たさなければならない。もうひとつは、取締役は株主の代理として適切な受託者判断を下さなければならない、というものですが、著者は、そうした法律的な義務に加えて、実際の場面で必要な3つのポイントを挙げます。
①先頭に立つとき
②協力するとき
③沈黙するとき
私は2012年ごろから欧州の某企業の社外取締役と監査委員会のメンバーでした。日本でいう指名委員会等設置会社でした。社外取締役が半数以上を占めるだけでなく、取締役会の議長、各委員会の委員長は社外取締役でした。
そこでの体験からこの3つのポイントにはまったく共感します。
社外取締役は、「先頭に立つとき」「協力するとき」「関与しないとき」を見極めることは、重要な任務である、とします。
先頭に立つとき、とは、経営陣にやや迷いがある時、株主の利益を損なうような場面の時、そのような時に先頭にたって方向性を出していくことです。特定の株主からのイレギュラーな要求に対しては、社外取締役だけで議論を行い、経営陣を支えていきます。
協力するとき、とは経営陣が目指す経営を後押しすることです。大きな設備投資をしようとする時、組織を変えようとする時、幹部クラスを更迭せざるを得ない時、など経営陣が足踏みすることなく、決断を勇気を与えてあげることです。
関与しないとき、沈黙すべきとき、とは経営陣に対して干渉しすぎないようにすること、です。社外取締役が発言すると当然取締役会の議事録には残りますし、その発言の対応を経営陣は行わないといけなくなります。言いたいことがあっても、あえて黙っている。黙示の同意、と言ってもいいかもしれません。
本書は発行から時が経っていますが、このように社外取締役のプラクティスをまとめており、非常に実践に役に立つ良書です。
「取締役会の仕事 When to Take Charge. When to Partner. and When to Stay Out of the Ways ラム・チャラン、デニス・ケアリー、マイケル・ユシーム著 川添節子訳」によりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
