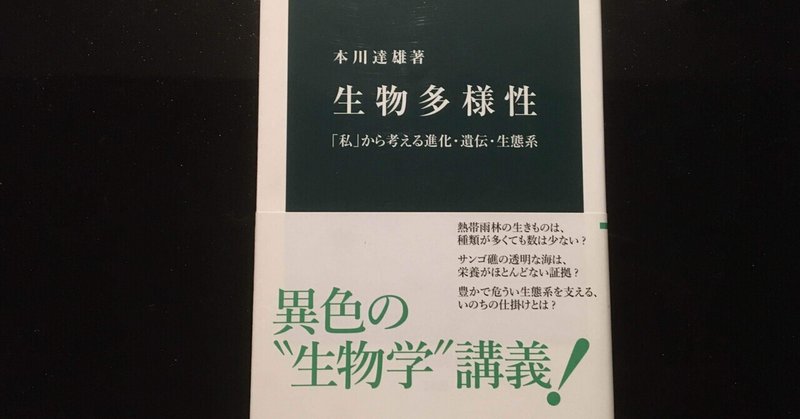
生物多様性を企業に求める動き
生物多様性については、それを唱えるだけでなく日常的において多様性を維持する活動を実践することが重要でしょう。
SDGs、ESGの視点から生物多様性を企業活動に求める動きが活発になってきています。脱炭素に向けた取り組みを企業の活動の「非財務情報」として公表することを目途としたTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures 気候関連財務情報開示タスクフォース)のように、TNFD(Task Force for Nature-related Financial Disclosures 自然関連財務開示タスクフォース)が2020年7月に発足されました。
政府、個人だけでなく、経済活動を主体である企業もさまざまな社会的課題に取り組むべき、ということです。企業は二酸化炭素排出の主体ですから率先して環境問題に取り組まなければなりませんし、それを財務情報と同じように非財務情報として投資家に開示することで、投資家の投資判断の一助になります。
生物多様性について企業が取り組む意義はなんでしょうか。
住宅メーカーでしたら、木材の伐採により野鳥の住みかが失われる、食品メーカーなら魚の捕獲しすぎで海洋生物の食物連鎖に影響を及ぼす、これら企業活動から派生する生物に対する影響を極小化することが企業が取り組む意義でしょう。
一方で、生物多様性を企業ミッションの中心に置く企業はこのようにすべての企業ではなく、特定の業界の企業になります。もちろん、自動車メーカーであっても、そのサプライチェーン(部品の調達の連鎖)の末端には、生物が関わっているでしょう。例えば、自動車の鋼材の元の鉄鉱石を採掘することでそこの生息する生物に影響を及ぼす、などですが、やはりミッションの中心箇所にいる企業は食品メーカーなどでしょう。
ただ、今の生物多様性と非財務情報の議論は、すべての企業に求めるような危うさがあります。直接消費者に販売する食品メーカーのようなB to Cの業種なら対応が必要でしょうが、食品メーカーに機械を販売するB to Bの業種では、生物多様性の活動はイメージが湧きにくく、社食の割り箸を廃止する、事業所周辺を清掃活動をする、などになってしまいます。そのような活動を「非財務情報」として開示するにはレベル感が低すぎ、仮に開示したとしても、CSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任)の1つに留まってしまいます。
企業はNPOではなく、利益追求集団です。利益を上げることで持続的な活動が可能になります。新しい資本主義、株主資本主義の見直しが言われるようになっています。しかし、社会、従業員、仕入れ先への責任もありますが、株主への責任を軽視するわけにはいけません。
脱炭素への取り組みは企業活動の中心点になりますが、生物多様性をあまねくひろく企業活動に網をかけるような動きは企業活動を停滞させ、脱炭素のグリーンウォッシング(greenwashing 環境配慮をしているように装いごまかすこと、上辺だけの欺瞞(ぎまん)的な環境訴求)のように、工場の敷地の片隅でドジョウを養殖するとか、形だけの「生物多様性」維持活動になりかねないと思います。
「生物多様性 本川達雄 中公新書」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
